
[更新日'00/3/1]

平成12年3月号(通巻第31号)
目 次
北海道大学大学院 教授 瀬尾 眞浩
北海道大学大学院 教授 瀬尾 眞浩

平成9年度からの金属材料技術研究所において、産官学の英知を結集して、強度2倍、寿命2倍以上の特性を有する鉄鋼材料、すなわち「超鉄鋼」の研究開発を目的とするSTX-21プロジェクトが推進されている。現在、STX-21プロジェクトは、着々とその成果を挙げており、21世紀を支える構造材料開発のための先導的指導原理の構築が期待される。20世紀の後半から資源枯渇、地球温暖化、廃棄物処理、リサイクルなどの問題が深刻化し、これらの問題を解決せずして21世紀の科学技術の発展は望めないであろう。また、トンネル内のコンクリートの劣化による落下などに象徴されるように、高度成長期における主要インフラも21世紀には更新期を迎え、それらの更新には多大な労力とエネルギーが必要となる。
21世紀の主要インフラに使われる構造材料に求められる課題は、高い安全性、長寿命性、環境調和性、優れたリサイクル性である。STX-21プロジェクトでは、これらの課題に答えるべく、環境に優しい溶接用高張力鋼、遅れ破壊に強い超高張力鋼、高効率発電用耐熱鋼、海でも錆びない鋼の開発を4本の柱として掲げている。また、その実現化のために原子レベルでのミクロ組織の制御と解析・評価、および材料の強度や破壊挙動を解析し予測する計算機シミュレーション技術をキーテクノロジーとして駆使し、ブレークスルーを試みている。
ところで、21世紀に情報化社会に突入するが、その実現には、インフラの整備が重要である。わが国では、現在のところ、容量の小さな電話回線にファクシミリを通し、インターネットまで通すという無理を重ねている。大前研一著「21世紀維新」によれば、アメリカでは同軸ケーブルを使い、モデムを入れてデジタル化と双方向化の機能を付加し、48%の家庭がすでに、このケーブル・モデムで結ばれているという。このケーブル・モデムはテレビ映像などの大容量の通信の他、インターネットや電話も乗り、画面を通じショッピングもできる。日本では、同軸ケーブルよりも容量の大きな光ファイバーを用いて、2010年までに全家庭を光ファイバーでつなごうと計画しているが、そのためには30兆円もの膨大な費用がかかる。このような情報通信技術の違いにより日本はアメリカに比べて情報化社会への立ち遅れが目立っている。
21世紀を支える科学技術には、その先見性と柔軟性が必須である。STX-21プロジェクトが目指す「超鉄鋼」の研究開発から21世紀を支える先見性と柔軟性を兼ね備えた材料開発の先導的指導原理が創生されることを期待している。
 金属材料技術研究所は、2000年の幕開け早々の1月12、13の両日にわたって第4回の超鉄鋼ワ-クショップをつくば国際会議場で開催しました。
金属材料技術研究所は、2000年の幕開け早々の1月12、13の両日にわたって第4回の超鉄鋼ワ-クショップをつくば国際会議場で開催しました。
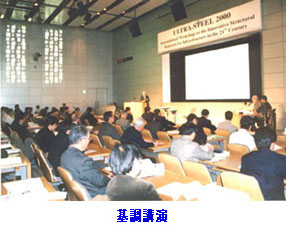 国際ワ-クショップ
国際ワ-クショップ
基調講演: 超鉄鋼研究を推進中の中国、韓国、日本のプロジェクト構想と現在までの成果が、責任者のWeng氏(中国、中国金属学会)、Lee氏(韓国、浦項総合製鉄)、佐藤(金材技研)から報告された。背景、目標、推進方法などに共通点が多いこと、一方で、中国、韓国のプロジェクトは段階的な実用化を重視し、工業化プロセスの開発を早期から視野に入れていることなど各国の特徴が理解された。
国際1: 超々臨界圧発電プラント用フェライト系耐熱鋼開発の現状に関しての講演と討論を行った。Mayer氏(独、GEC ALSTOM)が、ヨーロッパにおける高強度耐熱鋼開発プロジェクトの概要、Bhadeshia教授(英、Cambridge大)がニューラルネットワークを用いた耐熱鋼設計、福井氏(日立)が650℃級タービンロータ用鋼、阿部(金材技研)が650℃級ボイラ用鋼の研究開発状況を紹介した。ヨーロッパと日本の目標が同じこと、長時間クリープデータの取得を重視していることなど共通点が多いことが確認された。
国際2: 溶接構造物と接合技術の現状と将来と題して、Dolby所長(英、TWI)、三木教授(東工大)、志賀(金材技研)による講演と討論が行われた。低合金細粒型の高張力鋼を構造物に使用する場合、溶接性に最大の関心をはらうべきことをDolby氏が述べ、三木教授も橋梁の疲労を例に溶接継手特性を重視すべきことを指摘した。志賀(金材技研)がこれに応えて、金材技研における低合金超細粒鋼の開発は新溶接技術と新溶接材料の開発と併行して進めていることを強調し、これらの成果を示して紹介した。
国際3: 機械構造用と耐熱機器用のマルテンサイト鋼の革新に焦点を合わせて討論された。Krauss教授(米、Colorad School of Mine)が機械構造用鋼,Bhadeshia教授が耐熱鋼について基調講演を行い,各々今後は粒界炭化物の制御、第2相粒子のサイズ分布や粒界性格に注目すべきことを述べた。これに対し大村と津崎(金材技研)が粒界炭化物に着目したナノスケ-ル組織・力学解析と制御法、中島助教授(九大)が高温変形における粒界性格分布の変化に関する研究を紹介し、課題とその研究状況が噛み合う討論となった。
国際4: 海浜構造物の耐食性研究の今後の方向を探る討論を行った。村田氏(新日鐵)が基調講演で、長寿命化や信頼性向上技術は持続可能な社会の構築を図るキ-技術であることを強調した。Phull氏(米、Laque Center for Corrosion) が長期間の環境モニタリングを伴う暴露試験の重要性を指摘し、小玉(金材技研)が超鉄鋼研究の耐食鋼研究における環境モニタリングつき暴露試験の研究を紹介して、耐候性鋼研究の焦点を浮かび上がらせた。
国内ワ-クショップ (高橋 稔彦)
国内1: 80キロ鋼討論会: 21世紀に向けた鋼構造物の展望と課題の主題のもとに、駒田氏(海洋架橋調査会)、岡本氏(日本サハリンパイプライン調査企画)、中島助教授(京大)の話題提供を受けて討論が行われ、高強度鋼メリットを生かした次世代鋼構造物の実現のためには、材料-施工に加えて設計を含めた連携の必要性が認識された。
国内2: 耐食鋼討論会: 超耐食をめざした表面改質技術と題した討論会を行った。柴田教授(阪大)、原助教授(東北大)、藤本講師(阪大)は不動体皮膜の改質・創製、篠原助教授(東大)は酸化物半導体膜の利用、黒田(金材技研)と原田氏(ト-カロ)は溶射技術に関して最新の成果を紹介した。耐食性向上を目指した表面改質の多くの考え方、新しいアプローチの現状と今後の方向を探る非常に良い討論会となった。
国内3: 150キロ鋼討論会: 遅れ破壊特性の評価法を主題にして開かれた。最初に金材技研提案の評価法の考え方と開発状況を津崎と高木が紹介し、その後同じく評価法の確立を目指す山崎氏(新日鐵)、西村助教授(大阪府大)、松山氏(東洋電機製造)および高強度鋼のユ-ザ-の立場から中野氏(トヨタ)、関氏(NTT東日本)がコメントを行った。使用可否判定可能な評価法の確立をユ-ザ-側が求めていることが明確になる等実り多い討論会となった。
国内4: 耐熱鋼討論会: 超々臨界圧発電プラントの実現にむけて、長期間使用中の材料損傷を考慮するとどのような材料特性が重視されるべきか、に焦点を合わせた討論会が開かれた。増山氏(三菱重工)、福田氏(バブコック日立)、野中氏(IHI)、齋藤氏(発電技検)の話題提供と討論の中で、材料研究者はクリープ重視、機械研究者は疲労重視と考え方がわかれ、今後研究会を設置してさらに議論を進めることが要望された。
評価ステーション第3ユニット紹介
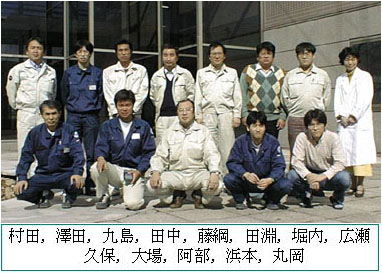 評価ステーション第3ユニットは、職員8名、構造材料特別研究員2名、外来研究員1名、アルバイト2名で構成されています。研究内容は、フロンティア構造材料研究の耐熱鋼テーマ、それに加えて世界的に有名なクリープデータシートの作成に取り組んでいます。両テーマとも全室員と材料試験事務所(目黒)が相互に連携し合って研究を進めています。 評価ステーション第3ユニットは、職員8名、構造材料特別研究員2名、外来研究員1名、アルバイト2名で構成されています。研究内容は、フロンティア構造材料研究の耐熱鋼テーマ、それに加えて世界的に有名なクリープデータシートの作成に取り組んでいます。両テーマとも全室員と材料試験事務所(目黒)が相互に連携し合って研究を進めています。阿部冨士雄(職員、ユニットリーダー)は、耐熱鋼TFリーダーも兼ねており、毎日の激務と格闘しながらも室員を指導し、時々目黒にも足をのばしています。 田中秀雄(職員)および村田正治(職員)は、オーステナイト系耐熱鋼の研究および金属組織写真集の作成に広瀬由美子(アルバイト)の援護を得ながら取り組み、社会的に注目されるH-Ⅱロケット事故調査にも参加しています。 久保清(職員)は、フェライト鋼溶接継手のクリープ特性評価について研究するかたわら、浜本顕一(アルバイト)の協力を得ながら材料強度棟クリープ試験室の総元締としても活躍しています。 大場敏夫(職員)は、応力リラクセーション試験の数少ないスペシャリストで、所内のレクリエーションで活躍するとともに管理部や企画室との円滑な連携にも日夜貢献しています。 九島秀昭(職員)は、フェライト鋼の長時間使用に伴う材質劣化機構の解明および長時間クリープ強度の加速評価に取り組み、毎回のように鉄鋼協会で発表する頑張屋です。 田淵正明(職員)は、まじめな性格で、フェライト鋼溶接継手の高温強度、クリープき裂成長試験評価法の標準化に関するVAMAS国際協同研究等に取り組んでいます。 藤綱宣之(構造材料特別研究員、神戸製鋼所)は、材料の製造から評価までの豊富な知識と経験をフルに発揮して、クリープ強度と耐酸化性の両立に取り組んでいます。 堀内寿晃(構造材料特別研究員、日立製作所)は、とにかく計算が得意で、最近は主としてクリープ強化相の安定性の計算などに取り組んでいます。 丸岡信也(外来研究員、茨城大学M2)は、フェライト鋼中の炭化物の成長過程を詳細に解析し、最近、修士論文としてまとめました。 澤田浩太(職員)は、去年4月に入所したばかりの若手で、フェライト鋼のクリープ強度を転位論に基づいて解析したり、共通電顕のお手伝いなどで忙しい日々を送っています。 (澤田 浩太) |
前号からの主な出来事 |
|
H12. 2. 8 2.16 |
斉藤鉄夫科学技術総括政務次官ご来所 第11回企画調整委員会開催 |
今後の予定 |
|
H12. 4. - 4. - 5. |
第12回企画調整委員会開催 各スパイラル研究作業分科会開催 |
バックナンバー
:
2000/2(30号)
,
2000/1(29号)
1999/12(28号), 1999/11(27号), 1999/10(26号), 1999/9(25号)
1999/8(24号), 1999/7(23号), 1999/6(22号),1999/5(21号),
1999/4(20号),1999/3(19号),1999/2(18号),1999/1(17号),
1998/12(16号),1998/11(15号),1998/10(14号),1998/9(13号),
1998/8(12号),1998/7(11号),1998/6(10号),1998/5(9号),
1998/4(8号),1998/3(7号),1998/2(6号),1998/1(5号),
1997/12(4号),1997/11(3号),1997/10(2号),1997/9(1号)
本ページに関するお問い合わせ先:info@nims.go.jp