
[更新日'99/1/1]

平成11年1月号(通巻第17号)
目 次
研究総務官 齋藤鐵哉
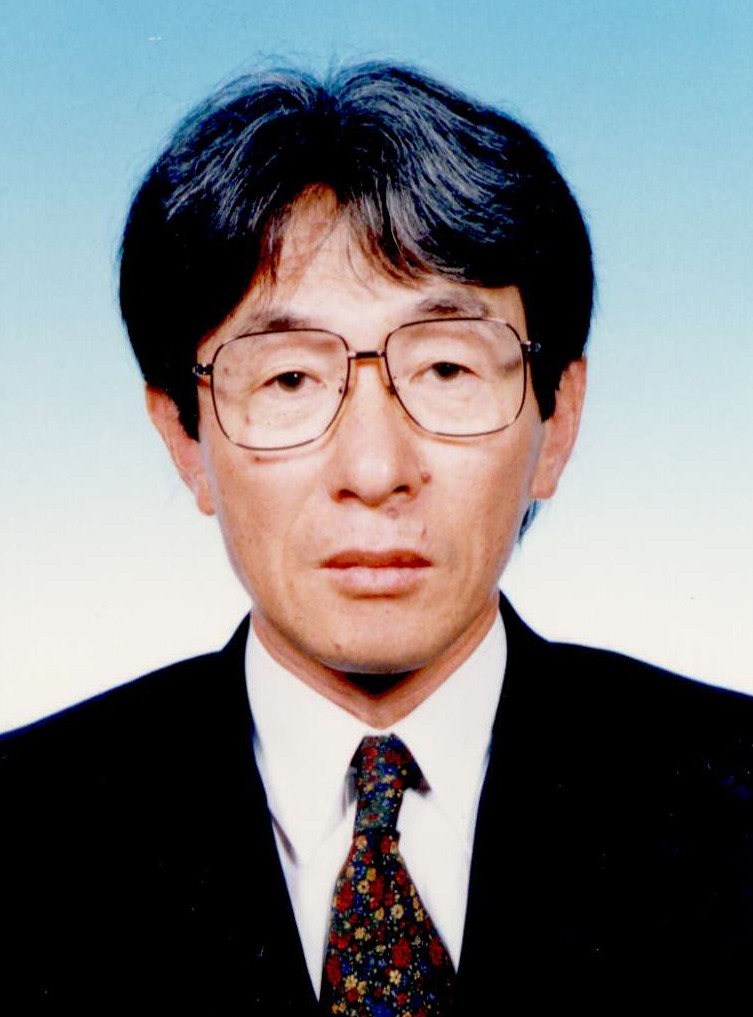 新年明けましておめでとうございます。本年もまた、旧年同様よろしくお願い申しあげます。一昨年の4月、金属材料技術研究所第5次長期計画に基づいて、フロンティア構造材料研究センターが発足し、そこを研究の場として21世紀での使用を目指した構造用鉄鋼材料の研究開発プロジェクトが開始され、早くも2回目の新年を迎えました。
新年明けましておめでとうございます。本年もまた、旧年同様よろしくお願い申しあげます。一昨年の4月、金属材料技術研究所第5次長期計画に基づいて、フロンティア構造材料研究センターが発足し、そこを研究の場として21世紀での使用を目指した構造用鉄鋼材料の研究開発プロジェクトが開始され、早くも2回目の新年を迎えました。
先ずはこの間に企業、大学、学協会ほか、関連の方々からいただきましたご支援、ご鞭撻に対して厚くお礼を申し上げます。おかげ様を持ちまして、国立の研究機関として新しい研究開発体制を模索しつつ立ち上がったこの「新世紀構造材料研究」プロジェクトも、産学官の英知・総力を結集することにより、着実に前進してきました。新しい推進体制であるために具体的に研究が進むにつれて、いろいろと解決しなくてはならない問題も出て来ましたが、産学官の異なるカルチャーの融合により、当初予想していた以上の有意義な効果が現れ、研究成果を発信してきたと実感しております。
さて、わが国では科学技術基本法や科学技術基本計画に基づいて、来るべき新世紀を科学技術創造立国として迎えようとしています。国内の社会インフラの整備更新・維持、グローバルには、省資源・省エネルギー、地球環境の維持・改善等々、科学技術に対する社会的・経済的な要求は、今後さらに大きくなってくることが予想されています。その中で、新世紀構造材料の開発研究の意義は極めて大きいものと思います。世紀末のこの時期、ともすればとらわれそうになる閉塞感を打破する画期的な技術革新は、画期的な新材料の出現がその基礎となるのではないかと考えるからです。
そのためか、経済、資源、環境等に大きな影響をもつ構造用鉄鋼材料を対象としたこの研究プロジェクトは、特にこのところ、外国からも大きな注目を集めています。しかし、国内的には鉄鋼材料研究に携わる人材の大きな減少が云われています。この新世紀構造材料研究プロジェクトが1つの契機となって、鉄鋼材料研究が活性化し、新世紀を担う優秀な若い人材が育ってくれることを期待してやみません。フロンティア構造材料研究センターが、そのような場として機能するとともに、産学官の研究者が集い、研究成果の発信基地として今後さらに発展していけるように、一層努力する所存です。
あらためて、関係の皆様方の変わらぬご支援、ご鞭撻をお願い申し上げます。
2.TOPICS
高強度鋼のギガサイクル疲労特性
−介在物起点内部破壊を克服する−
評価ステーション 阿部孝行、大村孝仁

 研究の背景
研究の背景
近年、輸送機械などの軽量化、高速化に伴いばね鋼等の高強度鋼は、高荷重下で長時間の使用に耐えることが要求されている。しかし、引張強度1200MPaを越える高強度鋼のギガサイクル域(繰り返し数107〜1010回)では、鋼中に含まれる介在物等を起点としてき裂が進展する内部破壊が顕在化するため、疲労強度が低下することが問題となる。
ギガサイクル域での疲労強度の低下
図1に、ばね鋼と工具鋼の107および108サイクルにおける疲労強度と引張強度の関係を示す。これらの鋼は、引張強度σBが1300MPa〜2200MPa級の材料である。図中には引張強度1200MPa以下の機械構造用調質鋼の結果も併せて示す。機械構造用鋼の場合は表面を起点とする破壊形態であり、表面破壊した107サイクル疲労強度σWと引張強度σBの関係はσW
=0.53σBで表される。これに対してばね鋼と工具鋼の結果は、この関係を高強度側に延長した破線上には乗らず、引張強度や硬さから期待されるよりも疲労強度が低くなる。
疲労破壊の起点となった介在物は、ばね鋼ではAl2O3系介在物が観察され、その直径は平均約15μm
であった。工具鋼SKD61鋼では平均15μmのCaO系介在物、SKD11鋼では、平均47μmのCaOまたは平均20μmのCrC系介在物が観察された。
疲労特性における内部破壊のメカニズム
従来の考え方では、内部破壊の起点となる介在物を同じ大きさのき裂とみなし、その寸法を小さくすることが疲労強度を上げる指針とされてきた。これに対し、寸法のみならず介在物の種類、すなわち硬さやヤング率等の力学特性も考慮に加える必要を示唆するのが図2である。この図は、繰り返し応力
σaと初期き裂長さ(介在物直径の半分)aiから計算される疲労き裂進展寿命と破断繰り返し数Nfの関係であり、介在物寸法が寿命に与える影響が取り除かれている。すなわち、疲労特性が介在物寸法のみに支配されるとすると、すべての点は1本の直線上に乗らなければならない。しかし、弾性が支配的な小規模降伏下では、介在物の種類により寿命が異なっている。これより、高強度鋼の高サイクル疲労特性を改善するためには、従来指針である介在物寸法を小さくすることに加え、介在物の種類、すなわち介在物の力学特性も考慮することが重要になることが明らかとなった。
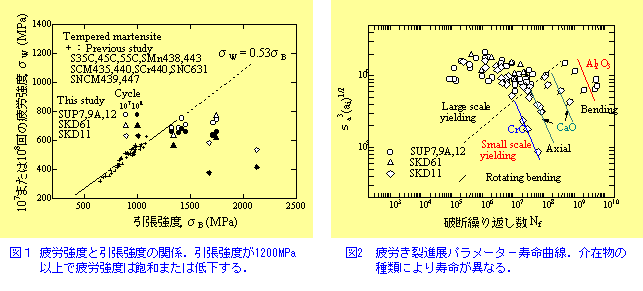
去る12月3日、4日の両日に亘って、つくばの金属材料技術研究所において第3回超鉄鋼ワ−クショップを、「超鉄鋼材料実現への期待と課題」と題して開催しました。
今回のワ−クショップは、21世紀の構造物を構想されている研究者から次世代の構造物の姿と鉄鋼材料にかける期待を直接語っていただき、一方超鉄鋼材料の研究者から、21世紀に実現を目指す鉄鋼材料の姿と具体的な研究の進捗状況を紹介し、議論の中からお互いの今後の課題を明らかにすることを趣旨にしました。超鉄鋼材料研究者からは、「ここは更に加速して伸ばそう、ここはもう一度良く検討してみる必要がありそうだ」、構造物側の研究者からは、「こんな鉄鋼材料ができるのか、構造物の姿を大きく変えられるかも知れない、どんどん注文をつけよう」という声が出てくることを期待しました。
参加者は、鉄鋼材料の製造関係の企業から72名、鉄鋼材料の使用者側の企業から136名、大学・研究機関において鉄鋼材料、施工・加工技術、そして構造物の研究を行っておられる方など132名、金材技研の研究者115名合わせて138機関455名という多数に及びました。中でも、鉄鋼材料を使用する側の企業、大学・研究機関の方に多数参加いただいたことは、主催者として非常にうれしいことでした。
1日目は最初に鉄鋼材料の使用者と製造者の視点に立った基調講演を3名の方からいただきました。
大阪大学の豊田教授は、「21世紀の建築・土木構造物と超鉄鋼材料」と題して、弾性設計という設計概念の紹介も含めて、新しい構造物の姿と鉄鋼材料への要求を講演されました。この中では、構造研究者と材料研究者が交流を密にすることの必要性も力説されました。住友金属の大谷技監は、「21世紀の環境問題と超鉄鋼材料」と題して、21世紀は環境とエネルギ−がキ−ワ−ドであり、この問題の解決に貢献することが鉄鋼技術の最大の課題であることを強調され、この観点で見た鉄鋼材料の到達点と今後の課題を講演されました。最後に、金材技研の福沢総合研究官が「超鉄鋼材料創製の現在」と題して、超鉄鋼研究の中の主として材料創製技術の研究の概況を紹介しました。
午後はポスタ−発表が行われました。プロジェクトがスタ−トして1年半を経過した結果として、金材技研からは初公開のデ−タを含む最新の54件の研究成果が公開され、外部からはこれに呼応するように同じ分野の研究成果が26件も公開されたため、発表者と一般参加者との間だけでなく、発表者同士の議論も展開され会場は白熱した雰囲気に包まれました。その後、80キロ鋼、150キロ鋼、耐熱鋼、耐食鋼の4分野に分かれての技術討論会が開かれました。いくつかの討論会では、金材技研の研究者と外部の研究者が共同で企画し、使用者側と製造者側の第1線で活躍されている方に話題提供と問題提起をあらかじめお願いしたこともあり、非常に突っ込んだ使用者側と製造
者側の議論が戦わされました。金材技研の研究者は現場の迫力に圧倒される思いもしました。もっと時間が欲しかったというのが参加者に共通した感想でした。最後に技術討論会の内容の紹介を含んでの総合討論会が開かれ、超鉄鋼材料の研究成果あるいは研究の進め方に対して様々な見方、期待、意見が図らずも現れるという討論会になりました。
翌日は朝から4分野に分かれて各分野の最先端の研究成果が産学官から発表されました。
4つの分野の各々において、研究開発の到達点と今後の課題が議論され、認識の共通化が図られたようです。2日間に亘って、熱心な討論を続けた結果、一種のファミリ−的な雰囲気が生まれてきたようにも感じられました。
午後は見学会が開催され、80キロ鋼では25トン圧延・鍛造シミュレ−タ−と超狭開先溶接装置、150キロ鋼ではマルチ回転曲げ疲労試験機と超音波疲労試験機、耐熱鋼では定応力クリ−プ試験機、耐食鋼では環境モニタリング機能付き屋外暴露試験場が紹介されました。
今回のワ−クショップで強く印象付けられたことは、21世紀の構造物、材料のコンセプトとして「ハイブリッド化」という方向が示されたことでした。これは構造物の各要素あるいは1枚の鋼板が全ての機能を満足していることを求めない、必要な部位に必要な機能が備わっていれば良いというものでした。例えば、ある鉄鋼材料に強度も靱性も疲労も耐食性もその全てが備わっていることを求めない、そんなことを要求すれば70点の材料しかできない。これからはある機能において150点、200点で他の機能は50点でも良い、これを適材適所で使いこなす、そうしなければ構造物のブレ−クスル−は図れないという考え方でした。従って、金材技研にはまず150点、200点の機能を実現するシ−ズの創出を望みたい、そのシ−ズが使いものになるシ−ズか、そして現実に工業的に実現できるシ−ズかを一緒に見極めようという、うれしくも厳しい声をいただきました。
私たちは、150点、200点のシ−ズの創出に注力することに止まらず、シ−ズの有効性、実現性を自ら見分け、研究加速・減速の判断を的確に行ってプロジェクトを推進していかなければならないという思いを強くしました。
今回のワ−クショップは、金材技研の研究者にとって非常に刺激的な有意義なものでした。材料は使われてはじめて意味を持つ、従って使用者側と普段に交流することが重要であることを改めて実感しました。アンケ−トなどによって頂戴しましたご意見を参考に、ワ−クショップをさらに魅力あるものにするように努力してまいりたいと思っております。
そして、金材技研が鉄鋼材料の使用者と製造者の、また産学官の研究者の交流の場になるように努力してまいりたいと思っております。
最後になりましたが、基調講演会、技術討論会、課題別討論会そしてポスタ−の場でご発表いただきました皆様はもとより、遠路ご参加いただきました皆様に衷心よりお礼申し上げますと共に、超鉄鋼研究の推進に一層のご指導とご鞭撻をいただきますようにお願いして、ワ−クショップ開催記といたします。(高橋 稔彦)

受
賞 報 告
高橋 稔彦(評価ステーション 総合研究官)は、「高強度鉄鋼材料の金属組織と機械的性質に関する研究」により、平成10年12月8日、日本熱処理技術協会から協会賞・林賞を戴きました。
前号からの主な出来事 |
|
H10.12. 3 10.12. 4 10.12.16 |
第3回超鉄鋼ワークショップ開催(公開)
第3回建設材料連絡会開催 |
今後の予定 |
|
H11.1. - 11.2. - |
第5回企画調整小委員会
第7回企画調整委員会 |
バックナンバー:1998/12(16号),11(15号),10(14号),9(13号),8(12号),7(11号),
1998/6(10号),5(9号),4(8号),3(7号),2(6号),1(5号),
1997/12(4号),11(3号),10(2号),9(1号)
本ページに関するお問い合わせ先:info@nims.go.jp