
[
更新日 '97/11/7]
平成9年11月1日発行(通巻第3号)
目 次

これまで一般の人に「構造体化ステーション」と言うと、少しけげんな顔つきをされ、「 Joining and Interface Research Station 」と補足すると少し納得されのが通常で、少し分かりにくい組織名かもしれない。おそらく上層部は「このプロジェクトの目指す鋼材の特徴を十分に把握して、母材特性の利点を壊さない最適な接合・結合法を考案し、また継ぎ手を作るだけに止まらず、構造物としてその健全性までを考慮し、材料設計や接合法にフィードバックすべし。」の考えの基に、言い替えるなら構造物を従来より強く意識すべきとの気持ちから構造体化ステーションと命名されたと解釈している。
「バランスのとれた高張力鋼材はすでに存在する、従って優れた新しい溶接法のみに研究を傾けよ」とする考え方もあるが、これまでの溶接法開発の経緯からすると進展が遅く感じられる。それは素材側と溶接側の境界領域に問題があることによると思う。本プロジェクトは強度2倍、寿命2倍を目指した基本コンセプトをもっているが、このような抜本的な飛躍を望むなら素材側と溶接側の協力した大胆な挑戦が無ければ大きなブレイクスルーが生まれないと考える。従って研究テーマ中には達成が不可能と感じられる目標と内容を持つものも含まれている。
金材技研ではこれまで 拡散接合、ブレイジング、レーザー、アーク現象、溶射、等の要素研究に優れた功績をのこしているが、上述の構造体としての取り組みは非常に少ない。一方、民間の材料メーカー等はユーザーの要求する特性値を満たすことに追われて来て、実用上の問題点は理解しているものの、その解決のための要素研究までは十分遂行されてこなかった。
要素研究のテーマは数多くあり、総花的に取り組んでいたら限られたメンバーと期間では研究能率が悪い。対象とする構造物を強く認識し、それらの開発に存在する問題点解決のための要素研究に焦点をあてることが大切である。本プロジェクトの発足を機に、異なる環境で育ってきた産学官の関係者が結集し、材料と接合の連携した開発の重要性を再認識し、さらには設計も含めた各分野の境界領域の問題点解決に進む事を期待する。
大角粒界からなる2ミクロンの微細粒組織の生成
本プロジェクトの目標である一般溶接構造用鋼(400MPa級)をベースに800MPa級の鋼を実現するためには、現在5-10ミクロンが工業的な達成限界であるフェライト粒径を1ミクロン程度までに微細化しなければならないことが理論的に示されている。さらに、ひとつひとつが単結晶である結晶粒が、隣り合う境界で原子の整列方向が大きく変化する(大角粒界という)ようにしなければ、微細化の効果がないことも分かってる。
今回、 Fe-0.17C-0.3Si-1.5Mn(mass%) の組成の鋼において、等軸な形態を有し、平均粒径2ミクロンのフェライト−パーライト微細粒組織を作ることに初めて成功した。その組織写真を図1に示す。個々のフェライト粒の方位を電子線後方散乱回折(EBSD)法により測定し、同一方位を有するフェライト粒を同一の色で表すようにカラーマッピングした結果を図2に示す。同一の色を有するフェライト粒の集団(方位コロニー)はなく、ランダムに近い方位を有することが確かめられた。同時に、粒界の97%が方位差角15゜以上の大角粒界からなることも確認された。今までにも数例2ミクロン程度のフェライトを含む結晶粒組織の研究報告はあるが、大角粒界が確認されたのは初めてである。本鋼の硬さは Hv 203で、引張強度約700MPaに相当する。800MPa達成の可能性を示した結果と考えている。
今回の結果は、オーステナイト低温域において、圧縮加工を加え10 K/sで冷却することにより得られたものである。フェライト粒の微細化には、従来、強制急冷(50 K/s以上)が必須条件と考えられていたが、今回、10 K/s程度の冷却速度でも実現でき、工業化にとって有利な条件を見いだしたと考えている。
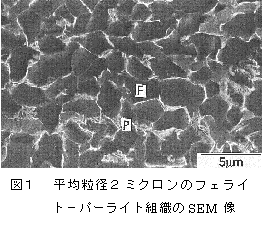
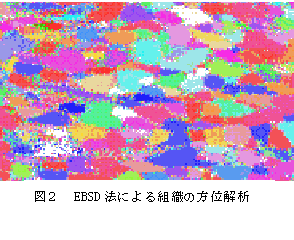
高強度パーライト鋼線の微細組織の原子レベルでの解析
ピアノ線は古くから使われている鉄鋼材料であるが、現在のハイテク時代においても実用金属材料中で最も強い材料である。0.8%程度の炭素を含む共析鋼にパテンティングとよばれる熱処理を施しラメラー状のパーライト組織を得た後に、伸線により強加工を加えていくと著しい加工硬化を示し、現在では3.6 GPaの強度が実験室レベルで実現されている。材料の強度はその微細組織と深く関連があるので、加工や熱処理による材料の強化とそれを阻害する因子を解明するためには、その内部構造を解析することが必要ではある。しかし、3 GPa級を超える強度のスティールコードでは、ラメラ−間隔は6 nm以下になり、強加工したピアノ線の微細構造はナノオーダーになっている。そのうえ、ピアノ線の微細組織形成には炭素の挙動を解明することが必要で、電子顕微鏡法による微細構造・組織解析には著しい限界がある。そこで我々は、最新の3次元アトムプロ−ブや高分解能電子顕微鏡を駆使して、高強度パーライト鋼線の原子レベルでの微細構造解析をフロンティア構造材料センターと共同で進めている。
強加工されたピアノ線において、真歪みが増大すると、一部のセメンタイトが分解し、炭素がフェライト中へ再固溶すると言われているが炭素の固溶状態に関しては不明な点が多い。たとえば炭素は転位に固着され、加工とともに転位密度が増加し、そのために見かけのフェライト中の炭素濃度が増加すると考えられてもいるが、強加工後のラメラー組織中のフェライト中の転位密度は実は考えられているほど高くはない。暗視野像で同一の組織を観察すると、セメンタイトは高度の塑性変形によりナノオーダーに分断され、ナノ結晶状態になっていることも確認された。さらに表皮部分の加工度の高いと考えられる部分では、セメンタイトは一部非晶質化していることも確認された。図1左は真歪み4.2の0.2 mmのスティールコードの電界イオン顕微鏡像である。このように20 nm程度の間隔のラメラー組織も明瞭に観察することができる。このような原子像を得て、そこから元素の分布に関する情報を得ることができるのが3次元アトムプローブである。図1 右には3次元アトムプローブによる炭素原子の分布状態をしめした元素マップがしめされている。炭素原子の密度が著しく高くなっている部分がセメンタイトであるが、フェライト中にも多くの炭素が固溶している様子が観察される。このようにこれまで良く理解されていなかった古くて新しいハイテク高強度材料の微細組織が現在原子レベルで解明されつつある。今後これらの解析結果から得られる知見により、さらに鋼線の高強度化への指針を与えることが出来るのではないかと期待している。
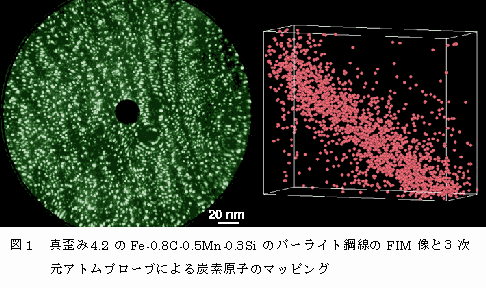

委員会報告
海外出張報告 センター長 佐藤 彰
|
前号からの主な出来事 |
|
|
H9.9.24 10.20 10.27 |
「鉄の微細粒組織を生成」が日本工業新聞等に掲載される 第1回企画調整小委員会開催 第3回企画調整委員会開催 |
|
今後の予定 |
|
|
H 9.11 H10. 1 10. 1 10. 2 |
80キロ,150キロ,耐熱鋼,耐食鋼研究作業分科会開催 第2回企画調整小委員会開催 平成9年度ワークショップ開催 第4回企画調整委員会開催 |
本ページに関するお問い合わせ先:
info@nims.go.jp