
[
更新日 '97/9/8]
平成9年9月1日発行(通巻第1号)
目 次

「科学技術基本法」が1995年11月に制定され、これを受けて、「科学技術基本計画」が1996年8月に閣議決定された。これらを背景として、金属材料技術研究所では「第5次長期計画」が設定され、①「材料科学の基礎的・先導的研究」を一層強力に推進する、②国立研究所がなすべき責務を抽出し、「社会的・経済的ニーズに対して積極的に対応」していく、③「国際的研究開発拠点として、材料研究の中心的地位を確立すべく基盤構築」を図る、が決定された。「新世紀構造材料(超鉄鋼材料)研究」プロジェクトは、社会的・経済的ニーズが高く、既存技術の改善の積み重ねだけでは解決できない、ブレークスルーが必要な材料開発研究課題に対して明確な目標を設定し、産学官の密接な連携を図り、長期的な展望の基で人的結集と資金的集中投入を行い、目標の達成を目指す目標達成型基礎研究と位置付けられている。
超鉄鋼材料の研究・開発の目標は、得られつつある研究シーズを考慮して、「実用強度の2倍化、構造体寿命の2倍化、トータルコストの低減、環境負担度の低減」である。本年4月から、フロンティア構造材料研究センターを発足させ、基礎研究の第1段階として10~20 kg の素塊レベルでの技術基盤を確立することをスタートさせた。素材の組織の作り込みを研究する材料創成ステーション、作り込まれた組織を壊さない接合プロセスを研究する構造体化ステーション、素材及び構造体の諸特性の評価を研究する評価ステーションが設置されている。任期付き任用職員を含めて職員80名、構造材料特別研究員等の外来研究員約20名から構成されている。平成9年度は、研究費9.4億円、研究棟建設費11.9億円が予算措置されている。研究テーマとして、高強度化と長寿命化の研究を選定した。具体的には、合金添加をしない組織制御による溶接が簡単な80キロ級高強度鋼、水素割れを克服する150キロ以上の高強度鋼、超々臨界圧発電プラントを実現する耐熱鋼、海洋性環境での構造物の長寿命化を実現する耐食鋼に関する研究を行う。
構造材料への社会的・経済的ニーズの把握には、外部に開かれた研究推進体制が不可欠であり、「フロンティア研究推進委員会」、「フロンティア企画調整委員会」、「スパイラル研究作業委員会」、「研究会」などに外部委員に参加して戴くことになっている。また、成果報告会としてワークショップ等を年1回は開催したいと考えている。
この「センター便り」は、上記のプロジェクト目標達成のために、センターの活動状況をお知らせするとともに、皆様のご協力とご支援を御願いしたく思って発行します。本「センター便り」に対するご批判、ご希望等を率直に戴ければ幸いです。皆様のご助言を生かして、目標達成に邁進したいと希望しております。
第1回のフロンティア研究推進委員会が6月23日(月)に開催された。本委員会は、「超鉄鋼材料研究」の研究方針、体制、予算、計画などを産業界、学会、官界の学識経験者に長期的な視点から審議していただいて、その意見を研究の組織的かつ効率的な推進に生かすことを目的にしており、外部委員18名と所内委員5名とによって構成されている。
今回は「超鉄鋼材料研究」のスタ-トに当たり、基本的な研究方針として本研究を社会的・経済的ニ-ズに対応する目的達成型基礎研究として5年間かけて行うこと、実行に当たっては材料創製・構造体化・評価の3機能の円環結合を図るスパイラルダイナミズム方式を取ること、外部委員を交えた委員会、各種制度を活用した人事交流によって産学官の英知の結集を図りたいこと、更にスパイラル研究4課題(80キロ級鋼、150キロ超級鋼、フェライト系耐熱鋼、海洋環境用耐食鋼)の概要及び平成9年度の研究計画と平成10年度の計画・概算要求(案)などの説明とその審議が行われた。
以下に要約するように、研究運営から具体的な研究内容にまで亘って貴重な意見を多数いただいた。これを実行面に反映させるよう現在検討を進めている。
(高橋 稔彦)
平成9年7月1日(火)午後、増本健電気磁気材料研究所長を委員長とする事前評価委員会を開催し、本研究の事前評価を行った。これは、「科学技術の振興を図るためには、国費が投入された研究開発活動について厳正な評価を実施し、その結果を適切に活用することにより、より優れた成果をあげていくことが必要」という科学技術基本計画に基づく。「透明性のある開かれた評価」を、5年以上のプロジェクトについては、事前、中間、事後評価を、研究所が主体となって行うべきであると謳った科学技術会議「国の研究開発全般に共通する評価の実施方法の在り方についての大綱的い指針(案)」の提示に呼応して、金材技研が実施を決めたものである。本来ならばプロジェクト開始前に行うべきであるが、時期を逸しないために、開始間もないこの時期に行うこととした。
委員長を初め、阿部光延新日鐵(株)顧問、岸輝雄工業技術院融合研所長、田中重雄三菱重工(株)取締役技術本部長、増子昇千葉工大教授、松田福久(財)発電設備技研足崎試験研究センター所長(五十音順、敬称略)の外部6名の方々に委員をお願いし、ご熱心に審議していただいた。
最終的な評価結果は8月中旬にまとめていただき、「国家的かつ時期的に重要性が高く、国研にふさわしいテーマである」と総合評価を受けた。同時に研究リーダーの指導性、研究資金の合理的配分、優秀な研究者・技術者確保のための流動性と柔軟な組織運営などの重要性、斬新な研究設備開発、知的所有権の重視、産学官連携の一層の推進など細部にわたる貴重なご指導的な助言をいただいた。金材技研およびセンターとしては、助言等を含めた評価を励みとし、所期の成果実現に向けて奮闘する所存である。委員各位に深く感謝する。 (長井 寿)
7月
25日、大阪大学接合科学研究所荒田ホールで、当研究所のプロジェクトを題材にした研究集会が開催された。タイトルは、「新世紀構造材料(超鉄鋼材料)プロジェクトと共同研究について」。当日は、台風が近畿地方へ接近する悪条件にも関わらず、接合科学研究所31名、大学及び民間28名、フロンティア構造材料センター11名、総勢70名の参加があった。1. 新世紀構造材料プロジェクトの概要
2. 超微細組織高強度鋼の開発と取り組み
3. 耐熱鋼・耐食鋼の開発と取り組み
4. 高強度鋼の問題点と組織微細化のためのキーテクノロジー
5. 高強度鋼接合部の問題点と取り組み
6. 大出力レーザによる小入熱深溶込み溶接
7. 高効率狭開先アーク溶接研究における試み
8. in-situひずみ計測
9. 溶接継手の疲労強度
いずれの講演においても、予定時間をはるかに越える活発な討論があり、会場は熱気に満ちた。最後に総合討論に移り、小溝(住金)、山本(ダイヘン)、池内(接合研)の各氏からコメンテーターとして貴重な意見をいただいた。また、参加者から、本プロジェクト研究の背景、進め方、研究協力体制、研究内容等についてコメントと質疑応答があった。
学術的な議論から、研究体制、研究の進め方に渡る幅広い討論内容に関しては、とてもこの紙面では書ききれないが、当プロジェクト研究が産学官の連携によって初めて成り立つものであり、この体制を強化することなく成功はあり得ないことを改めて痛感させられた。今後は、当研究集会でいただいた貴重な意見をもとに、さらに研究内容の充実と研究協力体制の強化を図る努力をする所存ある。
最後に、当研究集会の機会を与えていただきました井上所長、牛尾教授、松縄教授はじめ接合科学研究所の皆様、並びに当研究集会に参加し貴重な意見をいただきました皆様に心からお礼申し上げます。 (塚本 進)
| 発足から今までの主な出来事 | |
|
H 9. 4. 1 4.11 4.15 5.16 5.21 6. 9 6.23 7. 1 |
フロンティア構造材料研究センター発足 今井敬新日鐵社長ご来所 所内センター発足式 江本寛治川鉄社長ご来所 「非接触AFMによる水滴の観察」が日経産業新聞に掲載 第1回フロンティア企画調整委員会開催 第1回フロンティア研究推進委員会開催 新世紀構造材料研究事前評価委員会開催 |
|
7. 2 7.15 7.25 8. 5 9. 1 |
寺門良二新日鐵副社長ご来所 研究員インターネットで公募 阪大接合研研究集会参加 國岡計夫NKK副社長ご来所 第2回フロンティア企画調整委員会開催 |
| 今後の予定 | |
|
H 9.10 10 H10. 2 |
80キロ,150キロ,耐熱鋼,耐食鋼の各分科会開催 第3回企画調整委員会開催 ワークショップ開催 |
STX-21とは?
超鉄鋼材料の英語訳、Structural Materials for 21st Centuryを略したもの。STにはScience & Technologyの意味も重ねてある。Xは未知のものをいくつも生み出すイメージを表す。
今後、ご愛用をお願いします。
- 金表面の水滴の成長のその場観察に成功 -
金属の大気中における腐食は雨による表面の濡れと温度変化による表面の結露によって起こる。室内はいうまでもなく、屋外でも長い年月で考えると、金属表面の濡れ時間は大部分温度変化による結露によるものが占めているといえる。このように結露による表面の濡れが腐食量を支配するといっても過言でなく、結露の機構を知ることが非常に重要なポイントとなる。結露の機構については水晶マイクロ天秤法(QCM)測定の結果などから湿度が60%を越えると金属表面の吸着水の量が増え、表面が濡れ始めることが報告されている。しかし、理想的な状態を考えると湿度が100%以上で結露が始まると考えられ、理想とのずれは表面の汚れなどで説明されているが、詳しいことはわかっていない。そこで開発した非接触AFMモードを用いて環境セル中で湿度を制御しながら金コートされた水晶振動子の表面をその場観察し、水滴の発生、成長機構を調べた。また同時にQCM測定も行い、AFM測定の結果と照らし合わせ検討した。その結果、表面には新品の水晶振動子でも直径10~30nm程度の水滴が付着しており、その量は大気中に放置したり、乾湿実験を繰り返すと増加することが判明した。また湿度を変化させた時の表面の水分の量はこの微小水滴の付着量に依存し、図に示すように湿度が60%を越えると水滴は成長し、湿度を60%より下げると縮小し一定の大きさになる。しかし一旦付着したこの微小水滴は湿度を10%以下にさげても蒸発することなく存在する。このような微小水滴の付着を防ぐことが可能であれば、湿度100%まで結露しない材料ができる。
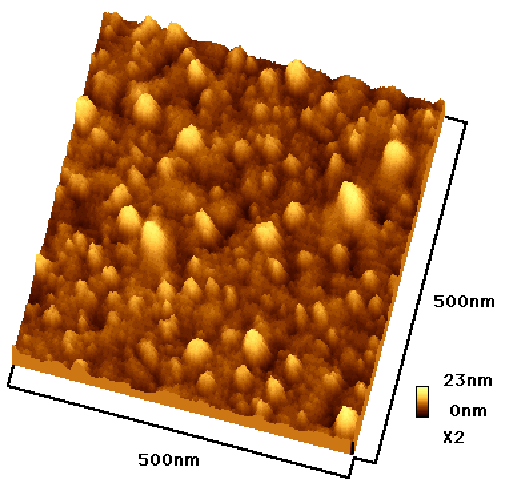
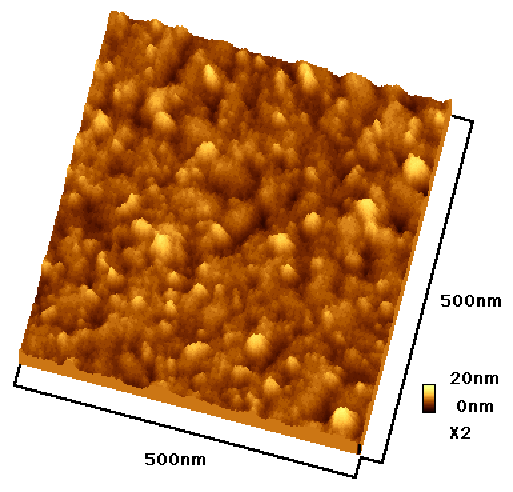
図1 金表面の微小水滴寸法の湿度による変化(左 湿度
70%、右 40%)。本ページに関するお問い合わせ先:
info@nims.go.jp