
[更新日 '98/9/1]

平成10年9月号(通巻第13号)
目 次
京都大学大学院工学研究科 教授 牧 正志
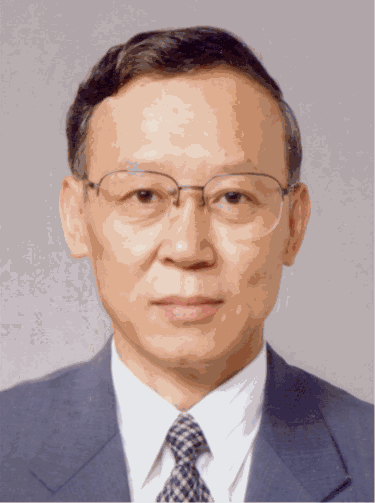
いわゆる新素材が世間で持てはやされるようになってからかなりの時がたつが、鉄綱材料に取って代る構造材料が有るとは考えられない。鉄鋼材料が将来にわたって工業材料の中心的役割を果たさねばならない責務がある限り、より安価なものを供給する努力に加えて、より高性能、高機能を有した鋼を開発し続けて行かねばならない。
ところが、鉄鋼は成熟した材料であるが故に、多くの先達が心血を注いで創り上げた現在の鉄鋼材料の性質をさらに大きく上回る高級な製品を開発するには、従来にも増して研究者の高い能力と努力を必要とする。決して片手間でなし得るものではなく、全力を投入して取り組むべき課題である。
約30年前、鉄鋼材料研究が盛んであった時代には、企業および国研・大学は多くの優れた人材(研究者)を有し、高いポテンシャルを維持しながら互いに競い合い、活気に満ちていたように思う。当時の研究者たちは、鉄鋼材料研究にロマンを感じ大きな誇りを持っていたはずである。しかしその後の社会情勢の変化に対応し、多くの研究者(特に大学関係者)が鉄鋼材料の分野から離れていった。企業においても鉄鋼研究者の数は減少した。わが国の鉄鋼産業が今後も世界をリードしていくためには、次の世代を支える若手研究者の人材確保、育成が急務である。
かかる時期に、金属材料技術研究所で産・官・学の総力を結集した超鉄鋼材料プロジェクトが生まれた意義は誠に大きく、鉄鋼材料研究に携わる一人として大変心強く感じている。鉄鋼材料の研究を活性化させるには、若手研究者が鉄鋼の明るい未来を信じ、夢と限りない情熱を持たせるようにせねばならない。「強度2倍、寿命2倍」という高い数値目標の達成を追い求める研究は当然大切であるが、同時に、素材としての鉄の魅力を再認識させるような夢のある研究もぜひ進めて頂きたいものである。超鉄鋼材料プロジェクトが世の中への鉄の魅力の発信基地となり、鉄鋼材料研究の復権と次世代を支える情熱ある研究者創出の核となることを期待する。
鉄を愛し情熱を持つ有能な人材がいる限り、鉄鋼材料の未来は明るいと確信している。
2.TOPICS 溶接のバーチャルシミュレーション技術の開発
―構造物の種々の継手形状における溶接部形状とHAZ領域の熱履歴予測―
構造体化ステーション 岡田 明
 熱履歴予測の重要性とその手法
熱履歴予測の重要性とその手法
STX-21プロジェクトでは、材料創製、構造体化及び評価の有機的連携を図るスパイラル研究体制をとっているが、その接点の一つに、構造物の溶接部近傍の熱履歴の解明がある。溶接継手の機械的性質の評価に、溶接時の最高到達温度、冷却速度及びある一定温度以上での保持時間などの熱履歴の詳細な把握が不可欠である。
図1(a)は被覆アーク溶接によって平板(I開先)及び二種類のV開先で溶接した時の溶接部形状と熱影響部(HAZ)形状の実験結果を示すが、開先形状によって溶接部形状は大きく異なり、必然的にHAZ形状も異なる。従って、熱履歴を予測するには、開先内での溶接部形状を正確に予測する必要がある。
しかしながら色々な溶接法及び溶接条件で作られ、しかも種々の形状を持つ構造物の継手の溶接部形状を物理的に解析できる数学モデルは得られていない。そこで、この問題の有効な解決のために、未知の部分を既存の溶接実験データの利用によって補完し、データベースと数値解析技術を有機的に組み合わせた仮想溶接実験の手法の開発に取り組んで、溶接施工シミュレーションシステムを試作した。
仮想溶接実験による高精度予測
既存の実験データ(例えば平板上に溶接したときの断面形状のデータ)をデータベースとして、任意の溶接継手形状に任意の溶接条件で溶接したときの溶接結果を計算機実験によって予測するもので、図1(b)は(a)の平板上のデータを基にこの手法で求められた溶接部の形状である。さらに予測された溶融池形状を基にその周囲に形成されるHAZ形状やその領域での熱履歴を熱伝導計算するための熱源モデルが決定される。このモデルは実験データから溶融池内の動的な熱輸送の影響を考慮して、図2に示すように溶接部の各位置で大きく異なる熱サイクル曲線を精度良く予測することが可能となった。
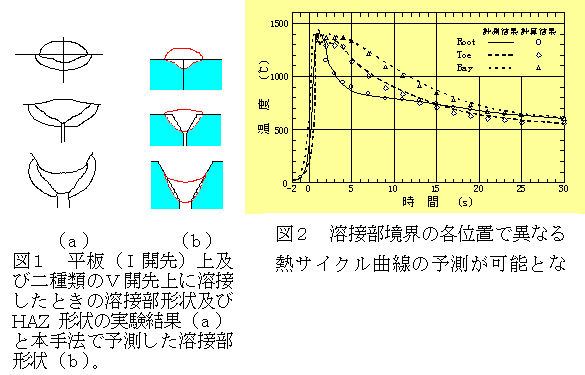
3.TOPICS 超々臨界圧発電プラント用耐熱鋼の構造体化を目指して
―溶接熱影響部クリープ割れの解明に関する基礎的研究
評価ステーション 田淵 正明
 まえがき
まえがき
STX-21
のフェライト系耐熱鋼に求められるブレークスルーの一つに、「素材に創り込まれた画期的な性能を溶接構造体のスケールでいかに発現させるか」ということがある。
そのネックとなるのは、高温で長時間使用中に、母材に隣接する溶接熱影響部に生じるクリープ割れであり、現在、その発生メカニズムの解明を進めている。
熱影響部のクリープ特性
現用の高Crフェライト系耐熱鋼をピーク温度を変えて加熱し、さらに応力除去の熱処理を施した試験片について、クリープ破断時間と硬さを求めた例を図1に示す。αとγの2つの相が混在する温度範囲(AC1~AC3)に加熱すると破断時間は減少し、AC3変態点付近で最も短くなる。硬さについても同じような傾向があるが、最も低くなる温度はAC1変態点付近である。従って、実際の溶接熱影響部でも、この2相域のいずれかでクリープ破壊の生じる危険性が示唆される。現在、この種の熱影響部再現の手法による試験のほかに、実際に作製した溶接継手のクリープ試験やクリープき裂発生・伝播試験データの取得及びミクロ組織の観察を進めており、上述の熱影響部クリープ割れの1次要因あるいは2次要因としての、クリープ速度、破断強さ、き裂発生・伝播特性と組織の意味が明らかになりつつある。
継手組織の最適化
当研究所では独自の技法による継手部のクリープひずみ分布の測定も行っている。結果の一例として、550℃,200MPaで100hクリープした9Cr系耐熱鋼溶接部の歪み分布を図2に示す。溶接部の不均一なクリープ変形が定量的に観察できる。さらに、継手のクリープ挙動の計算機シミュレーション結果についての検討を加えて、2相域にひずみと応力の集中しにくい最適な溶接設計指針の確立を期している。
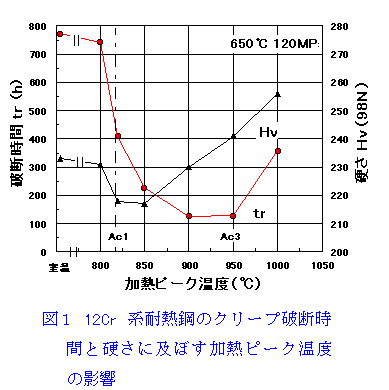
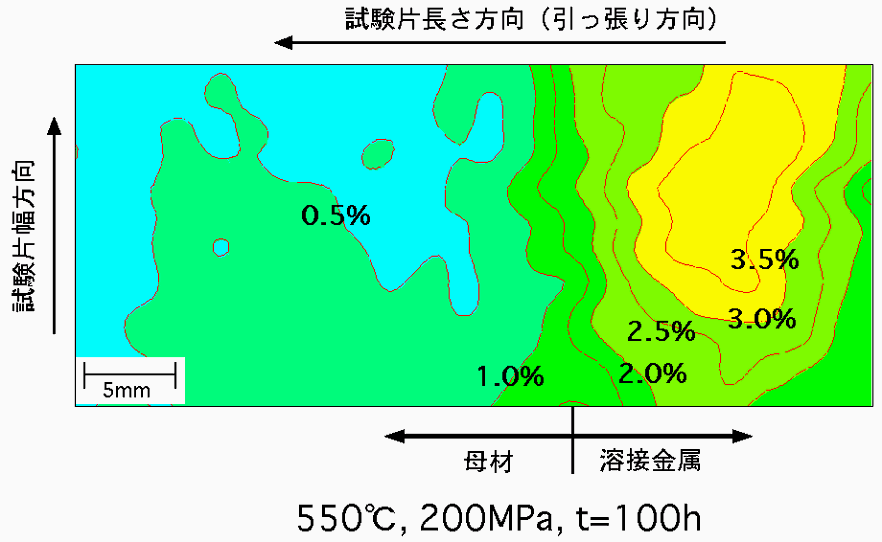
図2 9Cr系耐熱鋼溶接継手におけるクリープひずみ分布の実測例
人物紹介(7)
センター発足後、フロンティア構造材料研究に参画するため産業界及び大学から当研究所に入所された方の感想と抱負を紹介いたします。
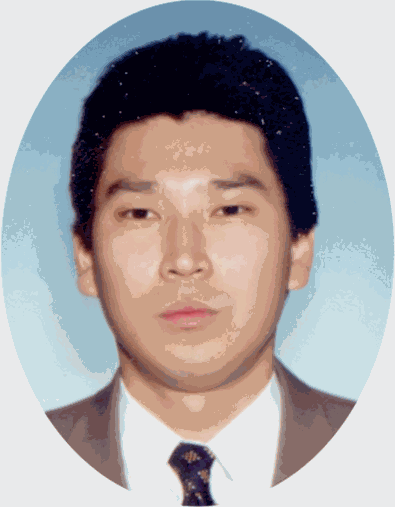 井上 忠信
井上 忠信
研究者にとって、多彩な方々と交流し議論することは、以後の研究を進める上で、極めて重要なファクターと言えます。本研究センターでは、これが苦もなく行える環境が整っており、豊富な研究設備とつくばという環境を加味すれば、研究者にとって理想的な職場だと思います。
こちらに赴任してから半年が過ぎようとしていますが、多くの方々に教示頂き、色々な問題にTryして、私の担当しております高強度鋼の研究で成果が出せるよう努力していく所存であります。宜しくお願いいたします。
(材料創製ステーション 第3ユニット 研究員、京都大学から)
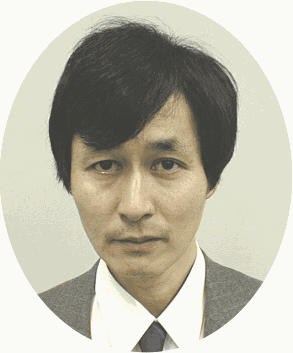 花村 年裕
花村 年裕
金材技研に赴任し約半年がたち、感じることは研究設備が充実していることに加え、研究環境が自由闊達な空気に満ちていることです。特に研究討論では物事の本質に突っ込んでいく小気味よさが感じられます。
私が関わっている組織微細化はこれまでにない研究の切り口を必要とする鉄鋼材料の革新的課題であり、産業界へのインパクトを期待しています。このなかで微細組織の厚板化に繋がるシーズを確立したいと思っています。
(材料創製ステーション 第3ユニット 特別流動研究員、新日本製鐵㈱から)
受 賞 報 告
福澤章(材料創製ステーション 総合研究官)は、「コールドクルーシブル型浮遊溶解法に関する研究」により平成10年5月19日、科学技術庁長官から業績表彰されました。
第3回超鉄鋼ワークショップ「超鉄鋼材料:実現への期待と課題」開催について
日時:平成10年12月3日(木)、4日(金)の2日間
場所:金属材料技術研究所(つくば市千現1-2-1)
概要:ユーザーを含む広い分野の研究者、技術者が集い新世紀の鉄鋼材料の実現へ向けての期待と課題を議論いたします。
3日=基調講演/ポスタープレゼンテーション/技術討論/総合討論/懇談会
4日=課題別討論/見学 参加費:無料。但し懇談会は有料。
なお、詳細につきましては今後のSTX-21ニュース等でお知らせいたします。
前号からの主な出来事 |
|
H10. 8. 1 10. 8. 4 10. 8.12 10. 8.26 |
ワークショップ・ポスタープレゼンターション参加者の公募開始 加工容易な「酸素鋼」創製、日刊工業新聞他に掲載 大阪ガス(株)中西基盤研究所長ご来所 住友金属工業(株)長谷副社長ご来所 |
今後の予定 |
|
H10. 9. 1 10.10. - 10.12. 3 |
第6回企画調整委員会開催 第3回スパイラル研究作業分科会開催 第3回超鉄鋼ワークショップ開催 |
バックナンバー:1998/8(12号), 7(11号),
1998/6(10号), 5(9号),
4(8号), 3(7号),
2(6号), 1(5号),
1997/12(4号), 11(3号), 10(2号), 9(1号)
本ページに関するお問い合わせ先:info@nims.go.jp