
[
更新日 '98/1/6]
平成10年1月1日発行(通巻第5号)
目 次
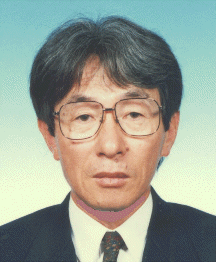
明けましておめでとうございます。本年も旧年同様よろしくお願い申しあげます。
私たちの研究所は、40年の歴史を経て、新たな第1歩を踏み出しました。これと時期を一にして、昨年4月、金属材料技術研究所第5次長期計画に基づいて、フロンティア構造材料研究センターが誕生し、21世紀のための構造用鉄鋼材料の開発に取り組むことになりました。間もなくやって来る新しい世紀における飛躍のために、産学官の英知を結集して、その実現に向かって努力を開始致しました。
私たちが携わっている物質・材料系の科学技術の研究につきましては、10年ほど前の科学技術会議14号答申にもその重要性が謳われておりますように、先端的材料・技術のための基礎的研究に重点が置かれてきたと言えるでしょう。この間、私たちの研究所におきましても、原子・分子あるいは電子の振る舞いに着目したナノあるいはメゾスコピックな観点からの基礎研究が大きく進展して、この領域の研究ポテンシャルを培って参りました。このような原子・分子のレベルでの材料の計測解析あるいは制御技術は、新世紀での使用を意図した構造用鉄鋼材料の開発研究に、力強い手段として適用できるものと期待しております。
しかしながら、新世紀構造材料の開発研究は、産学官の英知を結集することのできる研究体制なくしては、不可能であると考えております。社会的・経済的ニーズへの積極的な対応を目指したこのような研究プロジェクトには、異なった環境で育った研究者や技術者がそれぞれの能力を十二分に発揮し合い、お互いに切磋琢磨し合うことができる開かれた研究環境、まさに、科学技術基本計画が云っております新たな研究開発システムの構築が必要不可欠であると思っております。フロンティア構造材料研究センターが、そのための場として機能し、構造材料研究に関係しておられる研究者の集う研究の場としての役割を担えるように、今後とも最大限の努力を続ける所存でございます。
平成10年の新年を迎えまして、ここに改めて、旧年に変わらぬ関係各位のご支援、ご協力をお願い申し上げます。
高速ガス炎溶射皮膜の残留応力発生メカニズム
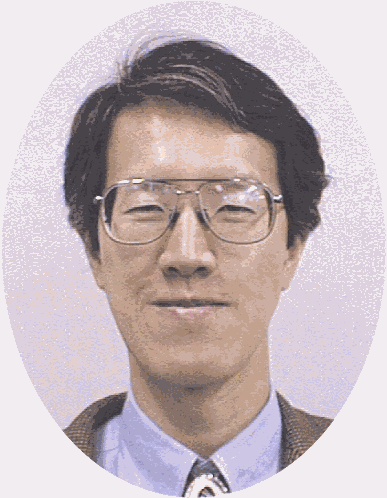
高速ガス炎溶射法とは?
皮膜中の応力のその場測定
当研究所では溶射中に基板の曲率をその場測定することにより、応力発生のメカニズムを明瞭にする計測器を開発し、これまでに主としてプラズマ溶射法に適用してきた。今回、この計測器を灯油を燃料とするHVOF溶射法に適用した結果、溶射中に圧縮応力が導入されていることが初めて明らかになった。図2に、ニッケル基合金のハステロイCをステンレス基板上に溶射した時の基板の曲率と温度変化の測定結果を示す。まずHVOF炎を着火し基板を約400℃にまで予熱後、ハステロイC粉末を約60秒間溶射し、そのまま放冷した。予熱中はほぼ一定に保たれていた基板曲率は、溶射開始と同時に大きく負の値に変化し、その後の膜厚の増加と共に一定の割合で階段状に変化した。階段状に変化するのは、溶射ガンが基板上を周期的に往復して膜を作るために、基板に入射する溶射粒子の数が変動するためである。負の曲率は図中に示すように、基板が溶射方向に対して凸になるような変形に対応しており、皮膜には圧縮応力が発生していることを示す。溶射終了後、基板温度が低下するにつれて、曲率はさらに負の方向に変化したが、これは皮膜と基板の熱膨張係数の違いによる。溶射中の曲率変化の割合から、この実験における溶射粒子の衝突による圧縮応力の値は約400MPaと計算された。
溶射終了後の皮膜中の応力を解析しても、どのような過程でそれが発生したかは分からないが、本法では明快である。今後、皮膜の密着性や耐食性等との関係を検討する予定である。
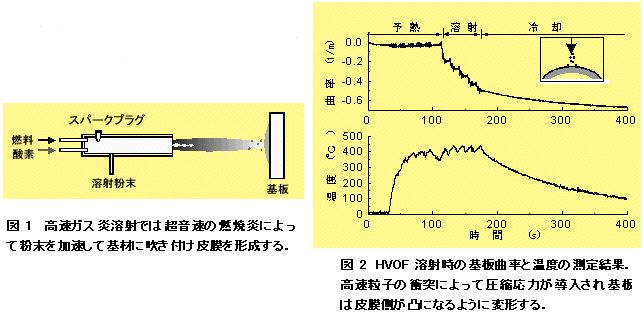
スパイラル研究作業委員会は、4つの課題毎に所外の学識経験者と所内の研究者で構成される委員会で、研究の進捗状況を検討して実行計画をブラッシュアップし、効率的な研究の推進を図ることを目的にしている。
去る11月18日に第1回の委員会が開催された。最初の委員会ということで、午前は4分科会合同会議とし、センタ-長からプロジェクトの背景、狙い、体制、運営などの紹介が行われた後、タスクフォ-スリ-ダ-から4課題の狙いと今までに得られた成果の概要が説明された。午後は課題毎に進捗状況、トピックスの紹介に基づいて討論が行われた。事前の情報がないぶっつけ本番の討議であったが、熱心な討論の中で有益なご意見を多数いただいた。これらの意見を積極的に研究に反映させていく積もりである。ただ、委員会自体の持ち方も暗中模索のところがあり、金材技研からの一方的な研究紹介になったこと、対象分野が広すぎて議論が詰められなかった分科会もあったことなど、反省点も多かった。委員の方々の意見を参考に、委員会の進め方の改善を図っていきたいと考えている。終日に亘って熱心に討論いただいた委員の皆様に衷心より御礼申し上げる次第です。以下に4タスクフォ-スリ-ダ-の感想を簡単にまとめました。
【800MPa鋼】2μmフェライト-パーライト鋼創製、狭隘開先アーク溶接プロセス、溶接継ぎ手疲労の3件の進捗を報告し、継ぎ手特性シミュレーションシステムの開発計画を審議願った。いずれも熱心に議論していただいたが、材料創製分野と溶接分野の異分野同士の議論を今後どう発展させるかについては工夫が必要と思った。
【1500MPa超級鋼】APFIMとナノ硬さ試験の1500MPa超級鋼の高性能化研究への利用の考え方とワイヤ研究への適用例を紹介し、遅れ破壊研究と疲労研究の計画の審議を願った。遅れ破壊、疲労とも核心をついた有益な指摘をいただいた。対象とする分野が広範囲に亘るので、研究会との連携など更に会の運営に工夫をこらす必要がある。
【耐熱鋼】目標が具体的なことに加えて、委員が旧知であることもあって学会以上に白熱した議論が行われた。民間委員からはクリープ破断強度や耐酸化性などの目標値、材料設計指針、材料開発の進め方、評価法、大学委員からはメカニズムに関する議論が多かった。次回は外部委員による話題提供を含めた検討会にしたいと考えている。
【耐食鋼】予想を越える活発な討論が繰り広げられたが、中でも最も関心の高かったのは、“耐食性能の評価および促進試験法の確立”であった。短時間評価法確立の重要性、加速評価の問題点、具体的な研究方案の提案など有益な意見が相次いだ。また、原子レベルの腐食現象の解明をマクロな腐食特性の解明へつなげる一貫した研究の必要を指摘された。
(高橋 稔彦)

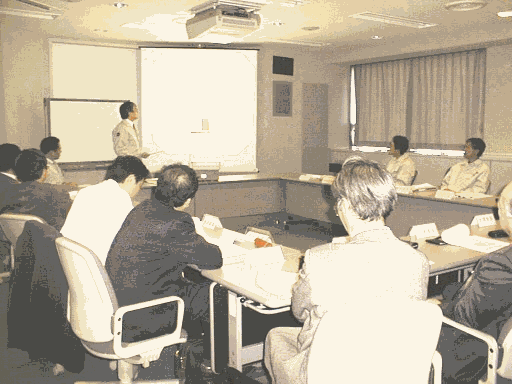
人物紹介(2)
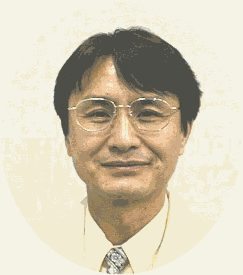
津崎 兼彰
金材技研には様々な専門領域を持つ多くの研究者がおられ、その方々との討論は刺激的です。特に超鉄鋼材料研究プロジェクトを推進する当センターでは、それら専門領域を異にする研究者が連携して研究を行うスパイラル体制が取られており、それぞれの専門知識と技術の融合により革新的成果が生み出されることを期待させます。新しい研究環境に戸惑うこともありますが、高強度鋼創製の挑戦的課題の達成のために知恵を絞り汗をかいてゆく所存です。
(材料創製ステーション 第4ユニットリーダー、京都大学より)
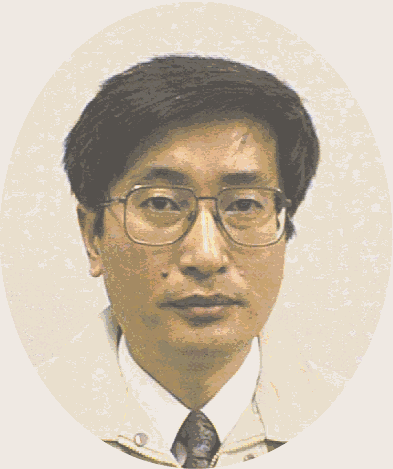
宇野 秀樹
4月に金材技研に赴任後、1年近くが経過し「光陰矢の如し」を実感しています。その間、研究者の方々との機会ある毎の話から、個々人の専門領域に対する自負は単に教科書的な知識ではなく、自ら培った技術をベースにしていることに感心させられました。私のテーマである「耐海水性ステンレス鋼の開発」には金材技研が有するナノ領域への高いポテンシャルを中心に活用させて頂き、効率的なスパイラル研究を行う予定です。
(構造体化ステーション 第6ユニット、構造材料特別研究員、住友金属工業より)

中嶋 宏
金材技研に赴任して半年以上が過ぎ、金材技研における研究設備、研究者の豊富な事を感じています。これまで材料を製造するプロセス、装置の開発に関わってきましたが、STX-21のプロジェクトでの高強度、長寿命鉄鋼材料の開発における上流から評価にいたる広い視野での研究によって、新しいプロセスが生まれてくるものと思っています。
金材技研はこの様な広い視野での研究が、可能な所でありこの機会を利用して自分自身の視野も広げていきたいと考えています。
(材料創製ステーション 第3ユニット、構造材料特別研究員、三菱重工業より)
| 前号からの主な出来事 | |
|
H9.12.11 12. 下旬 |
㈱神戸製鋼所佐藤副社長ご来所 平成10年度予算の大蔵内示に伴い各タスクフォース来年度の詳細研究計画作成作業開始 |
|
今後の予定 |
|
|
H10. 1.__ 1.19 2.__ 3.__ |
第2回企画調整小委員会開催 超鉄鋼ワークショップ '98開催 第4回企画調整委員会開催 春の学会に向けての所内検討会開催 |
本ページに関するお問い合わせ先:
info@nims.go.jp