
[
更新日 '97/12/12]
平成9年12月1日発行(通巻第4号)
目 次

パ−ライトという鋼の組織がある。トランプのカ−ドのような形状のセメンタイトを数10nmから数100nmの間隔で重ね、その間をフェライトで埋めた組織である。鉄鋼材料の最高強度を実現する組織で、冷間加工によって5000MPaを越える強度を得ることも可能である。最高と名が付くと研究者の知的好奇心をくすぐるようで、高い強度が発現する機構の研究が盛んに行われている。代表的なものは誰もが考えつくように、転位が移動できる距離がセメンタイトに制約されて極めて短いためという説である。金材技研ではナノインデンテ−ションの研究がこの数ヶ月の間に著しく進展し、数10nmから数100nmの領域の力学特性を定量的に求めることができるようになった。恐ろしい武器で、パ−ライトの中のフェライトの硬さだけを測定することができる。その結果、フェライトは塑性変形するが、セメンタイトは弾性変形に止まっているような歪のところでは、フェライトの塑性変形は、あたかもセメンタイトが全く存在していないかのように進行することが分かってきた。パ−ライトの強化機構の本質に迫るわくわくするような結果である。
前置きに力が入り過ぎたようである。
さて、実験科学は延長線上を進むものではなく、画期的な実験機器が開発された時に飛躍するとは良く言われることである。見えなかったものが見えるようになり、測れなかったものが測れるようになる、それによって研究が大きく飛躍する、私の限られた経験でもその通りだと思う。問題は革新的な武器をいかに「説明の研究」に止めることなく、「創造の研究」に使うか、その知恵を出すことである。材料屋と解析屋が組むことの強みをフルに発揮したい。
評価ステ−ションは「材料創製ステ−ション」と「構造体化ステ−ション」で創製された技術を「評価」し、その情報を次ぎの創製に反映させるのが任務であるとされている。しかしフロンティアでは、結果の解釈から始まる研究ではなく、仮説の検証から始まる研究を指向したいと考えている。わが評価ステ−ションが、まずあるべき技術像を提示するところから研究が始まるようにしたい。ご支援をお願いする次第である。
耐熱鋼の長時間クリープ強度を短時間で評価

火力発電プラントや化学プラントなどは数十年という長期にわたり使用されるので、高温高圧の過酷な条件で使用される高温構造部材ではクリープなどによる劣化や損傷が生ずる。そのため、それらの部材は一般に10万時間(約11年半)でクリープ破断する強度に基づいて設計される。
高強度耐熱鋼の研究・開発を効率的に推進するためには、長時間のクリープ強度特性を短時間で予測・評価する加速評価法が必要である。従来、長時間クリープ強度の予測には、時間‐温度パラメータ(TTP)を用いたクリープ破断データの統計的解析法が用いられているが、精度良く予測できるのは最長データの3倍程度であり、10万時間クリープ破断強度を精度良く予測するためには、3〜4万時間(3〜5年)の試験データが必要であった。
長時間クリープ強度の予測が困難なのは、強度特性の重要な支配因子である微細金属組織が時間の経過に伴い変化するからであり、クリープ変形は微細組織変化を反映した挙動を示す。本研究では、東北大学丸山教授らが提案した修正θ法を用いてクリープ曲線を定量的に解析し、クリープ変形挙動に基づいた長時間クリープ強度の加速評価手法について検討を行った。
ε=εo+A{1-exp(-αt)}+B{exp(αt)-1} (1)
修正θ法では(1)式に示すように、εo、A、B及びαの4つのパラメータを用いて、クリープひずみ(ε)と時間(t)との関係を表示する。(1)式を用いるとクリープ曲線を精度良く表現できる(図1)だけでなく、クリープ破断寿命の予測を行うこともできる。フェライト系高強度鋼について、クリープ破断寿命を予測した結果を図2に示す。図中の黒塗りのデータポイントが解析に用いた試験データである。解析に用いるデータの温度、応力範囲などを適切に選択することにより、400時間(約半月)以下の短時間クリープ試験で、その100倍に相当する数万時間(数年)までのクリープ破断データを比較的精度良く予測することができた。この結果から、クリープ変形特性の解析による本評価法は、破断データ解析による従来法に比べて、短時間で長時間までの寿命予測が可能であることが確認された。今後は短時間試験法の高度化や微細組織変化の影響解明を図り、加速評価法のさらなる高精度化を試み、効率的な材料開発に反映させていく。
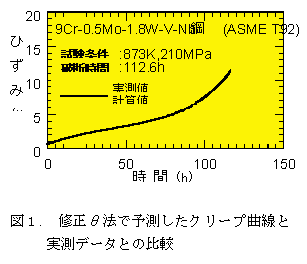
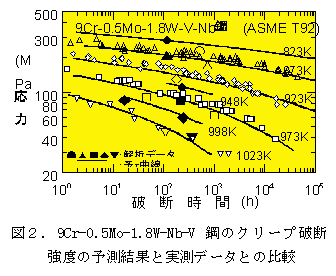
本年4月にスタ−トしました超鉄鋼プロジェクトの狙いと1年目の成果を紹介し、併せて大学、民間の方々からも広く話題を提供していただいて、超鉄鋼材料の実現に向けた萌芽技術について議論を深めることを目的に、標記ワ−クショップを下記の要領で開催いたします。多数の皆様のご来聴をお待ちしております。
開催日時:平成10年1月19日(月) 10:00〜17:00
開催場所:金属材料技術研究所(茨城県つくば市千現1-2-1)
主催:金属材料技術研究所
協賛:(社)日本機械学会、(社)日本金属学会、(社)日本鉄鋼協会、
(社)腐食防食協会、(社)溶接学会
ワ−クショッププログラム
10〜12 超鉄鋼材料プロジェクトの狙いと研究成果の概要紹介
13〜15 ポスタ−セッション(大学・民間20件、金材技研40件)
15〜17 コメンテ−タ−の先生のコメントと総合討論
(コメンテ−タ−は高木節雄、水流徹、松尾孝、松田福久の4先生)
フロンティア構造材料研究センターは今秋の学会において、鉄鋼協会、金属学会を中心に50件を越える発表を行った。この中には、「超鉄鋼材料」のプロジェクトがスタートする前から進めていた研究の成果が含まれているが、それらも超鉄鋼材料研究の目的の達成に寄与する成果である。学会のご配慮で超鉄鋼関連の発表をまとめていただいたこともあり、いずれのセッションでも高い関心を集め、研究内容について活発な質問を会場の中はもとより会場外でも受けた。更に今後の研究の展開に関しても様々な要望と熱い期待が寄せられた。私たちの予想を越える反響の大きさで、あらためてこのプロジェクトへの期待を実感し、責任の大きさを痛感した。4課題ごとの具体的な反響を以下にまとめた。
【800MPa鋼】:この研究の中心課題の一つである超微細フェライト粒組織創製の発表は、特に大きな関心を呼んだようで、創製技術とともにその生成メカニズム解明への期待も高かった。レーザー溶接、アーク溶接の基礎的な問題への関心も高く、今後の具体的な交流計画に発展する意見も寄せられた。継ぎ手疲労への関心も高く、残留応力発生・制御のメカニズム、今後のデータ蓄積への期待が交々述べられた。
【1500MPa超級鋼】:この課題では、ブレークスルーのためのキー技術である先進的な解析技術の研究成果の発表が一つの焦点であったが、AP-FIMなどを用いたワイヤーの原子レベル組織解析の研究、超微小硬さ試験によるナノレベルの力学特性測定研究への関心が高く、具体的な研究交流の要望も寄せられた。疲労強度向上の新シーズの窒素添加ステンレス鋼には、機構の解明を含めた今後の発展が期待された。
【耐熱鋼】:フロンティア研究の最初の成果として新材料設計に関わる結果を4件連報で発表したこともあり、通常の倍を越える聴衆が集まった。耐酸化性向上やクリープ強化に対する材料設計の考え方と、新たな合金元素のクリープ強度への効果、経済性などに活発な質問を戴いた。プロジェクトの今後の展望やフロンティアの組織についても多くの質問を受けた。特に民間企業の研究者の関心が高いようで、改めて期待の大きさを感じた。
【耐食鋼】:3件の国際会議発表を含めて、今回はいずれもフロンティアの今後の発展を支える基礎的な内容の研究成果について発表した。ナノスコピックレベルで腐食反応の素過程を追跡する研究、溶射による高性能表面の創製あるいは超高純度金属溶製など他の機関に類を見ない研究技術を有していることの理解が得られ、独自性の高い耐海浜環境用鋼研究の展開に強い期待を寄せられた。(高橋 稔彦)
人物紹介(1)
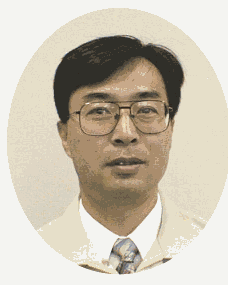
五十嵐 正晃
4月にスタートした超鉄鋼材料プロジェクトの研究も順調に軌道に乗り、師走の慌ただしいこの時期も何時になく充実感を持って迎えることができました。先月開催された第1回耐熱鋼分科会においては、参画戴いている大学・民間企業の委員の方々から、多数の率直、かつ有意義なご意見を賜りました。21世紀を担うオールジャパンの研究プロジェクトに対する熱いご期待と暖かいご支援を改めて実感させられ、決意を新たにした次第です。
(材料創製ステーション 第2ユニットリーダー、任期付任用職員、住友金属工業より)

大橋 鉄也
金材技研は人的資源も物的資源も豊富だと思いますが,それと同時に,研究所を訪問される方々の多彩なのが驚きです。このチャンスに色々な人達の考え方や手法を勉強させてもらいたいと思っています。STX-21のプロジェクトでは溶接継手の信頼性を主なテ−マとしたモデリングとシミュレ−ションが私の研究テ−マですが,材料強度をメゾからマクロのレベルにわたって理解できるようにして行く方針で研究を進めて行く予定です。
(材料創製ステーション 第3ユニット、構造材料特別研究員、日立製作所より)

藤綱 宣之
金材技研に赴任して、半年以上が経過し、この間、先日の研究作業委員会をはじめとする各種会合等を通じ、当初自分が想像していた以上に外部の方々がフロンティアに期待されていると感じています。その期待に添える成果の導出に貢献するとともに、企業では出来ないような金材技研ならではの研究を行えればと考えています。また、金材技研は研究を行う環境としては良い環境にあり、この機会を利用し、自分自身のポテンシャルも上げていこうと思います。
(評価ステーション 第3ユニット、 構造材料特別研究員、神戸製鋼所より)
第1回スパイラル研究作業委員会が、去る11月18日に金属材料技術研究所において開催された。終日に亘って熱心にご議論いただき、貴重なご意見、ご鞭撻を賜った委員各位に心より御礼申し上げます。なお、委員会の詳細は次号で報告する予定です。
| 11月の主な出来事 | |
|
H9.11. 7 11.12 11.13 11.18 11.26 |
Dr Leszek B.Magalas ご来所 日本鋳造工学会会員50名ご来所 高周波熱錬大谷茂久社長ご来所 第1回スパイラル研究作業委員会開催 新日鐵菊間敏夫フェローご来所 |
|
今後の予定 |
|
|
H10. 1.__ 1.19 2.__ |
第2回企画調整小委員会開催 超鉄鋼ワークショップ '98開催 第4回企画調整委員会開催 |
本ページに関するお問い合わせ先:
info@nims.go.jp