
[
更新日 '98/2/10]
平成10年2月号(通巻第6号)
目 次

新世紀構造材料プロジェクトが発足して、早くも10ヶ月が経過し、順調な立ち上がりをされていることは、御同慶の至りであります。一昨年7月、私は鉄鋼協会会長として科学技術庁を訪れ、”新世紀構造材料開発構想”に積極的に賛意を示し、その実現を強く要望しました。
我が国は、技術立国を目指し、科学技術基本法を制定し、基盤技術にさかのぼり、研究開発を推進することを決意したわけですが、これにより、将来に亘って、製造業の国際競争力を維持せねばなりません。本プロジェクトはまさにこの時代の要請に沿った鉄鋼材料の開発であり、近年希にみる大きな課題に挑戦するものです。このようなリスクの高いプロジェクトはやはり国で取り組むべきと思います。そして、実現に向けて産官学が一体となり推進をすることが重要であります。例えば、外部から任期付任用職員や客員研究官を”フロンティア構造材料研究センター”に集め、研究活動を進めるとか、研究成果を研究者個人と国との共同知的財産とするといった新しい制度の導入も意義が認められます。
さて、プロジェクトの目標である2倍の強度、2倍の寿命を有する鉄鋼材料の実用化は、まことに時代のニーズにマッチしたものであります。21世紀に入ると、我が国では戦後高度成長期に建設されたものも含め、道路・橋梁や建築物等、社会インフラの構造体が更新期を迎えます。このような時期に首尾よく、材料開発を成功させ、開発材を投入することにより国民生活の安定を維持するだけでなく、LCA的にも社会に評価される新たなハードを提供可能にしなければなりません。
最後に、これからの大型プロジェクトは外部評価に耐えなくてはなりません。日本鉄鋼協会の学会部門、生産技術部門のいずれも本プロジェクトと密接に関係し、研究会や講演大会等での連携、交流を通じ、より良い成果が得られるよう協力させて戴くつもりです。
原子間力顕微鏡に基づく超微小硬さ試験機の開発
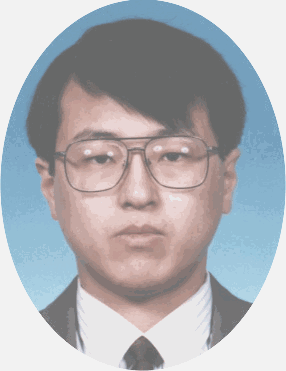
超微小硬さ試験機の意義と原理
本プロジェクトで行われている高強度鋼の開発では、結晶の大きさを1ミクロン程度まで微細化することがキーテクノロジーとなっている(STX-21ニュース第3号)。また、ピアノ線のように、ナノオーダーの微細な間隔を持つ2つの相が強度を高めている例もある(同)。このような高強度化のメカニズムを解明し、材料の設計指針を明確にするためには、材料全体の強度だけでなく、結晶粒や各相単体の力学的性質を知る必要がある。そこで、私達は
硬さの寸法効果とその影響の除去
硬さ測定では押し込み深さが小さくなるにつれて、見かけの硬さが上昇する寸法効果がある。そのため、この寸法効果を除いた硬さの絶対値を求めることが重要である。私達は単結晶を用いて、押し込み力と押し込み深さから硬さを計算する基準曲線の決定法を考案した。図2に、図1の結果を使って得られたニッケル単結晶の硬さと押し込み深さとの関係を示す。理想形状の圧子を仮定するビッカース試験と同様な通常の換算方法では硬さの寸法効果が現れるが、基準曲線による方法では押し込み深さによらず硬さはほぼ一定であり、
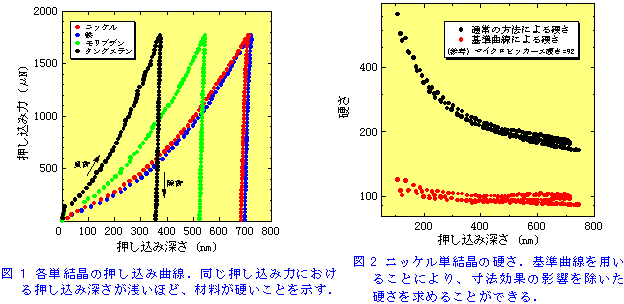
高クロムフェライト鋼のクリープ疲労特性評価
クリープ疲労とは?
高温大気下のデータと極高真空疲労試験機
図1は、フェライト系耐熱鋼として基準的な化学組成であるMod.9Cr-1Mo鋼についてクリープ疲労特性を600℃大気下で評価したものである。 ひずみ波形は、実機の起動停止を模擬したひずみ保持台形波と、基礎となる対称三角波を用いた。台形波には引張側ひずみ保持と圧縮側ひずみ保持の2種類用いた。この鋼の特徴は、圧縮ひずみ保持波の疲労寿命が最も短くなることである。
フェライト系鋼は、クリープ損傷に加え、酸化の影響が非常に大きいと考えられている。そのため、
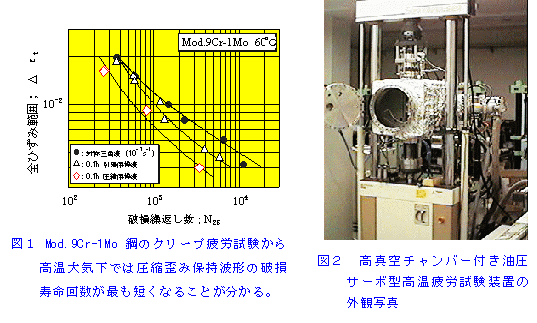
人物紹介(3)

中村 照美
金材技研に赴任して早くも1年が経過しようとしています。金材技研の研究者の皆様のポテンシャルの高さに驚かされ、憧れるのと同時に、このような方々と一緒に仕事ができることをうれしく思います。この機会を生かして自分自身のポテンシャルを最大限に高めたいと思います。
私のテ−マである「超鉄鋼材料の溶接技術の開発」では、材料創製や評価とスパイラル研究を組みながら、実用化をタ−ゲットとしたあたらしい溶接プロセスの開発によりSTX21プロジェクトに貢献できるよう努力する所存です。
(構造体化ステーション 第2ユニット主任研究官、任期付任用職員、石川島播磨重工業(株)より)
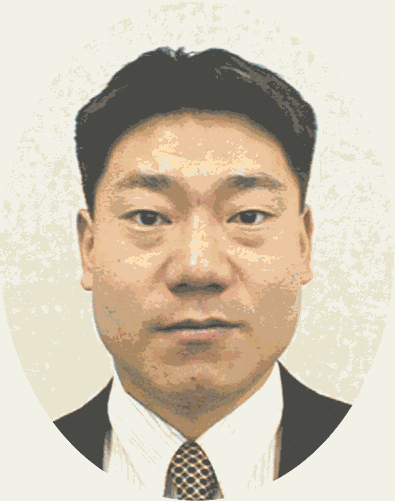
林 透
金材技研で最も強く感じるのは人的にも物的にも研究環境が整っていることです。外部の者でもスムーズに溶け込める雰囲気をも持ち合わせたこのような環境の中で研究できることを非常に幸せに思っております。
私の担当している組織微細化研究も順調なスタートを切り、これからの発展が楽しみな状況になってきました。最高の環境を最大限に生かし、研究を通して自他ともに幸せになれるように努力してゆく所存です。
(材料創製ステーション 第3ユニット、構造材料特別研究員、川崎製鉄(株)から)
昨年開催された新世紀構造材料研究事前評価委員会の評価報告書(案)が去る1月12日科学技術庁において公開されました。この評価報告書(案)は、
インターネット上(http://www.nrim.go.jp:8080/public/japanese/inf/)で公開し、社会一般から幅広い意見を募集しています。なお、評価の対象となった研究プロジェクトの研究目的や内容などについても、インターネットで公開しています(http://www.nrim.go.jp:8080/open/usr/frontier/)。超鉄鋼ワークショップ '98が去る1月19日に金属材料技術研究所において開催されました。産官学の各界から多くの参加を戴き(所外参加者181名)、心より御礼申し上げます。また、ポスターセッションにおいて多くの研究者と密度の高い情報交換が出来たことに深く感謝しております。なお、ワークショップの詳細は次号において報告する予定です。
|
前号からの主な出来事 |
|
|
H10. 1.12 10. 1.14 10. 1.19 10. 1.26 |
事前評価報告書(案)公開 NKK北田基盤技術研究所長ご来所 超鉄鋼ワークショップ '98開催 第2回企画調整小委員会開催 |
|
今後の予定 |
|
|
H10. 2.__ 10. 3.__ 10. 4.__ 10. 4.__ |
第4回企画調整委員会開催 春の学会に向けての所内検討会開催 第5回企画調整委員会開催 第2回スパイラル研究作業委員会開催 |
本ページに関するお問い合わせ先:
info@nims.go.jp