
[更新日'98/12/1]

平成10年12月号(通巻第16号)
目 次
1.21世紀への期待
(財)発電設備技術検査協会、大阪大学名誉教授 松田 福久
 20世紀も残すところニヶ年となった。それぞれの関係分野で、20世紀の反省もふまえ、すでに21世紀に対する多くのビジョンなどが検討されているようである。21世紀には平和、環境、人口、食料、エネルギー、経済、科学技術、教育および国際化問題など20世紀からの連続または新規問題が大きく目白押しに並んでいる。我々の専門分野も上記の問題のいずれかに関係しているので、分野の専門家としても最善の方策を模索していかねばならない。
20世紀も残すところニヶ年となった。それぞれの関係分野で、20世紀の反省もふまえ、すでに21世紀に対する多くのビジョンなどが検討されているようである。21世紀には平和、環境、人口、食料、エネルギー、経済、科学技術、教育および国際化問題など20世紀からの連続または新規問題が大きく目白押しに並んでいる。我々の専門分野も上記の問題のいずれかに関係しているので、分野の専門家としても最善の方策を模索していかねばならない。
我国は20世紀に二つの世界大戦を経験し、その結果破滅的状態となったが、その後驚異的な速度で立ち直り、後半は右肩上がりの経済、技術成長をつづけ、遂に世界に比肩する経済大国、技術大国へと成長した。しかしここへきて経済成長は世界と共に鈍化が起こり、これが21世紀にどのように推移していくものか不透明である。いずれにせよ、今後は大量生産能力の大きい特定国の独り勝ち的な経済構図は通じなくなり、量の増大より質の高度化または現有品の長寿命化ができる国に支点が移ってくることが考えられる。我国の技術大国云々にしても、よく云われるようにサイエンスやテクノロジーのオリジナルは借り物で、国民の有能さと器用さを利用した実用化や大量化技術により世界一流になった感も否定できない。このため21世紀の教育はむしろ今迄のように記憶力と応用力を最優先にするのではなく、創造力を持つ人間を作ることが重要となる。我国からサイエンスのオリジナルが次々に世界に向けて発信されることを期待したい。金材技研では21世紀を目指して新しい超鉄鋼「強度2倍、寿命2倍」の開発が進みつつあるが、これは21世紀に我国が行っていくべき技術のスパイラルアップと世界への技術発信の先駆けになるものと期待される。
溶接技術の分野でも、19世紀後半に発明されたアークは20世紀にアーク溶接として開花し、1世紀後に全盛を誇った。高温の熱源であるため20世紀には溶接の代名詞にまでなった。しかし、20世紀後半に発明された新しいレーザが21世紀にはアークに代わる優れた熱源として溶接界に大きな勢力を伸ばすことが考えられる。アーク溶接で培った技術のスパイラルアップを今後期待したい。さらに、21世紀には次の熱源のオリジナルが我国から発信されることを願いたい。
2.TOPICS
酸化物分散・微細粒組織で800MPa-高延性を同時実現
-超微細複相組織のコンセプトを粉末冶金法で実証-
材料創製ステ-ション 太田口 稔
 組織設計コンセプトとその実証
組織設計コンセプトとその実証
フェライト単相組織鋼の高強度化に当たって、600
MPa以上での一様伸びの低下が懸念されている。そこで本研究では、1)結晶粒1μm以下で強度を2倍化し、かつ2)微細酸化物の均一分散によって、変形による内部ひずみの蓄積を高めて、一様のびを保持するという組織設計コンセプト(超微細複相組織)を立てた。
そして、フェライト粒径1ミクロン以下で30nm以下の酸化物が分散した超微細複相組織を持ち、引張試験が可能な大きさの試料を粉末冶金を利用して作製した(図1)。この試料で、引張強さ850MPaで一様のび7%の良好な強度-延性バランス(図2)が達成できることを確かめ、コンセプトの正しさを実証した。
棒状試料の作製方法
九州大学高木節雄教授(客員研究官)らの薄板シース圧延の方法を参考に、溝ロール加工によって10
mm以上径の棒状試料を得る方法を新たに考案した。具体的な手順は、まず、原料粉(O:0.18、C:0.002、Si:0.02、Mn:0.16mass%、Fe:残)を、所定の硬さまで、機械ミリングする。次に、硬化粉を真空封缶して700度に加熱し、減面率80%以上の溝ロール加工で棒材にする。すると、最終的に350gの粉から、11mm径、650mm長さの棒状試料が得られる。
今後の展望
本成果は、まず溶製鋼での研究にフィードバックするが、全く新しい研究領域の創出につながる可能性も持っている。今後、鉄と酸素の合金、すなわち、酸素鋼とも呼ぶべき新しい鉄材料の分野を開拓できる可能性も示している。さらに機械ミリングの省略が可能になれば、いっそうの進展が期待される。


3.TOPICS
数万時間域における材質劣化機構の解明と加速評価
-クリープ変形解析により、長時間クリープ強度の低下を短時間で予測-
材料創製ステーション
木村 一弘
評価ステーション 九島 秀昭

 材質劣化機構
材質劣化機構
高温高圧の過酷な条件で材料が長期間使用されると、ミクロ組織変化に起因した材質劣化により材料のクリープ強度は徐々に低下する。高強度フェライト系耐熱鋼を開発するためには、優れた強度特性を発現するミクロ組織の高温安定性を高め、数万あるいは十万時間以上の長時間域でもミクロ組織を安定に維持することが必要であるとともに、長時間域で起こりうる材質劣化の機構を解明し、その現象を短時間で予測することが求められる。
改良9Cr-1Mo鋼では約1万時間を超えるとクリープ強度の低下の程度が増大するため、約1万時間以上の長時間クリープ強度は短時間クリープ強度から予測される値よりも著しく小さくなる。その原因は、高応力短時間側では焼戻しマルテンサイト組織の回復が試料全面でほぼ均一に進行するのに対して、低応力長時間側では図1に示すように、旧オーステナイト粒界近傍で局所的なミクロ組織の回復現象が優先的に生じるためであることを見いだした。
加速評価
クリープ強度が急激に低下する低応力域では、図2に示すようにクリープ変形挙動に大きな変化が認められる。すなわち、140MPa以上の高応力域では0.02~0.03のひずみまでクリープ速度が減少した後、加速クリープが開始するが、120MPa以下の低応力域では0.01以下の小さなひずみで加速クリープが開始する。低応力域では、ミクロ組織の回復が試料全面で十分に進行する前に旧オーステナイト粒界近傍で局所的な回復現象が生じ、加速クリープが開始するため、クリープ強度が急激に低下したと推察される。約1万時間以上で生ずる急激な強度低下をクリープ破断データから評価するには、約3万時間までの長時間データを必要とする。しかし、図2の実線部のように、6千時間以下の短時間データからでも120MPaでは小さなひずみで加速クリープが開始することがわかる。したがって、クリープ変形を解析することにより、不均一な回復現象により強度が急激に低下する応力条件(120MPa以下)を把握することが可能である。
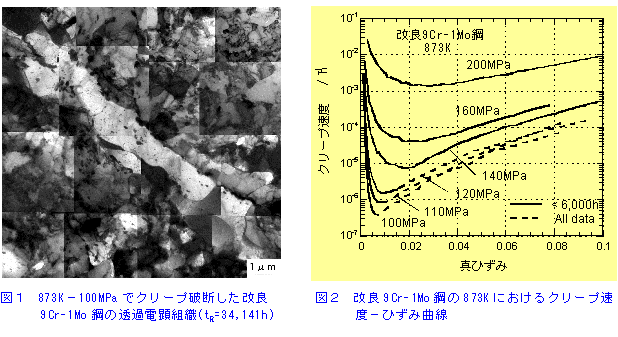
4.センター便り
人物紹介(9) センター発足後、フロンティア構造材料研究に参画するため産業界及び大学から当研究所に入所された方の感想と抱負を紹介いたします。
 大谷
忠幸
大谷
忠幸
金材技研に赴任して約半年が過ぎ、ある程度自分の意志で動くことができる
ようになりました。今後も、金材技研のあらゆる分野の方とお付き合いして、
鋭いディスカッションをお願いし、また実験装置をお借りして、お付き合いの
度を深めていくつもりです。私は、超細粒高張力鋼板の低入熱接合を担当して
います。鋼材開発と同時並行で接合性を論じることに戸惑いながらも、超細粒
高張力鋼板で構造部材を作ることを夢見て、頑張っています。
(構造体化ステーション 第1ユニット 構造材料特別研究員 新日本製鐵㈱から)
 小林
能直
小林
能直
「近代的」「理想郷」「実戦性」。これが初めて金材技研の門をくぐったと
きの私の率直な所感でした。赴任して半年余りが過ぎた今、それに「理念」なるものをつけ加えたいと思います。研究所としての、そして個々の研究に携わる者としての、理想を追求する姿がここにはあり、その一員としての責務を果たすべく日々勉強、努力させてもらえることを大変ありがたく、そして誇りに思っている次第であります。製精錬などをはじめとする「材料の創製」という全ての金属技術の基盤となる分野の、進歩・発展に全力を尽くさせていただく所存ですので、今後ともよろしくお願いいたします。
(材料創製ステーション 第1ユニット 研究員 東京大学から)
 高木
周作
高木
周作
STX21には、日本を代表する多くの材料研究者が関わっておられ、すばらしい
環境の中で研究させていただいています。
その環境の中で、ヒヨッコの研究者
の私は、「どのようにしてこのプロジェクトに貢献できるか」を良く考えて研究
しようと思っています。私は、川崎製鉄では、引張強さ780MPa以下の自動車用
薄鋼板について研究していましたが、STX21では、引張強さ1500MPa超級鋼の研
究をすることになりました。今までと違った世界の中で、自らが何と遭遇するの
か、楽しみです。
(材料創製ステーション 第4ユニット 構造材料特別研究員 川崎製鉄㈱から)
第3回超鉄鋼ワークショップ「超鉄鋼:実現への期待と課題」開催について
前号でお知らせ致しましたとおり、12月3日(木)、4日(金)に標記ワークショップを開催致します。今回は、鉄鋼材料を使う側と作る側の幅広い情報交換の場を提供出来るよう、準備を進めてまいりました。材料の使用者と製造者相互の研究交流の一助となればと願っております。ご来場を心よりお待ち申し上げます。
前号からの主な出来事 |
|
H10.11. 5 10.11.11 10.11.19 |
第5回耐食鋼フォーラム開催(公開) 冨浦新日本製鐵㈱顧問ご来所 竹山科学技術庁長官ご来所 |
今後の予定 |
|
H10.12.
3 10.12. - 10.12. - |
第3回超鉄鋼ワークショップ開催(公開) 第3回スパイラル研究作業分科会開催 建設材料連絡会開催 |
バックナンバー:1998/11(15号),10(14号),9(13号),8(12号),7(11号)
1998/6(10号),5(9号),4(8号),3(7号),2(6号),1(5号),
1997/12(4号),11(3号),10(2号),9(1号)
本ページに関するお問い合わせ先:info@nims.go.jp