
[
更新日 '97/10/6]
平成9年10月1日発行(通巻第2号)
目 次

材料創製ステーションは英語名をMaterials Creation Research Stationといいます。本ステーションに配属が決まり最初の仕事が英語でなんというかということでした。新世紀構造材料というフロンティアを開拓する先達集団にふさわしい言葉として、私の乏しい英語力の中からCreationという単語が浮かび上がったのですが、この語には神の御業、神の作り賜うたものというフィ-リングがあることは薄々感じていました。そこで、所内の何人かのキリスト圏のSTAフェロ-に聞いたのですが、その限りでは問題なかったので、所に進言したところ形式的な修正を加えて上記に決りました。所が聞いた人の中には異議を唱える人もいたそうですが、それにもかかわらず所がCreationを認めたのは、元来日本人は無神論者のためかもしれませんが、神の領域に入る意気込みで研究することを所が認めたことを深く理解する次第です。
新世紀構造材料のスロ-ガン「強度2倍、寿命2倍」に挑戦するには、全く新しい神業といえるような発想の展開と、それを具現化する新技術の開発が必要であるという信念を表す言葉としてCreation以外になかったのではと今思います。特にフロンティア構造材料研究センタ-において新世紀構造材料を生み出す要にある材料創製ステ-ションは、溶解、凝固、各種固相加工、熱処理の各過程を新しい発想で見直し、各プロセスの個々の機能の洗い出しとそこで生じている現象の新解釈、さらには新機能の組み込みを図ることにより、全く新しいプロセスの創造あるいは一見従来プロセスの延長にあっても全く異なった使い方を通して新世紀構造材料の創製を目指しています。
少なくとも名刺を見た外国人から疑問をもたれたり、改名しろというコメントはこれまでのところ頂いていません。ステ-ションのメンバ-には看板負けしないよう今後一層がんばってもらいたいと思うのみです。また、外部からフロンティアを支援して下さる各位には、時には論理性に乏しい発想もあるかもしれませんが、Serendipity の可能性もあると鷹揚に温かく見守っていただきたく思う次第です。
第低変態温度溶接材料を用い溶接継手の疲労強度を約2倍に改善
肉厚の構造用鋼板を溶接すると溶接部に降伏強さ程度の引張残留応力が発生し、溶接継手の疲労強度を著しく低下させるため、母材の強度を上げても全く効果がないのが現状である。そこで、低変態点溶接材料を使うことによって変態膨張による圧縮残留応力を導入し、継手疲労強度を抜本的に改善することに、川崎製鉄(株)の協力を得て成功した。
溶接部では冷却中にマルテンサイト変態が生じやすい。従来の溶接材料では、図1の破線のように変態開始温度(Ms点)が約500℃と高く、変態終了後の冷却に伴い収縮ひずみが生ずる。これが高い引張残留応力を誘起させる原因となる。これに対し、図1の実線のようにMs点を約200℃まで下げ、変態がちょうど室温で終了するようにすると、溶接金属が膨張した状態で溶接が完了し、溶接部に圧縮残留応力を導入できる。
そこで、低変態温度溶接材料(合金組成:10Cr-10Ni-Fe)を用いて、800MPa級高張力鋼の20mm厚(240mm幅、800mm長)の主板に、同じ厚さのアッタチメント(50mm幅、150mm長)の角回(かどまわし)溶接を行った。溶接入熱によってアタッチメント側の温度上昇が大きいと、線膨張差による熱応力が角回溶接部に誘起されるので、それを避けるために、主板のみを110℃に予熱した。さらに、アタッチメントを終端付近で仮付けし、まず直線部を溶接し、角回部を最後に溶接することによって線膨張差による熱応力の発生を避けた。
図2は、室温大気中における従来タイプの600MPa級鋼の継手疲労試験結果(繰り返し応力範囲=最大応力-最小応力と破断までの繰り返し数の関係をプロットしたもの)に対して、最近得られた開発タイプ継手の疲労試験結果を比較して示してある。これから、2000万回繰り返し疲労強度(ここでは応力範囲で考える)は従来溶接継手では65MPaであるのに対し、開発溶接継手では130MPaと見積もられ、約2倍に改善できることを示している。
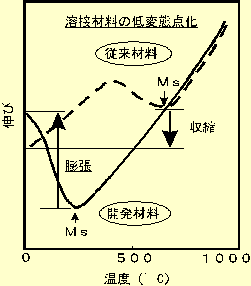
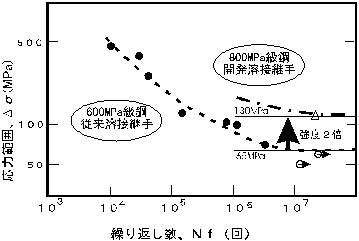
図1 温度低下に伴う溶接材料の伸び変化. 図2 継手疲労強度線図.
耐熱鋼の新しい強化元素を探索
フェライト系耐熱鋼はマルテンサイト母相と炭窒化物等の微細析出物で構成される焼き戻しマルテンサイト組織として使用される。この組織はクリープ変形に伴い、析出物が凝集・粗大化すると共に、マルテンサイト母相では回復・軟化が進行してクリープ抵抗が低下する。このようなミクロ組織変化を出来るだけ長時間抑制してやればクリープ強度の維持が可能となるため、合金元素の調整による析出物の種類や形態・量を制御する試みが広く進められている。
本研究では従来にない新しい試みとしてマルテンサイト母相自体を強化する方法についても探索している。高温におけるマルテンサイト相の強化方法としては、Mo,W等のフェライト生成元素で熱力学的に安定化(⊿Gγ-α’ =0となるTo温度が高くなる)する方法や、逆に Ni,Mn等のオーステナイト生成元素でMs点(マルテンサイト変態開始温度)を低下させ、変態歪み強化する方法が考えられる。
フェライト系耐熱鋼では高温におけるクリープ強度に加えて耐水蒸気酸化性が同時に要求されるため、現用の9%Cr鋼以上の高Cr含有が必須である。さらに靭性を確保する観点からはδ-フェライト相の生成を抑制する必要があり、フェライト生成元素を多量に添加するためには、同時にオーステナイト生成元素を添加しなければならない。そこで本研究ではオーステナイト生成元素の中でも、融点が高い、重い(拡散速度が遅い)、原子サイズがFe等に比べて大きい(格子歪みによる固溶強化能が大きい)、元素としてCoと同族元素であるIr(原子量;192.22、融点;2683 K、原子サイズ;2.71Å(およそFeの1.1倍))について検討した結果、マルテンサイト相が著しく強化されることが明らかとなった。写真(図1)はIr添加鋼(2%Ir)の焼き入れ状態での光学顕微鏡組織であるが、微細なラスマルテンサイト単相組織が得られている。この鋼の高温における軟化抵抗(高温で焼き戻しされた時の硬さの低下度合い)は従来鋼を著しく上回っており(図2)、650℃級フェライト系耐熱鋼の開発に向けてクリープ強度向上の可能性が得られた。
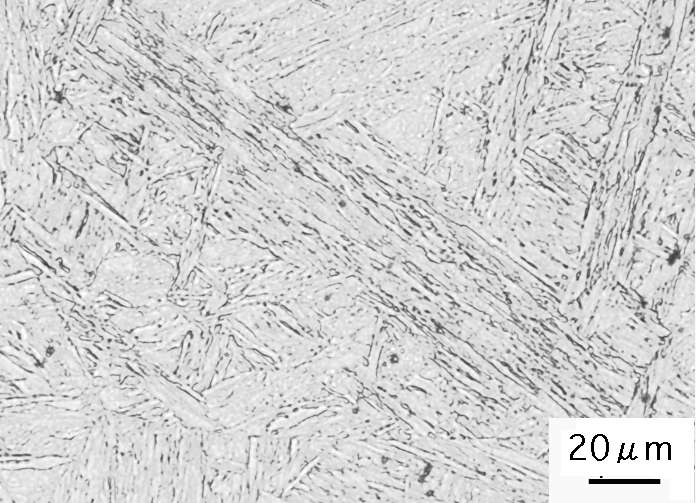
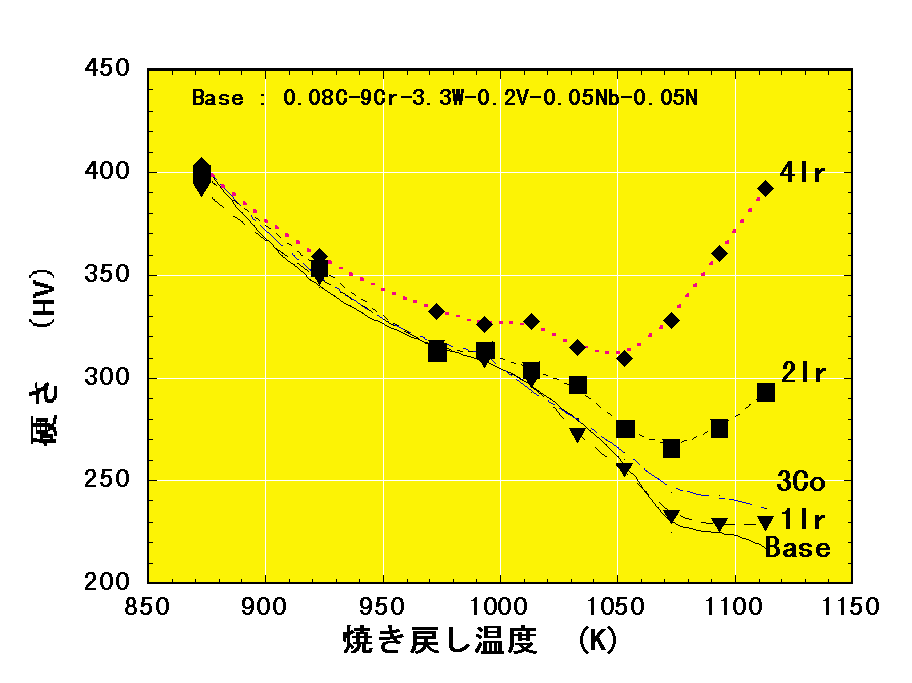
図1 2%Ir添加鋼の 焼き入れ組織 図2 Ir添加鋼の焼き戻し軟化抵抗

秋の学会に向けて発表の準備整う
秋の学会に、フロンティアから日本鉄鋼協会に29件、日本金属学会に10件、溶接学会に7件、腐食防食協会に4件、 その他2件の計52件を発表する。このため、発表の確認と研究者相互の理解を兼ね9月22日に予行演習を行った。各発表に対し、職員による活発な議論が展開され、研究成果に対する真剣さがうかがえた。発表者たちは、その後実験データー等を携え学会開催地に出発する準備を始めた・

人事: 評価ステーション総合研究官に高橋稔彦氏を採用
このたび、フロンティア構造材料研究センター評価ステーション総合研究官に9月1日付けで新日本製鐵株式会社技術開発本部嘱託の高橋稔彦氏が採用された。
同人の採用は、6月4日に施行された「任期付き研究員法」に基づく招聘型採用で、国立研究機関としては初めての任用となった。
(略歴)昭和41年に京都大学工学研究科修士課程を修了し、八幡製鐵(株)(現新日本製鐵(株))に入社、技術研究所主幹研究員、鉄鋼材料研究所条鋼研究部長、鋼材第2研究部長等を歴任、工学博士。
| 発足から今までの主な出来事 | |
|
H9.8.29 9.1 9.1 9.22 |
内仲康夫日本鉄鋼協会専務理事ご来所 評価ステーション総合研究官に高橋稔彦氏採用 第2回企画調整委員会開催 フロンティア構造材料研究センター所内研究発表会開催 |
|
今後の予定 |
|
|
H9.10 9.10 9.11 H10.3 |
第1回企画調整小委員会開催 第3回企画調整委員会開催 80キロ、150キロ、耐熱鋼、耐食鋼研究作業分科会開催 平成9年度ワークショップ開催 |
本ページに関するお問い合わせ先:
info@nims.go.jp