
[更新日'98/11/1]

平成10年11月号(通巻第15号)
目 次
建設省建築研究所 第三研究部長 平石 久廣
 国内で鉄骨造建築物に使用される鉄骨は年間約1千万トンといわれている。しかし、これらの鉄骨が使用される建築物は、1階建てから超高層建築物まで箱形の形状のものからドーム形状のものまで多種多様であるが、使用されている鋼材は、大部分がいわゆる一般(溶接)構造用鋼材である。これらは多くの実績をもつ材料であるが、これから需要が高まると思われる高性能材料を主に建築物の構造安全性等の観点から見てみると、次のような材料が考えられる。
国内で鉄骨造建築物に使用される鉄骨は年間約1千万トンといわれている。しかし、これらの鉄骨が使用される建築物は、1階建てから超高層建築物まで箱形の形状のものからドーム形状のものまで多種多様であるが、使用されている鋼材は、大部分がいわゆる一般(溶接)構造用鋼材である。これらは多くの実績をもつ材料であるが、これから需要が高まると思われる高性能材料を主に建築物の構造安全性等の観点から見てみると、次のような材料が考えられる。
・強度、靱性、エネルギー吸収能力等に特に優れている材料。
・接合(溶接など)に特殊な技能を必要とせず、接合性能の検査・評価が容易な材料。
・耐火性能、耐久性能等に特に優れている材料。
これらの性能は、一般には相反する要因を包含しており、すべての性能を満足するような鋼材は難しいだろうが、設計者がそれら一つ一つに優れたものを適材適所に用いることができるような設計体系を築くことも大切であると考えている。
さらに、新世紀材料という観点から、次のような機能が実用化されれば、建築物の構造性能を飛躍的に向上させることができる。
・損傷(亀裂、塑性変形等)を検知し、自己修復あるいは外部からの簡単な刺激で容易に修復できる材料。
・地震時等に剛性等を自由にコントロールできる材料。(これによって、構造物の応答を小さくし、安全性を高めることができる。)
これらは、システムとして一部実現されているが、比較的安価で信頼性の高い材料レベルとしての開発が期待される。
これまでユーザー側と材料開発側は、経済行為の上での発注者と製造者という関係が強かったが、これからは互いに情報交換を進め、一体となった材料開発が求められる。そういう意味で新世紀構造材料プロジェクトが、鉄鋼材料開発側とユーザー側の交流の核にもなることを期待している。
2.秋の学会参加報告
80キロ鋼―鉄鋼協会、金属学会、溶接学会、IIW、機械学会
超微細粒鋼に関する鉄鋼協会の討論会は150人定員教室で立ち見が出る盛況ぶりで、スーパーメタルやその他の微細粒鋼の研究の成果を交えて、活発に議論が行われた。一般講演も好評、微細化研究への関心は高かった。話題の中心は微細化のメカニズムについてであったが、引張特性の取得を急ぐことや既存設備で対応可能な微細化検討が要望された。討論会の継続開催に協力し、重要な課題を段階的に解決、解明していく弾みにしていきたい。
溶接学会では、我々は超微細粒鋼の溶接にとって熱影響部の粗粒化抑制のため狭開先溶接とレーザー溶接の開発の重要性を強調し、その関係の発表を行ってきている。その効果もあってか、セッションが設けられるほど発表件数が増え盛況だった。今後の意味ある貢献のためには、ハード面での実証などの必要性が痛感された。圧縮残留応力による継手疲労特性向上、高温歪みのその場測定についての発表には、反響が大きく、国際的な成果の交流などの申込もあった。
機械学会、鉄鋼協会などにおける変形のモデリングについての数件の発表に対しては、興味深いアプローチとの関心が寄せられた。
150キロ鋼―鉄鋼協会、金属学会
遅れ破壊強度の向上を目的とした新マルテンサイト組織の発表は連続2回目であった。オースフォームによる遅れ破壊向上効果について粒界炭化物の減少と方位のランダム化のどちらが有効であるか等の本質に迫る議論が展開された。ナノ・原子レベルの解析技術はすでに高い評価を受けているが、FIM-APとナノ硬さ試験による強度特性の解析に加え、新たに原子間力顕微鏡を用いた粒界炭化物の観察とEBSD法による疲労変形組織の観察についての発表が行われた。それらの中で、ベイナイト鋼のナノ硬さが粒界近傍で上昇する現象は、透過型電子顕微鏡観察から粒界炭化物と密接に関係することが明らかにされ、注目を集めた。解析技術についての発表は全て最終日の午後であったが、多くの聴衆が集まり、ある会場では廊下から窓越しに講演を聴く状態が発生していた。
耐熱鋼―鉄鋼協会、金属学会
鉄鋼協会の耐熱鋼セッションで14件発表したが、このセッション全体の31件の約半数を占め、当所のアクティビティは多くの人から称賛を得た。この他、ステンレス鋼のセッションで1件、金属学会で1件発表した。前回までは材料創製と評価関係の発表であったが、今回初めて溶接関係の発表も行った。
材料創製関係では、長時間組織安定化の観点から微細炭化物や金属間化合物による析出強化の活用を報告した。特に、FePd基L10型金属間化合物の微細析出は新たな高温強化法として注目された。クリープ強化のための最適組織設計に関しては、違った視点からの指摘も出され活発な討論が行われた。評価関係は、データシートの長時間データを背景にしていることもあって、総じて高い評価を受けた。
耐食鋼―鉄鋼協会、金属学会、腐食防食協会
高純度316Lの清浄度を保持したままで0.5%
N を添加する手法を開発したこと、また、この開発鋼は耐海水試験で優れた耐孔食性能を示すことを発表した。従って高窒素ステンレスはニッケルを含まないオーステナイトステンレス鋼が有効と考えている。耐食溶射については現時点では封孔処理なしの膜を目標としていること、耐食性に優れた膜が得られつつあることなどの現状を報告した。
大気腐食に関しては鉄鋼協会では実環境での暴露試験を主に、腐食防食協会ではさびの特性に及ぼす海塩の影響、さびの起点あるいはその安定化測定手法について、ミクロな解析、さびの物性や構造解析及び環境側の化学作用を中心に発表した。大気腐食への関心が高くその報告は活況を呈し、われわれの研究がこの分野の研究を刺激していると考える。
フロンティア構造材料研究としての耐食鋼研究全般に対して、1)新しい解析法・評価法を提案すること、2)これら新手法を駆使した新海浜耐候性鋼の開発指針を確立すること、
3)促進試験法の確立に注力して欲しいとする意見が多かった。当方の意欲とは逆に、新材料の開発に関しての期待は薄いように感じられた
なお、今回の秋の学会では、当センターから57件の発表を行った。 (志賀 千晃)
来る12月3日(木)、4(金)の両日に亘って、第3回超鉄鋼ワ-クショップを「超鉄鋼材料実現への期待と課題」と題して、金属材料技術研究所(つくば)で開催する。
これからの材料の研究開発では、材料の使用者と製造者が普段から情報を交換し、連携を深めることが重要であると考えられる。
今回のワ-クショップは鉄鋼材料を使用する側と製造する側の研究者・技術者が集まって、21世紀の超鉄鋼材料への期待を語り、研究の現状を理解し、今後の課題を討論する、そういう交流の場となることを願って企画した。
第1日は午前10時から3件の基調講演が行われる。
①21世紀の建築・土木構造物と超鉄鋼材料 (大阪大学 豊田政男教授)
②21世紀の環境問題と超鉄鋼材料 (住友金属工業株式会社 大谷泰夫技監)
③超鉄鋼材料創製の現在 (金属材料技術研究所 福沢章総合研究官)
①と②の講演では、鉄鋼材料を使う側の21世紀の社会・技術の動向と超鉄鋼材料の開発に寄せる期待、③は金属材料技術研究所における研究成果を中心にした超鉄鋼材料の創製の現在が、紹介される。
午後は12時30分からポスタ-発表が開かれ、今回は70件を越える産学官の研究成果が発表される。このうち25件は金材技研外からの発表である。
ついで、4つの研究分野に分かれて、基調講演、ポスタ-発表に加えてそれぞれ使う側と作る側のコメンテ-タ-の方からの話題提供を受けて、期待、研究の現状、今後の課題について突っ込んだ技術討論会を14時15分から行う。
討論内容と司会、コメンテ-タ-の方々は次の通りである。
・80キロ鋼:「低Pcm・超微細粒高強度鋼と新溶接技術による構造物の設計・施工メリットと
新構造物の可能性」(青木博文/横浜国立大、中西保正/石川島播磨重工業、福田俊文/建築研)
・150キロ鋼:「自動車などの機械構造部品の高強度化の動向と材料・製造技術」(小林英男/東京工大、尾谷敬造/日産自動車、蟹澤秀雄/新日本製鐵)
・耐熱鋼:「超々臨界圧発電プラントの設計と材料問題」(福井 寛/日立製作所、増山不二光/三菱重工業、村松清貴/電源開発)
・耐食鋼:「海洋構造物で期待される耐食材料」 (福手 勤/港湾技研、松岡和己/新日本製鐵)
第1日目の最後に、総括討論として4分野の討論会の概要報告と討論を行う。その後17時30分から懇談会(会費制)が開かれる。
2日目は9時から、4つの分野の最先端の研究成果の発表を主にした課題別討論会と見学会が開催される。課題別の発表題目は以下の通りである。
80キロ鋼:「80キロ溶接構造用鋼が克服すべき技術課題」
1)超微細複相組織鋼への期待(長井/金材技研)
2)微細組織鋼の接合実験結果の紹介
・ア-ク溶接模擬の接合組織(伊藤/金材技研)
・スポット溶接模擬の接合組織(大谷/金材技研)
3)酸化物微細分散利用の新しい可能性
・オ-ステナイト粒の成長抑制効果(中島/金材技研)
・酸素鋼の提案(太田口/金材技研)
150キロ鋼:「ギガサイクル疲労」
1)高強度鋼の疲労における内部破壊(小林/東京工大)
2)介在物軟質化技術の基礎(荻林/千葉工大)
3)介在物軟質制御の現状(草野/新日本製鐵)
4)介在物のナノインデンテ-ション(松岡/金材技研)
5)介在物とナノインデンテ-ションのマイクロメカニックス(田中/長岡技術科学大)
耐熱鋼:「長時間耐久化と高温強化」(本討論会のみ8時30分開始)
1)高温機器の損傷事例(時政/近畿大)
2)耐食性と耐久性(丸山/東京工大)
3)溶接継手の損傷と耐久化(長谷川/新日本製鐵)
4)高温強化の理論(丸山/東北大)
5)粉末合金の高温強化(鵜飼/サイクル機構)
6)オ-ステナイト鋼の高温強化(椹木/住友金属工業)
7)フェライト鋼の高温強化(五十嵐/金材技研)
耐食鋼:「超耐食材料と発錆機構」
1)イオンビ-ムデポジション法による高純度鉄薄膜の耐食性(大橋/日立製作所)
2)高純度ステンレス鋼薄膜の耐食性(藤本/大阪大)
3)コ-ルドクル-シブルによる金属の高純度化とその耐食性(櫻谷/金材技研)
4)超高純度ステンレス鋼の耐硝酸腐食(黛/電中研)
5)窒素含有ステンレス鋼の高清浄化と耐海水腐食性(宇野/金材技研)
6)ステンレスの発錆に及ぼす液膜厚さの影響(升田/金材技研)
7)ACMを用いた大気腐食環境のモニタリング(篠原/東京大)
8)交流法による鉄鋼材料の大気腐食のモニタリング(西方/東京工大) (高橋稔彦)
参加費:無料(但し、懇談会は会費制:懇談会出席ご希望の方は、11月20(金)までに、フロンティアセンター業務室にFAX(0298-59-2213)にてご連絡下さい。)
人物紹介(8) センター発足後、フロンティア構造材料研究に参画するため産業界及び大学から当研究所に入所された方の感想と抱負を紹介いたします。
 九津見
啓之
九津見
啓之
1月に初めて金材技研を訪れてから約1年、月日の流れの速さを実感しています。周囲の研究員の方々の豊富な知識に驚きつつ、日々勉強の毎日を送っております。高Crフェライト鋼の水蒸気酸化のメカニズム解明を目指して研究を進めてきましたが、まだまだ研究の入り口といった感触です。このプロジェクトにとって、また自分自身にとっても有意義な研究成果を目指して、今後の研究生活をエンジョイしたいと考えております。
(評価ステーション 第4ユニット 特別流動研究員、日本鋼管㈱から)
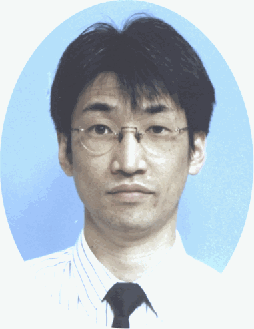 原 徹
原 徹
今年四月に赴任してきました。三月までは大学に勤務しておりましたが、こちらに来てまず思うのは、ディスカッションをしてくださる方が身近に大勢いることで、しかも気軽に相談に乗ってくれることです。専門の分野が違う方々との交流は視点が異なることもあり、非常に刺激になります。現在は、これまでやってきたこととは異なる分野の実験も始めたこともあって、視野が広がっていく楽しみを味わっています。これからよろしくお願いいたします。
(材料創製ステーション 第4ユニット 研究員 帝京大学から)
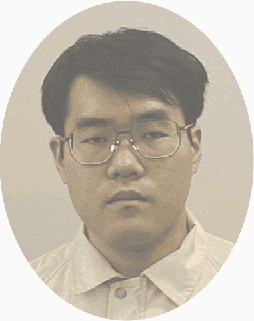 堀内
寿晃
堀内
寿晃
日立研究所から参りました堀内です。学生時代は合金の相安定性のシミュレーション、入社以降は圧延機システムの開発に携わっておりましたが、1年程前からMg合金の研究に取り組んでいました。耐熱鋼は自分にとって新分野であり、毎日が勉強と驚きの連続ですが、少しでも成果を残せるよう心機一転して頑張ろうと思います。趣味は合唱(今も社会人サークルで歌ってます)と旅行(特に地元北海道を廻るのが好き)です。よろしくお願いします。
(評価ステーション 第3ユニット 構造材料特別研究員、㈱日立製作所から)
前号からの主な出来事 |
|
H10.10.21 10.10.23 |
稲葉科学技術政務次官ご来所 第3回超鉄鋼ワークショップ詳細プログラムをインターネットに掲載 |
今後の予定 |
|
H10.11. 5 10.12.3-4 10.12.- |
第5回耐食鋼フォーラム開催(公開) 第3回超鉄鋼ワークショップ開催(公開) 第3回スパイラル研究作業分科会開催 |
バックナンバー:1998/10(14号),9(13号),8(12号),7(11号),
1998/6(10号),5(9号),4(8号),3(7号),2(6号),1(5号),
1997/12(4号),11(3号),10(2号),9(1号)
本ページに関するお問い合わせ先:info@nims.go.jp