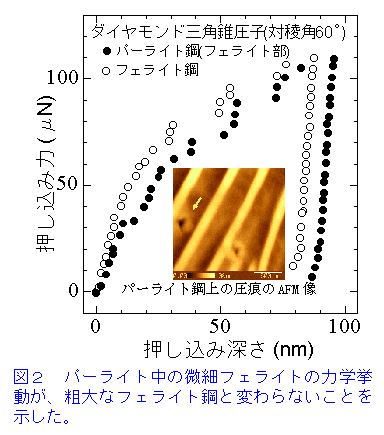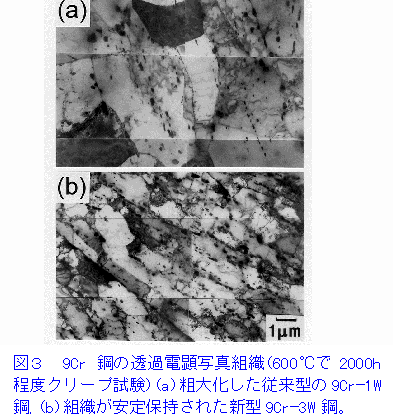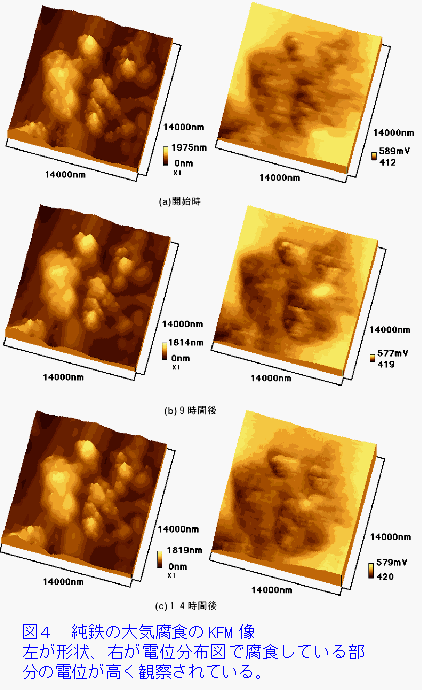[
更新日 '98/6/1]

平成10年6月号(通巻第10号)
目 次
国立研究所のモデルケース
産業技術融合領域研究所長 岸 輝雄
センターの平成9年度活動報告
フロンティア構造材料研究センター長 佐藤 彰
センター便り
バックナンバーへ
1.国立研究所のモデルケース
産業技術融合領域研究所長
日 本 鉄 鋼 協 会 会 長
東京大学教授 岸 輝雄
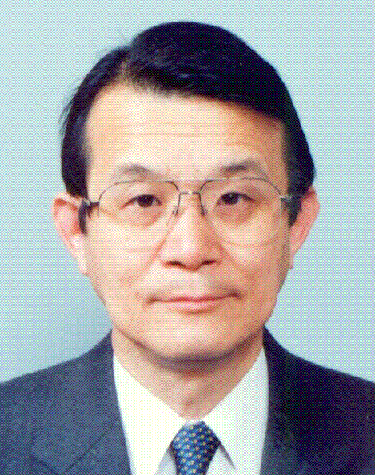 学生時代を思い出しているところである。鉄に憧れ、鉄をやろうと思い、冶金学科に進学した学生が多かった。しかしながら鉄鋼産業の素晴しい発展と高い研究意欲の煽りで、大学では鉄鋼材料から遠ざかざるをえない状況ができてきた。それ故、当時は鉄鋼材料の基礎研究がほぼ一段落し、応用開発研究の時代であると認識することにしたこともある。国立研究所としての金属材料技術研究所も金属の名称にも拘らず、鉄のアクティビティを低下させた時代が続いたと言える。
学生時代を思い出しているところである。鉄に憧れ、鉄をやろうと思い、冶金学科に進学した学生が多かった。しかしながら鉄鋼産業の素晴しい発展と高い研究意欲の煽りで、大学では鉄鋼材料から遠ざかざるをえない状況ができてきた。それ故、当時は鉄鋼材料の基礎研究がほぼ一段落し、応用開発研究の時代であると認識することにしたこともある。国立研究所としての金属材料技術研究所も金属の名称にも拘らず、鉄のアクティビティを低下させた時代が続いたと言える。
高コスト社会になり企業だけでは基礎研究を賄えなくなり、かつまた基礎研究として鉄鋼の分野にもやるべきことがたくさんあることが判明してきた。一方戦後、材料研究の中心となったセラミックス、高分子、半導体材料もその急速な研究開発により、金属材料と同じような状況になり、再びあらゆる材料がその種別を超えて研究を行う時代に来たとも言える。
このような時期に金属材料技術研究所における大きなプロジェクトが始まったことは、誠に喜ばしい限りである。目的を明確に、例えば2倍の強度、2倍の寿命などを掲げながら、それでいて国立研究所として重要な基礎研究を軽視することのない研究開発体制が望まれる。産官学の結集は元より、諸外国からの頭脳及び若手研究者の大幅な導入も期待されよう。工業技術(又は産業技術)は技術の成果そのものが最終評価の対象になるが、科学技術庁の研究は将来の幅広い発展を生み出すシーズに重きが置かれることも重要と言える。目的の明確な数値と拡大可能な萌芽研究とは一見相矛盾するが、その中に難しさとおもしろさが混在していると言えよう。国策を中枢的に推進する国立研究所のモデルケースとしてのプロジェクトの成功を祈りたい。いや、必ず成功させねばならないし、成功するものと確信している。
2.センターの平成9年度活動報告
フロンティア構造材料研究センター長 佐藤 彰
1.はじめに
 昨年4月に発足し、国立研究所としては様々な新しい試みに挑戦していますが、初年度としては円滑に推進できたようです。これは、所内外の関係者の方々のご指導、ご支援、ご協力の賜であり、感謝に堪えません。
昨年4月に発足し、国立研究所としては様々な新しい試みに挑戦していますが、初年度としては円滑に推進できたようです。これは、所内外の関係者の方々のご指導、ご支援、ご協力の賜であり、感謝に堪えません。
発足直後、研究課題等の評価を外部委員からなる事前評価委員会にお願いしました。まず、「国家的且つ時期的重要性が高く、国立研究所が取り上げる研究課題として適切である。」と意義を認めて戴きました。同時に、種々の努力目標を御指摘して戴き、それらを私達の指針としています。
材料科学に関する新しい知見を得ることは研究者の主要な任務です。しかし、ここでは、さらに、材料開発も重要な任務です。約20年後に使用して貰うために、総合的基礎研究を遂行し、次段階の研究へ継続させねばなりません。幸い研究者の発奮により初年度から、様々な良い芽が出て来たと思います。これらの芽をさらに育てていくべく、努力するつもりです。一層のご指導、ご支援、ご協力をお願い致します。
2.研究者及び研究支援者(合計 約120名)と客員研究官(35名)
外部からの受入がほぼ順調にスタートした。
職員(任期付き職員3名を含め:80名)、構造材料特別研究員(9名)、招聘型任期付き研究員(国立研究所採用第1号1名)、重点研究支援協力員
(5名)、特別流動研究員(4名)、受入研究者(STA特別研究員・フェロー:7名)、研究協力者(研究生、大学院生、卒論生:11名)、客員研究官(35名:大学教授33名)
3.主な導入装置
材料創製に力点を置いた装置導入を図った。
微細複相組織形成過程解析装置、高速鍛造加工装置、超清浄溶解凝固装置、極微小領域損傷評価装置、長時間組織シミュレータ、可変雰囲気溶射装置、動的応答現象計測解析装置、レーザー誘起プラズマ構造解析装置、応力評価装置。
4.研究費(予算総額:2,126百万円)
研究費の有効な使い方を工夫した。
試験研究費:902、施設整備費(研究棟):1,187、非常勤職員等の任用及び事務費等:37百万円。
5.主な委員会等の開催
研究の具体的推進、特許の第三者譲渡などについて熱心な討議が展開された。
事前評価委員会;1997.7.1、社会基盤材料技術懇談会;1998.3.31、フロンティア研究推進委員会;1997.6.23、企画調整委員会4回、企画調整小委員会2回、合同スパイラル研究作業分科会1997.11.18。
6.成果・情報の発信
特許出願、学会発表、ニュース発刊などを旺盛に展開できた。
特許;国内出願 26件、海外出願準備中、学会発表;97秋季及び98春季大会の口頭発表;国内132件、海外21件、誌上発表;国内35件,海外33件、学協会への委託調査研究5件。
ワークショップ;1998年1月19日(月)開催;外部参加者 181名,学会等からの表彰;12件、STX-21ニュース発刊、ホームページ開設。
7.研究の進捗
代表的な研究成果を以下に記す。
(1) 微小サンプルでフェライト粒径2.3μmの微細なフェライトーパーライト組織の作製に成功した。フェライト粒の方位はランダムに近い。組成は普通鋼成分のもので、オーステナイト低温域で大きなひずみを加え、制御冷却することにより得た。現在さらなる微細化に挑戦している。(図1)

(2) 100nm以下の微小領域の力学特性を評価できるナノ硬さ試験法を確立した。高強度鋼創製の指導原理を得るために、パーライト鋼中の微細フェライト(図2)や、ばね鋼中の微小介在物などに適用している。
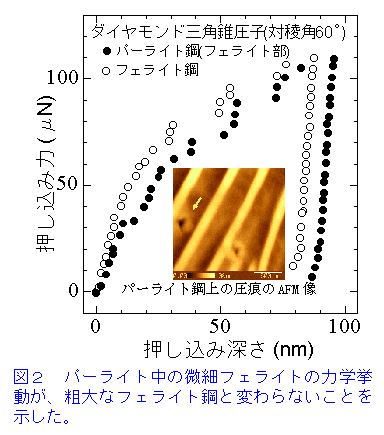
(3) 高温での長時間保持により従来型の鋼では、ラス組織が壊れ、粗大化して強度が低下するのに対して、新型の鋼では、初期の微細なラス組織が安定に保持され、強度が維持されることを示した(図3)。合金設計や析出物制御により、さらなる高温での高強度鋼の開発に挑戦中である。
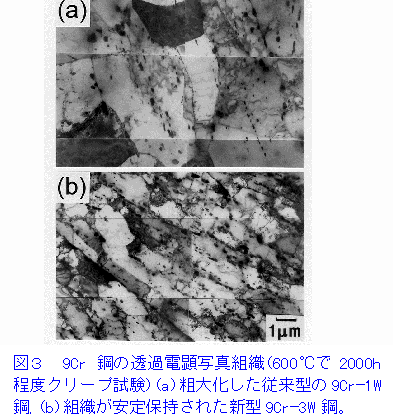
(4) ケルビンフォース顕微鏡による純鉄の大気腐食に伴う表面形状及び電位分布像の連続観察に成功し、さびの進行を形状と電位変化から追跡できた。今後の鉄鋼材料の防食法に関する新規なアイデアの提案が期待される。(図4)
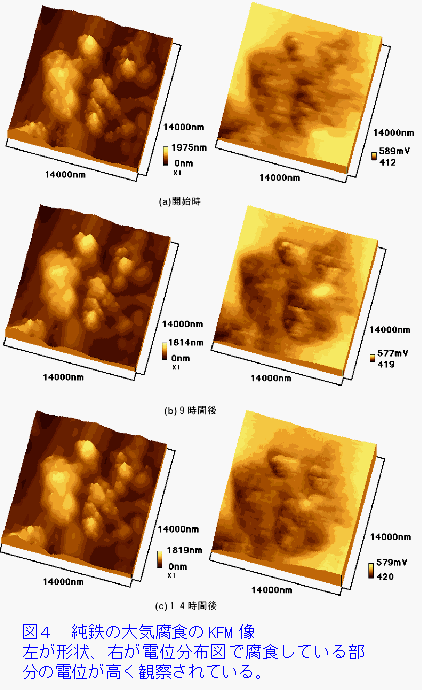
3.センター便り
―春の学会参加報告―
この春、フロンティア構造材料研究センターからは鉄鋼協会、金属学会などを中心に50件を越える発表をしましたが、発表への質問などの端々に、関心の対象が研究内容そのものに移ったことが感じられ、プロジェクトがスタートして1年を経過したことを実感しました。
今期学会での大きな話題は超微細粒鋼でした。当研究センターからの発表は大きな関心を呼びましたが、他にも繰り返し重ね圧延、メカニカルミリングなど様々な方法による超微細粒鋼の創製とその力学的な性質に関する発表が多数ありました。1μm鋼も実験室的には手にすることができるところまで来たことが明らかになりました。私たちは、今後超微細粒バルク材の機械的な性質を調べて構造材料としての可能性を検討すると共に、超微細粒形成の機構を明らかにし、工業化可能な創製法の開発につなげて行きたいと考えています。新しい研究分野が立ち上がってきており大きく育てたいものです。
耐熱鋼の分野では、「超々臨界圧火力発電用先進耐熱鋼」の討論会が鉄鋼協会で行われています。多くは650℃級プラントの実現を視野に入れたもので、現時点での到達点と課題についての密度濃い内容の討論会でした。溶接性あるいは耐酸化性なども両立させなければならないボイラー材の研究の難しさも浮き彫りになりました。当センターからの高強度化の指導原理の提示や、新しい視点からのクリープ強度の評価の研究が高く評価されました。
この他、接合分野では建築、機械など鉄のユーザーの方々の大きな関心を呼び、研究の充実を要望されました。
150キロ超級鋼関係では、焼戻しマルテンサイト鋼の粒界炭化物を制御するという遅れ破壊研究の視点とその実現手法や、超微小硬さ試験とこれを利用した疲労の研究発表に関心が集まりました。
耐食鋼では、ステンレス鋼の耐海水腐食性を超高窒素化と超高清浄化の組み合わせによって図る試み、コ−ルドクル−シブルによる極低P化などの発表に議論が集中しました。 (高橋
稔彦)
−受
賞 報 告−
洪文憙(科学技術特別研究員)、寶野和博(物性解析研究部
第3研究室長)は、「TEMとAPFIMによるパーライト鋼線の微細組織観察」により平成10年3月26日、日本金属学会から金属組織写真賞を授与されました。
松岡三郎(評価ステーション 第2ユニットリーダー)、宮原健介、長島伸夫(同ユニット)と田中紘一先生(当所客員研究官:長岡技術科学大学)は、「AFM超微小硬さ試験機による弾性常数と降伏応力の測定」により平成10年4月3日、日本機械学会から論文賞を授与されました。
| 前号からの主な出来事 |
H10. 5.11
10. 5.14
10. 5.19 |
第2回150キロ分科会開催 第2回耐熱鋼分科会開催
第2回耐食鋼分科会開催 |
今後の予定 |
H10. 6._
10. 6._ |
第5回企画調整委員会開催 第2回研究推進委員会開催 |
バックナンバー
:1998/5(9号),1998/4(8号),1998/3(7号),1998/2(6号),1998/1(5号),
1997/12(4号), 1997/11(3号),
1997/10(2号), 1997/9(1号)
本ページに関するお問い合わせ先:info@nims.go.jp



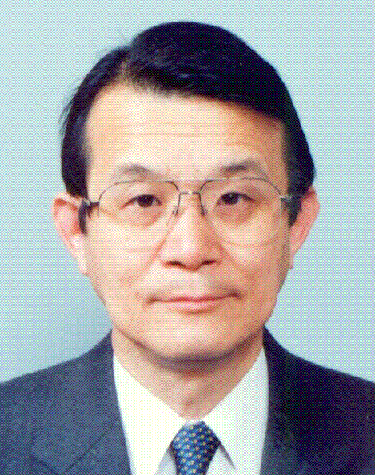 学生時代を思い出しているところである。鉄に憧れ、鉄をやろうと思い、冶金学科に進学した学生が多かった。しかしながら鉄鋼産業の素晴しい発展と高い研究意欲の煽りで、大学では鉄鋼材料から遠ざかざるをえない状況ができてきた。それ故、当時は鉄鋼材料の基礎研究がほぼ一段落し、応用開発研究の時代であると認識することにしたこともある。国立研究所としての金属材料技術研究所も金属の名称にも拘らず、鉄のアクティビティを低下させた時代が続いたと言える。
学生時代を思い出しているところである。鉄に憧れ、鉄をやろうと思い、冶金学科に進学した学生が多かった。しかしながら鉄鋼産業の素晴しい発展と高い研究意欲の煽りで、大学では鉄鋼材料から遠ざかざるをえない状況ができてきた。それ故、当時は鉄鋼材料の基礎研究がほぼ一段落し、応用開発研究の時代であると認識することにしたこともある。国立研究所としての金属材料技術研究所も金属の名称にも拘らず、鉄のアクティビティを低下させた時代が続いたと言える。 昨年4月に発足し、国立研究所としては様々な新しい試みに挑戦していますが、初年度としては円滑に推進できたようです。これは、所内外の関係者の方々のご指導、ご支援、ご協力の賜であり、感謝に堪えません。
昨年4月に発足し、国立研究所としては様々な新しい試みに挑戦していますが、初年度としては円滑に推進できたようです。これは、所内外の関係者の方々のご指導、ご支援、ご協力の賜であり、感謝に堪えません。