
[
更新日 '98/5/6]
平成10年5月号(通巻第9号)
目 次

どのセンサーが働くのか、ああ何か大きく変わりそうだなと感じることがある。社会、経済、人、もちろん、技術に対してもだ。
昨年から始まったSTX-21研究プロジェクトの活動を見ていると、鉄鋼材料の世界にまた一つ革新が起きるのかなという予感を感じる。ことに800MPa級、1500MPa超級材料開発タスクフォースで取り上げられている超微細結晶粒制御の技術思想が、その感を強くさせる。
鉄鋼材料は長い開発の歴史の中で、幾たびかの技術革新を遂げてきた。今や単純な合金成分調整だけでなく、造り込み技術との複雑な融合で高い性能が発揮されている。さらに他材料に比べて、コストパフォーマンスの良さ、信頼性の高さから、来る次世紀においても構造材料の中枢材料として期待されている。換言すれば、革新される性能は、必ず高い実用性を有していることが要求されるということである。
本研究プロジェクトが、その期待に応えてくれる予感を抱かせるが、基礎研究ではあるものの、目標達成型としてスムーズに実用化へ移行できる基礎研究を目指す以上、留意すべき点がある。それは、実用性の高い材料にするためには、材料として製造がし易いことはもちろんのこと、材料を使う立場の技術とも一体化が必要である点である。つまり、鋼構造物としての設計、成形、接合、破壊防止、防食といった利用加工技術によく適合する材料でないと、実用化はできない。
この点に対応して、我々鉄鋼企業研究者は、単に鉄鋼製造の立場からだけではなく、使用する立場での課題を自ら積極的に研究すると共に、鉄鋼ユーザーとの共同研究によって、利用加工上の諸課題への対策を織り込んだ鉄鋼材料を開発して来た。研究体制として既に構造体化及び評価の両ステーションを置いており、その認識は十分であると思うが、鉄鋼企業、鋼構造加工企業、建築研、土木研等の研究者の参加を今以上に呼びかけ、材料屋の独りよがりの研究開発にならないように進めることが肝要である。
盛り上がった木肌から出た芽が勢いよく伸びる。これが春の木々である。萌芽したSTX-21を陽光の中に勢いよく伸ばして頂きたい。
粒径1μm以下のフェライト粒組織の創製
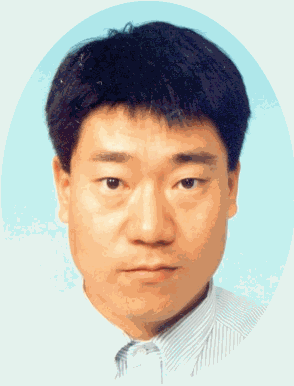
組織微細化による高強度化
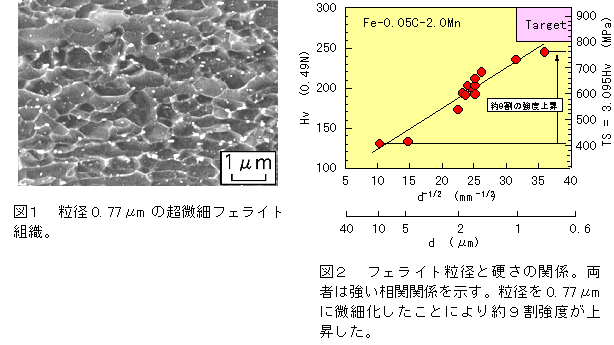
耐酸化性に優れた高強度フェライト系耐熱鋼の開発
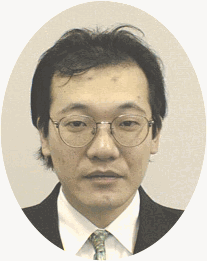
基本的考え方
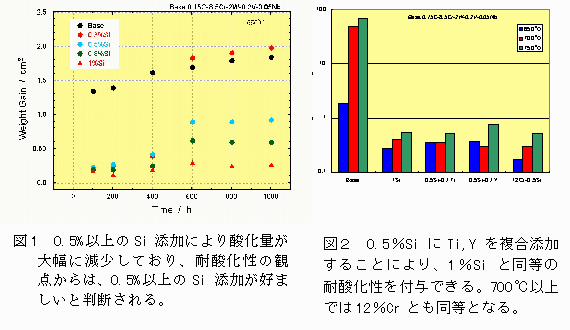
人物往来 ―英国ケンブリッジ大学H.Bhadeshia先生―
平成10年3月10日から一週間、相変態・組織制御を中心とした鉄鋼材料研究の第一人者である英国ケンブリッジ大学のHarry Bhadeshia先生を金材技研にお招きして研究討論を行いました。短い滞在期間ではありましたが、(1) Design of Heat-Resistant Steel、 (2) Design of Welding Alloys、 (3) Heterogeneous Nucleation on Oxides in Steelsの3件のご講演を頂くとともに、所内の研究者および客員研究官の先生方を交えて8件の自由討論会を行っていただきました。講演は「質問があるときは何時でもどうぞ」のスタイルで行っていただき活発な意見交換がなされました。自由討論会には多くの希望者があったために土曜日までスケジューリングに入れる必要がありましたが、先生は快く応じて下さいました。「観光よりは研究討論がお好き」というのは今でも真実です。
鉄鋼材料研究を心から愛しておられる先生は、「超鉄鋼材料プロジェクト」によって鉄鋼材料研究の大きなサイトが出来たことを本当に喜んでおられました。今回学期末のお忙しい時期に来日下さいました先生に心から御礼申し上げるとともに、頂いたご意見は必ず「超鉄鋼材料研究」推進に生かしたいと考えております。最後に、先生から届いた礼状の一部をご紹介します。
Tsukuba is a wonderful place, full of science and now full of steel. What more can one ask for? I really feel that the Ultra Steels project is visionary and will achieve more than just the four themes set out currently. With the ambitious experiments planned and in progress, I am certain that there is a good chance of a breakthrough. (津崎 兼彰)
受
賞 報 告升田博之
(構造体化ステーション 第6ユニットリーダー)は、「走査プローブ顕微鏡(SPM)を用いて水溶液腐食、大気腐食研究分野に新しい領域を開いた」ことにより平成10年3月26日、日本金属学会から功績賞を授与されました。長井寿
(材料創製ステーション 第3ユニットリーダー)は、「低温用構造材料の組織と機械的性質の関係に関する研究」により平成10年4月1日、日本鉄鋼協会から西山記念賞を授与されました。阿部冨士雄
(評価ステーション 第3ユニットリーダー)は、「耐熱鋼および耐熱合金の微細組織変化とクリープ強度特性に関する研究」により平成10年4月1日、日本鉄鋼協会から西山記念賞を授与されました。| 前号からの主な出来事 | |
|
H10.4.3 10.4.23 |
「軟鋼の強度を2倍に高める」がNHK、日経新聞他で報道される 第3回企画調整小委員会開催 |
|
今後の予定 |
|
|
H10.5._ 10.6._ 10.6._ |
第2回研究作業委員会開催 第5回企画調整委員会開催 第2回研究推進委員会開催 |
本ページに関するお問い合わせ先:
info@nims.go.jp