
[更新日'98/7/1]

平成10年7月号(通巻第11号)
目 次
東海大学教授 唐津 一
 日本経済研究センターで2025年委員会の作業をやった。これは四半世紀先の日本の経済とそれを支える技術、また社会環境などを分担して予測しようという目的の委員会だが、私はそこで技術を担当した。さて、そこでどのようにして25年先を見るかという方法論がいる。そこで私は逆に過去25年間に日本の科学技術が、どのようにして発展して来たかの足取りを調べてみたのだが、ひとつの重要な経験則を発見した。それは、ある新しい科学技術の発見や発明がなされたとしても、これをモノに仕上げて製品として市場に出荷し、ひとつの経済単位としての地位を確立するには、余程早くて10年一般には20年はかかるということである。勿論、中には全く突発的に生まれてくるものもあるが、それは例外である。だから25年先のことは、現在我々が持っている既知の知識でかなりのところまで予見できるということであった。逆に言うと技術予測にとって25年というのは実に手頃なスパンだということである。
日本経済研究センターで2025年委員会の作業をやった。これは四半世紀先の日本の経済とそれを支える技術、また社会環境などを分担して予測しようという目的の委員会だが、私はそこで技術を担当した。さて、そこでどのようにして25年先を見るかという方法論がいる。そこで私は逆に過去25年間に日本の科学技術が、どのようにして発展して来たかの足取りを調べてみたのだが、ひとつの重要な経験則を発見した。それは、ある新しい科学技術の発見や発明がなされたとしても、これをモノに仕上げて製品として市場に出荷し、ひとつの経済単位としての地位を確立するには、余程早くて10年一般には20年はかかるということである。勿論、中には全く突発的に生まれてくるものもあるが、それは例外である。だから25年先のことは、現在我々が持っている既知の知識でかなりのところまで予見できるということであった。逆に言うと技術予測にとって25年というのは実に手頃なスパンだということである。
いま産業のコメとはやしたてられる半導体が生まれて今年で50年になるが、それが本格的に市場を拡大して日本で10兆円の規模になったのは最近のことであって漸く鉄鋼業の規模に近づいたのである。超電導を使ったリニアモータカーが時速550キロで走ったが、このプロジェクトがスタートしたのは新幹線が完成した直後からというから、30年近くたっている。
世間では新技術が生まれたというと明日にも商売になるような受け止め方をして株が上がることもあるが、技術を育てて本当の意味でのビジネスになるには殆ど無数の周辺技術の開発が必要だし、まだどのようにしてユーザーを開拓するかについても成功には時間がかかる。
いまでこそ液晶パネルは電子部品の標準的な製品になったが、その発明は1970年のRCAの発表であった。ところが肝心のRCAでは原理的可能性を証明しただけで育てることをしなかった。これを製品化して成功したのは日本の企業だった。その成否の別れ目は技術に対する評価とその予見に基づいて製品として育て上げる努力とである。液晶は比較的早かったが、それでも電卓用や時計用の小さなモノから始めて今のパソコン用の大型ディスプレイの生産技術確立までには20年近い年月が経過している。
これまでの鋼材の2倍の強度を実現するという超鉄鋼の研究開発について、金属材料技術研究所からの発表があった。その将来が楽しみである。
第2回フロンティア研究推進委員会:平成10年6月12日/つくば(本所)
希望委員に施設見学をいただいた後、午後2時から5時までの3時間にわたって報告と審議がなされました。
最初に佐藤センタ-長が平成9年度のまとめを報告しました。まず、皆様の強力なご支援のお陰で、環境整備をしながら研究を軌道に乗せるというめまぐるしい1年を乗り切れたと謝意を述べました。続いて、注目される新技術の芽の育成、独創性に富んだ設備の順調な導入、各種委員会、研究会活動の立ち上げと充実、23件の特許出願、約七十編の論文、百数十件の学会発表などについて報告しました。引き続き4タスクフォ-スリ-ダ-が、各課題における平成9年度の成果と今後の研究計画を紹介し、質疑が行われました。次いで平成10年度予算(案)と平成11年度概算要求(案)及びワ-クショップ、広報活動状況などが説明され、全体の審議に移りました。
今回の審議は、大谷委員から指摘されたように、この1年で端緒的な研究成果が出てきたことを前提としておりました。小林委員の意見にそれは代表されています。「使う側の考え方の十分な理解と、一方、フロンティア側から使う側への明確な材料コンセプトの発信が不可欠。この相互理解を土台にすべき。ワ-クショップは両者の相互理解を進める格好の場。材料を作る側、使う側双方の関連学協会の協賛を得て、相互理解の場を提供するという姿勢を求める。」というものでした。
広く外部の方々の意見を頂戴し、また私達のコンセプトも発信し、その交流の中で研究の方向を絞り込んで行くために様々な形で対話してまいりたいと考えております。この機会に、より良い対話の仕方についてもお知恵を拝借したいと考えております。
その他、民間側に比べてやや疎遠に見える大学の先生方との連携をさらに工夫するようにという貴重なご指摘もいただきました。
委員会後の懇談会の席で石田委員から、「このプロジェクトは全世界が注目している、成功を祈っている、我々もできる限り協力する。」という力強いお言葉をいただきました。委員会でいただきました貴重なご意見、厳しい叱正もすべて石田委員のご発言に集約されていると思います。ご期待に添うよう全力を傾けたいと思います。遠いつくばまでお運びいただき、熱心にご審議いただきました委員の皆様に心よりお礼を申し上げます。
(高橋 稔彦)

第2回80キロ研究作業分科会:平成10年4月24日/東京(科学技術庁会議室)
春季学会で新しい成果を発表した興奮のさめない内に、分科会を開催しました。午前10時から延べ6時間にもわたる討議で、大変有意義な成果があったと感謝しております。主議題は、「微細組織の造り込みの現状と課題」と「接合研究の在り方」の二つでした。
「微細組織の造り込み」では、バリアント選択性回避と変形モードの関係、分散第二相の組織制御利用などに関心が集中しました。私共から、微細組織サンプルの大型化展開へのご協力をお願いしました。「接合研究の在り方」では、狭開先溶接の有効性の実証、レーザー溶接、低温接合技術の意義などについて、多くの意見が出されました。私共から、使う場での問題意識をより直接的に把握させていただきたい旨お願いしました。また、「微細組織」-「小入熱溶接」スパイラル研究の観点が弱いという適切な指摘があり、可能なレベルから早急に実験を進めることを約束しました。計測やシミュレーションなどが時間制約で報告だけに終わったのは反省点です。
特許も12件申請し、研究成果の学会等での積極的な発信にも心がけています。しかし、実用上からの観点、学術的な立場からの観点を交換しながら密度濃い討論ができるのがこの分科会の特徴です。いっそう活発で有意義な議論と交流を進めていきたいと熱望しています。次回は秋に150㌔との合同開催を予定しています。 (長井 寿)
第2回150キロ研究作業分科会:平成10年5月11日/東京(科学技術庁会議室)
いずれも第一線で活躍されている所外委員には、ご多忙にも拘わらず丸一日の会議に出席くださり、貴重で、ある場合には厳しいご指摘をいただき感謝しております。
高橋主査より、「私達は単なる解析の請負をする積もりはないけれども、金材技研には『APFIM、ナノ硬さ、ナノ粒界解析など』の優れものがあります。これを武器に皆様との連携を強めることもプロジェクトの一つの狙いなので、魅力的な提案をお待ちします。」との挨拶があり、和やかな雰囲気の中に分科会が始まりました。
まず、遅れ破壊について討議しました。凹凸γ粒界を持つ新マルテンサイト組織は可能性が高いのではなどと活発な意見が出ました。次いで、疲労、ナノ・原子レベル解析、高剛性鋼の課題に移りました。APFIMでは、高疲労強度化のキーはMo-Nペアであるとする解析力の威力を示しましたが、新しい武器が最初に紹介されたことから、他の課題にもどしどし利用すべきという厳しい注文も出ました。
今回は所外委員講演を企画しました。家口委員に「自動車用高強度鋼の疲労破壊」について話題提供いただき、ばね等の高強度鋼における介在物起点の超高サイクル疲労破壊の克服には介在物の力学特性制御も重要と言われました。私共の方向とも一致し、大変勇気付けられました。
7時間にも及びましたが、議論が途切れることなく、実り多い分科会となりました。半年後にも今回以上の活発な討議をいただきますようお願い申し上げます。(松岡
三郎)
第2回耐熱鋼研究作業分科会:平成10年5月14日/東京(材料試験事務所)
午前10時から分科会を開きました。「前回の午後3時間半だけでは短すぎる。」という所外委員からの指摘がありましたので、今回は十分時間をとらせていただきました。
午前中は、研究計画概要、各サブテーマ進捗状況についての報告、質疑応答が手際よく淡々と進められました。今回は具体的データの報告を意識しました。昼食時にある委員より、「興味ある展開がいくつかあった。材料創製、溶接、評価とまとめて話を聞くだけでも、分科会に出る価値がある。」との意見を聞き、大変勇気付けられる思いをしました。
午後は、耐酸化性、疲労特性の研究トピックス紹介の後、「USCプラント実現に向けた世界の動向と材料開発の指針」について、増山委員に特別講演をお願いしました。この話題提供により、分科会全体の一体感が強まったと思います。最後の総合討論はさながら学会の耐熱鋼セッションの延長といった様相で熱が入り、時間切れ打ち切りとなりました。特に、クリープ強化機構や焼戻マルテンサイト組織設計に関して意見が出ました。これらは学会でも最もホットなテーマで、指導原理が模索されているところです。かなり厳しい意見もありましたが、活発な討論になったのは新しい具体的データを示せたためと思っています。懇親会でも、高強度化の話に花が咲いていました。今後とも、よろしくお願いします。(阿部
冨士雄)
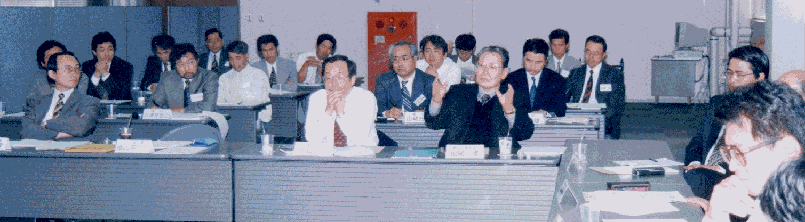
第2回耐食鋼研究作業分科会:平成10年5月19日/東京(材料試験事務所)
腐食防食協会の年会開催時期に合わせて、分科会を開きました。
主査挨拶に続き、平成9年度後期の研究進捗状況、研究成果概況、さらに平成10年度事業計画等の説明をしました。次いで6サブテーマから進捗と成果を報告しました。この中で、特に極低りんステンレス鋼は耐粒界腐食性に優れた耐海水材料として期待されること、新しいガス炎溶射膜が大きな圧縮応力を示し耐海水被覆として応用を探索していること、耐海浜低合金鋼開発に対する基本指針を得つつあること等が注目されました。心暖まる声援とともに厳しい指摘もありました。ステンレスの耐海水性改善を窒素だけに依存することへの限界が指摘されましたが、省資源材料開発を目標とし、超高窒素化と清浄化の併用によって耐食性限界へ挑戦する基本方針を説明しました。溶射膜の耐海水被覆としての将来展望、鉄さびの発生と安定化機構についてもご意見をいただきました。
総合討論でも示唆に富む指摘がありました。与えられた環境における材料の限界を把握や、腐食メカニズム解明が最重要という基礎研究重視論とともに、国研にありがちな計画や評価の緩慢さに対する注文もありました。具体的には達成目標を年次計画として明示すること,更に、その達成度を一定期間後に評価する必要があるとの指摘です。本タスクフォースにおける研究はこの趣旨に沿って動いているはずですが、民間委員の視点からはまだ甘さが残っているようで、身の引き締まる思いでした。(小玉
俊明)
3.センター便り
受 賞 報 告
前号からの主な出来事 |
|
H10. 6. 1 10. 6.12 |
第5回企画調整委員会開催 第2回研究推進委員会開催 |
今後の予定 |
|
H10. 9.-- 10.10.-- 10.12.-- |
第6回企画調整委員会開催 第3回スパイラル研究作業分科会開催 平成10年度ワークショップ開催 |
バックナンバー:1998/6(10号),1998/5(9号),1998/4(8号),1998/3(7号),1998/2(6号),1998/1(5号),
1997/12(4号), 1997/11(3号), 1997/10(2号), 1997/9(1号)
本ページに関するお問い合わせ先:info@nims.go.jp