
[
更新日 '98/3/20]
平成10年3月号(通巻第7号)
目 次

学術研究は、本来営利とは無関係に、思考の赴くままに自由な発想で真理の探究を行う知的行為である。そもそも学術は、古来から人類の智恵として発達し、利益を生む技術とは大きく異なる分野である。これに対して、産業は、古くは主に衣・食・住を基本として家内工業的に発達してきたが、19世紀の産業革命によって、大量生産技術の確立と交通機関の発達による物流が近代工業の発展を促した。この近代産業の形成は社会システムそのものを根底から変えたのである。従って、学術と産業との隔離が進み一体化しないのが通常である。
しかし、近年は学術と産業が密接に関連する場合が多く見受けられるようになった。すなわち、学術の基礎研究の中から新しい産業が生まれる傾向が強くなっており、しばしば新産業の形成に極めて重要な役割を果たすようになっている。とくに、独創的新分野の形成が求められる場合に重要である。欧米の産業界では常に学術研究を重視しており、企業研究所においてさえ多くのノーベル賞受賞者が生まれているのである。これと較べて、日本の産業界では学術の重要性を軽視しがちであり、産業と学術との間に遊離が生じている。
例えば、鉄鋼業界にあっては、昭和40年代後半に粗鋼生産量が1億トンを実現し、世界一の鉄鋼生産国として君臨した時代から、大学と鉄鋼業界との遊離が進行し始めたのである。鉄鋼業界は資金にまかせて独自の基礎研究所や中央研究所と言う大型研究施設を整え、また優秀な若手研究者を集めた。このような状況下で、大学における鉄鋼分野への興味は次第に失われ、今では大部分の大学から鉄鋼名の講座は消滅してしまい、鉄鋼学を十分に学んだ学生は激減してしまっている。ところが、現在日本の鉄鋼業界にも転機がやってきた。後進の国々の急成長により日本の地位は低下し、粗鋼生産量は今や中国に追い抜かれ、生産量の最大メーカも韓国に移った。鉄鋼産業が今後生き残るためには、学・官との協調によって新しくかつ高度な基盤技術を自ら開発しなければならないと言える。これからは、学術が創造的産業の源となることを十分に理解せねばならない時代に入ったのである。本フロンティア構想はその試金石になるであろうと言う点で大いに注目される。
In-Situひずみ測定手法の応用
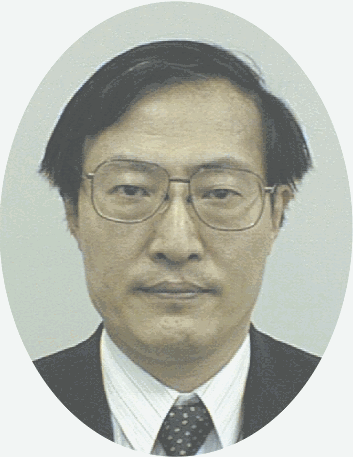
レーザースペックルひずみ測定法の応用
溶接のような局部加熱途上の高温域から室温にいたる広範囲のひずみをその場測定することは、高温割れ発生に関する情報取得、また残留応力の推測など力学的見地から重要である。しかし溶接部は一時的にせよ1000℃以上の高温に曝されるため、従来の貼付け式のゲージなど接触法でひずみを測定することは不可能である。そこで、当センターにおいては、
裏波ビードのひずみ測定
現在、鋼板の裏面まで溶込んだ場合すなわち裏波表面のひずみ測定を行っている。その測定結果の一部を図2に示す。
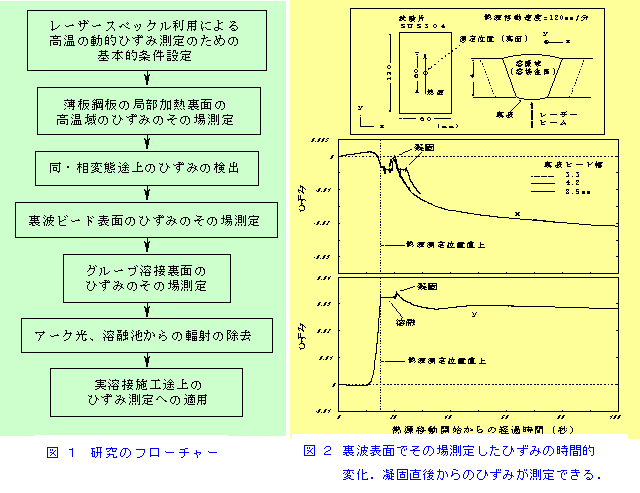
去る1月19日につくばの金属材料技術研究所において、超鉄鋼ワ-クショップ’98が、「超鉄鋼材料:実現への萌芽技術」と題して開かれました。このワ-クショップは、「超鉄鋼材料プロジェクトの狙いと1年目の成果」を紹介し、併せてコメンテ-タ-を含む外部の方々から本プロジェクトに関わる話題を提供していただいて、超鉄鋼の実現に向けて議論を深めることを目的としました。
当日は、外部からの参加者が181名と予想をはるかに越え、補助席も満員で立ち見が出る盛況でした。産業界からは120名の参加者がありましたが、鉄鋼、重工メ-カ-はもとより自動車、建築、電気などの鉄鋼材料の最終ユ-ザ-の方にも参加いただきました。また、大学、官庁、協会等からも60名を越える参加をいただきましたが、この中には10名を越える学生が含まれております。
午前中は、フロンティア構造材料研究センタ-長ならびに4人のタスクフォ-スリ-ダ-から、80キロ鋼、150キロ超級鋼、フェライト系耐熱鋼及び耐食鋼研究の狙いとこれまでに得られた成果の概要が紹介されました。
午後は最初にポスタ-セッションが開かれ、大学、民間からの16件を合わせて54件の超鉄鋼に関わる研究成果が披露されました。その後、高木節雄(九州大学)、松田福久(発電技検)、松尾孝(東京工業大学)、水流徹(東京工業大学)の各先生から話題を提供していただき、今後の研究の展開に関する総合討論が行われました。
80キロ鋼では、超微細粒鋼創製に関して機構の解明への要望とスケールアップへの期待が寄せられ、また小入熱溶接技術及び溶接継手の疲労強度向上技術に関しては、技術内容が評価されると同時に作業性の向上などに有益なコメントが寄せられました。
150キロ超級鋼では遅れ破壊や疲労の研究の進め方に関する議論が行われ、多くの助言が寄せられました。またこの研究の特徴である原子レベル、ナノレベルの解析技術を用いた機構解明・指導原理の提示に高い期待が集まると共に協同作業への希望も寄せられました。
耐熱鋼ではマルテンサイト組織の長時間安定性の向上に視点を置くアプローチが支持されると同時に、その手段であるIrの効果の解明あるいは基底クリープ強度増加への努力が要望されました。更に耐酸化性の向上では強度との両立などの観点から助言が寄せられました。
耐食鋼では、この分野の基礎となる大気腐食の反応を正確に解析できる暴露試験法の確立、安定さびの生成機構の解明が要望されると共に、創製技術で浮揚溶解技術のスケールアップ、高窒素ステンレス鋼の高耐食性の指導原理の確立などが求められました。
総合討論では、金材技研がこのプロジェクトを成功させて日本の鉄鋼研究のセンターになることへの期待も述べられました。
私たちは、ワークショップを通じてこのプロジェクトと金材技研に寄せられている期待の大きさと広がりを改めて実感し、目標の達成に全力を傾ける決意を新たにしました。ワークショップに参加いただいた皆様に心から感謝申し上げると共に、益々のご支援をお願いして超鉄鋼ワークショップ’98の開催報告と致します。
(高橋 稔彦)
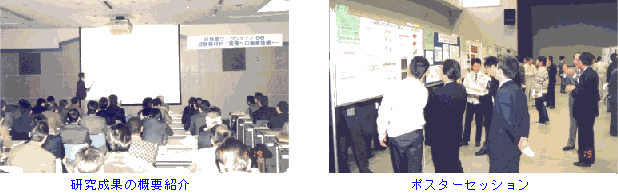
人物紹介(4)
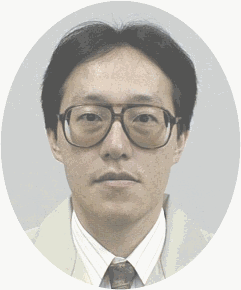
西村 俊弥
1月のワークショップでは発表する機会を得ることができたのですが、外部の方々からは基礎機構から今後の展開まで幅広く質問され、冷汗をかくとともに本プロジェクトへの期待の大きさを再度実感致しました。今後、金材研の様々な専門家の教えを頂き、私の担当する耐食鋼の研究分野において成果が出せるように努力致します。また、レベルの高い金材研の研究環境の中で自分自身のポテンシャルも上げていきたいと考えております。
(構造体化ステーション
第5ユニット、構造材料特別研究員、日本鋼管㈱より)

山本 正弘
8月に赴任して約半年が過ぎました。ようやく金材研の中に自分の居場所ができてきたように感じているところです。
超鉄鋼プロジェクトでは、耐食鋼のタスクフォースメンバーとして、鋼材の屋外での腐食挙動の詳細を明らかにし、耐食材料の開発指針を出していこうとしております。屋外での鋼材の腐食反応を解明するには、自然を相手にしていることもあり時間もかかります。成果を焦らず、一歩ずつ進み、金材研でしかできない研究結果を出そうと考えています。
(構造体化ステーション
第5ユニット、構造材料特別研究員、新日本製鐵㈱より)
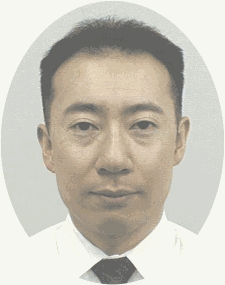
遊佐 覚
多彩な人々と自由な雰囲気、豊富な設備という金材技研の環境は、研究にとってある意味で理想的だと思います。そして、その中で大目標に向かって様々な人の力を結集するプロジェクトに参加する機会が与えられたことは、私にとってステップアップの良い機会だと感じています。
現在担当している「高強度鋼の遅れ破壊特性の向上」というテーマも取っ掛かりがつかめてきましたので、今後は具体的な成果につなげられるように、努力して行きたいと思っております。
(材料創製ステーション
第4ユニット、構造材料特別研究員、石川島播磨重工業㈱より)
前号からの主な出来事 |
|
H10. 2.10 10. 2.12
10. 2.16 10. 2.17 10. 2.20 |
Ir 添加耐熱鋼、化学工業日報に掲載 谷垣科学技術庁長官ご来所 丹羽衆議院議員ご来所 第2回企画調整委員会開催 浮遊溶解で新技術、化学工業日報に掲載 唐津東海大学教授ご来所 |
今後の予定 |
|
H10. 3.__ 10. 4.__ 10. 4.__ 10. 5.__ |
春の学会に向けての所内検討会開催 第5回企画調整委員会開催 第2回スパイラル研究作業委員会開催 第2回研究推進委員会開催 |
本ページに関するお問い合わせ先:info@nims.go.jp