
[更新日'98/8/1]

平成10年8月号(通巻第12号)
目 次
三菱重工業株式会社 常務取締役技術本部長 田中 重穂
 わが国では橋梁や各種建造物の社会インフラの整備・維持コストの低減、また、エネルギーや素材の生産設備における省資源・省エネルギーと地球環境対策が重要な課題であり、各分野において種々の取組みがなされている。例えば、エネルギーシステムにおいて重工業では、(1)高効率化を中心とする省資源、(2)廃棄物削減、(3)廃棄物の再資源化リサイクル、(4)リサイクル不可能な廃棄物の無害化貯蔵および(5)自然エネルギーの利用拡大による資源確保にバランスよく寄与するシステム開発を行い、地球環境を維持、さらには改良しつつ、持続的に産業の発展を可能にしなければならないと考える。
わが国では橋梁や各種建造物の社会インフラの整備・維持コストの低減、また、エネルギーや素材の生産設備における省資源・省エネルギーと地球環境対策が重要な課題であり、各分野において種々の取組みがなされている。例えば、エネルギーシステムにおいて重工業では、(1)高効率化を中心とする省資源、(2)廃棄物削減、(3)廃棄物の再資源化リサイクル、(4)リサイクル不可能な廃棄物の無害化貯蔵および(5)自然エネルギーの利用拡大による資源確保にバランスよく寄与するシステム開発を行い、地球環境を維持、さらには改良しつつ、持続的に産業の発展を可能にしなければならないと考える。
さて、昔から「材料を制する者は技術を制する」と言われているが、確かに画期的材料が出現した時には大きな技術革新が起こることは過去にも多くの例がある。昨年4月に発足した「新世紀構造材料研究」プロジェクトでは「従来技術の改良」の域を越えて全く新しい視点で技術のブレークスルーを狙った超鉄鋼材料の研究開発が行われている。プロジェクトの目標として強度を2倍、寿命を2倍とすることが明確に挙げられ、コスト低減と環境負担度低減という、経済面とLCA(ライフサイクルアセスメント)を考慮した社会面から極めて有意義な計画であると評価できる。また、ブロジェクトの推進は材料創製、構造体化および評価という3つのステーションに産官学から有為な人材が配置され、密接な連携によってなされており、画期的な成果が期待される。
ところで、鉄鋼材料は従来から広く使用され、長い歴史を持っているために、今さら新しい材料が生まれる余地があるのか、また、研究の余地はあるのかといった素朴な疑問が湧いてくるが、このプロジェクトが発足して以来、報告されている研究成果をみていると、鉄鋼材料の奥深さと無限の魅力を持った研究分野であることを窺い知ることができる。現在、溶接可能な80キロ級高強度鋼、耐水素割れ性を有する150キロ超級高強度鋼、超々臨界圧発電プラント用耐熱鋼、そして海洋性環境用耐食鋼への挑戦が続けらているが、近い将来、これらの努力が実を結び、新材料が次々に実用に供され、上記の社会的要請に応えて産業の発展に寄与することが期待される。また、このプロジェクトが材料科学の新たな発展の基盤となって、わが国の科学技術の進歩に大きく貢献することを願う。
2.TOPICS 高剛性に関する研究
−鉄系高剛性材料の基礎的検討−
プロセス制御研究部 増田 千利
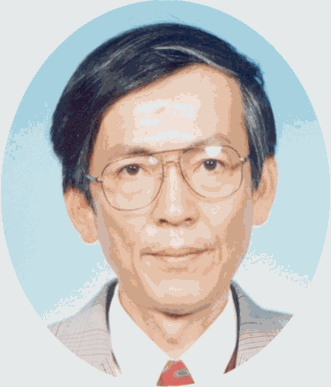 まえがき
まえがき
鉄系材料の剛性を向上させるには、鉄の結晶方位による剛性率の違いを利用する方法、剛性率の高いセラミック粒子や繊維により強化する方法などがある。ここでは高剛性のセラミック粒子や繊維による剛性率の向上を目的として、まず繊維の形状、寸法などの剛性率への影響などを調べて、高剛性材料を創製するために必要となる基礎的な検討を行うとともに、材料を試作した。
強化材料の種類、強化材の形状等の検討と試作結果
鉄系材料としては、まず軟鋼をとりあえず考え、セラミック粒子、繊維としてはアルミニウム合金、チタン合金などの複合材料の強化材として一般的に用いられている強化材料を取り上げて、計算により剛性率を予測してみた。図1には、粒子及び繊維による強化材料を用いて得られる剛性率の計算結果を示す。これから分かるように、粒子としてはWC、棚化物が、ウイスカでは黒鉛の剛性率が高いことが知られている。当然のことながら強化材の剛性率が高ければ、同一体積含有率で、得られる材料の剛性率も高くなる。繊維の長さと直径の比(アスペクト比)が大きくなると剛性率も高くなるが、アスペクト比が約5までは大きな変化が期待できるが、それ以上のアスペクト比では剛性率の向上は期待するほど大きくないことが分かった。
ここではカーボン繊維を用いて鉄の粉末と混合して、高温で、応力下で成形を試みた。その例を図2に示す。これから成形温度、応力がまだ十分でなく、鉄マトリックス中にボイドが残存していた。しかしカーボン繊維は反応していると思われるが、その形を残していることもわかる。
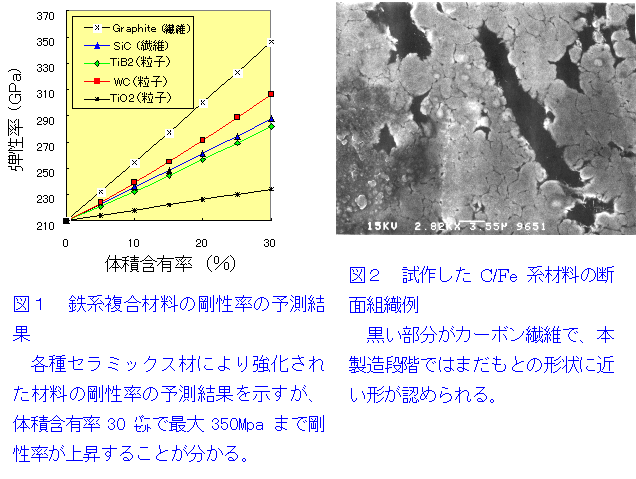
3.TOPICS コールドクルーシブル浮遊溶解によるステンレス鋼のリンの除去
―不純物元素を除去することにより材料の耐食性向上を目指すー
材料創製ステーション 櫻谷 和之
 ステンレス鋼の高純度化による耐食性の向上
ステンレス鋼の高純度化による耐食性の向上
耐食鋼としてのステンレス鋼は、リンが不純物として混入すると、その耐食性が大きく劣化することが知られている。しかしながら、ステンレス鋼の製造工程で、主要成分のクロムの原料であるフェロクロムからのリンの混入が避けられず、また、クロムが共存するため一般的な脱リン法である酸化脱リン精錬ができず、低リン濃度のステンレス鋼を製造することは、経済的にも、技術的にも困難であった。
コールドクルーシブル浮揚溶解法の特徴
コールドクルーシブル浮揚溶解では非接触溶解ができるため、次のような特徴がある。るつぼからの汚染がないため高純度の溶解が可能である。また、スラグ組成を自由に選択できるので、耐火物るつぼとの反応を考えると、今まで不可能であったメタル−スラグ精錬反応を利用することが可能となる。
そこで、これらの特徴を持ったコールドクルーシブル浮揚溶解法をステンレス鋼の脱リンに応用し、極低リン濃度のステンレス鋼を創製することを試みた。
SUS316L材の脱リン実験
図1は、浮揚溶解した800gのSUS316Lに5g及び20gのCa−CaF2系フラックスを使用したときのリンの低減した例である。市販材中のリン濃度はフラックス処理により0.026%から0.001%に下がった。
図2は、5gのCa−CaF2系フラックスを使用したときの処理回数によるリン濃度の低下を示したものである。処理回数と共にリン濃度は低下し、3回の処理で0.002%に下がった。
今後は、ステンレス鋼中のリン濃度の低減に関して、低減の限界、脱リン挙動の解明、低減に有効なフラックスの組成の探索について研究を推進し、併せて、低減した材料の耐食性の向上を確認する実験も行う予定である。
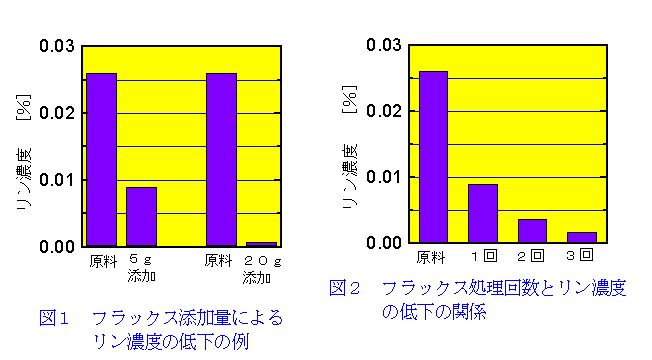
4.センター便り
人物紹介(6)
センター発足後、フロンティア構造材料研究に参画するため産業界及び大学から当研究所に入所された方の感想と抱負を紹介いたします。
 川口 喜昭
川口 喜昭
一月に赴任してはや半年が過ぎましたが,まだうろうろしているというのが正直なところです。これまで従事してきた円筒タンクやパイプラインなどの溶接構造物の大規模破壊にかかわる材料特性の研究は,STX−21のプロジェクトに対しては少々時期尚早かもしれませんが,今までの経験をそのまま持ち込むのではなく,それを再構築し,新たな息吹を与えることによってプロジェクトに寄与することを心がけたいと思っています。新しい材料の実用性は,構造物の破壊安全性が立証されてはじめて世に受け入れられることになると考えられ,材料およびその溶接技術の開発初期から対応しておくことは重要なことだと信じています。
(構造体化ステーション 第2ユニット、特別流動研究員、住友金属工業㈱から)
 野田 和彦
野田 和彦
本年2月よりフロンティア構造材料研究を行う一員として、当センターにて耐食鋼の研究に従事する機会を得ました。以降、耐食鋼タスクフォースの中では違和感を感じることもなく研究させていただいておりますが、金材技研内外の研究者が集うこのプロジェクトの中では、真実を追究する姿勢が共通言語として重要であると考えています。学びの姿勢を忘れず多くの方にご指導いただきながら、恵まれた研究環境に甘えることなく、僅かでも耐食鋼開発に貢献できればと思っております。
(構造体化ステーション 第5ユニット、特別流動研究員、東京工業大学から)
受 賞 報 告
黒田聖治(構造体化ステーション
第2ユニット 主任研究官)、田代安彦(当所外来研究員:東京理科大学大学院生)、湯本久美(東京理科大学教授)平良進、深沼博隆(プラズマ技研工業)は、「Peening
action and residual stresses in HVOF spraying of 316L stainless
steel coatings」により平成10年5月29日、国際溶射会議から優秀論文賞を授与されました。
「第3回超鉄鋼ワークショップ」ポスターセッション参加者の一般公募
当研究所では、本年12月3日(木)4日(金)に標記ワークショップを開催し、初日の午後にポスターセッションを行います。鉄鋼材料に対するご自身の研究あるいは提案などこの機会に発表いただきたく、参加者の一般公募を行います。募集対象の研究分野は①溶接構造用800MPa鋼(微細粒創製技術、溶接技術、継手特性)②高強度鋼の遅れ破壊、疲労、高強度ワイヤ③高強度耐熱鋼(フェライト、オーステナイト)④耐候性鋼、耐海水鋼(フェライト、ステンレス、溶射)などです。なお、詳細につきましは、金属材料技術研究所ホームページ(http://www.nrim.go.jp/)の最新情報をご覧下さい。
前号からの主な出来事 |
|
H10. 7.15 10. 7.15 10. 7.23 10. 7.28 |
日本塑性加工学会関東支部ご来所 板谷通産省鉄鋼課技術振興室長ご来所 田中科技庁科学技術振興局長ご来所 池田科技庁研究開発局長ご来所 |
今後の予定 |
|
H10. 8. - 10. 9. - 10.10. - 10.12. - |
第4回企画調整小委員会開催 第6回企画調整委員会開催 第3回スパイラル研究作業分科会開催 平成10年度ワークショップ開催 |
バックナンバー:1998/7(11号),
1998/ 6(10号), 5(9号),
4(8号), 3(7号),
2(6号), 1(5号),
1997/ 12(4号), 11(3号), 10(2号), 9(1号)
本ページに関するお問い合わせ先:info@nims.go.jp