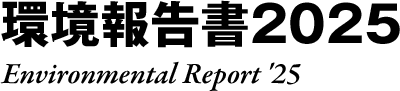NIMS紹介
NIMS紹介
NIMSは、物質と材料の科学技術に関する基礎研究および基盤的研究開発を総合的に行う国立研究開発法人です。物質・材料科学技術に関する研究開発を通して、持続的発展が可能で、安心・安全で快適な生活ができる資源循環可能な社会の実現に貢献します。
1.事業概要
NIMSは、物質・材料研究を専門にする我が国唯一の国立研究開発法人として、物質・材料科学技術の水準の向上を図ります。
 ミッション
ミッション-
・物質・材料科学技術に関する基礎研究及び基盤的研究開発
・研究開発成果の普及とその活用の促進
・NIMSの施設および設備の共用
・研究者、技術者の養成およびその資質の向上
 沿 革
沿 革-
NIMSは、2001年4月に旧科学技術庁所管の2つの国立研究所が統合され独立行政法人として発足後、2015年4月に国立研究開発法人に移行いたしました。
1956年 7月 科学技術庁 金属材料技術研究所 設立 1966年 4月 科学技術庁 無機材質研究所 設立 1972年 3月 無機材質研究所が筑波研究学園都市に移転 1995年 7月 金属材料技術研究所が筑波研究学園都市に移転 2001年 4月 2研究所を統合し、独立行政法人物質・材料研究機構(NIMS)設立
第1期 中期計画開始2006年 4月 第2期 中期計画開始 2011年 4月 第3期 中期計画開始 2015年 4月 国立研究開発法人物質・材料研究機構(NIMS)に移行 2016年 4月 第4期 中長期計画開始 2016年 10月 特定国立研究開発法人物質・材料研究機構(NIMS)に移行 2023年 4月 第5期 中長期計画開始
 研究組織
研究組織-
① エネルギー・環境材料研究センター
再生可能エネルギーの利活用の最大化に向け、本センターが総力を挙げ取り組むのが電池材料と水素関連材料の基盤研究と開発です。電池材料は、現行のリチウムイオン電池を凌駕する先進リチウム電池や全固体電池、新原理の革新電池、太陽電池などの研究開発を推進します。また、次世代エネルギーのもう一つの柱である水素については、その安定利用を可能にする水素製造用の触媒材料や、水素の貯蔵・運搬性向上をねらったNIMS独自の液化技術「磁気冷凍システム」の構築などを目指しています。さらに、センター内にはJST委託事業を推進する「先進蓄電池研究開発拠点」を設置。革新電池の創出から社会実装までオールジャパンで達成すべく、産官学のハブとなり研究開発を牽引しています。
② 電子・光機能材料研究センター
社会発展の起爆剤となってきた電子材料と光学材料。持続的な発展のため、材料の革新が待ち望まれています。本センターでは、高電圧・高温・高速といったシビアな環境のもと動作する次世代通信用の半導体素子をはじめ、サイバー空間と実空間をつなぐ映像機器用の蛍光体、レーザー光源用単結晶の開発など、多岐に渡る材料開発により社会システムの変革に挑みます。同時に、社会の安心・安全を守るセンサ材料の感度や信頼性の向上と、資源循環を考慮した材料開発に取り組んでいます。そして、これら材料開発の過程で得られる知見をデータとして収集し、NIMSのデータプラットフォーム構築にも貢献していきます。
③ 磁性・スピントロニクス材料研究センター
持続可能社会の実現に、磁性材料やスピントロニクス素子は大きく貢献します。エネルギー関連ではモーターやハイブリッドカーに用いられる永久磁石材料が、電子情報分野では、磁気記録媒体や不揮発性磁気メモリ用の磁気抵抗材料・素子が代表例です。本センターでは、それらの飛躍的な性能向上や新規用途の開拓に向けて多彩な基盤研究を展開しています。近年の取り組みとして、磁気と熱、磁気と光に関するトピックに注力しています。その知見を礎に、重希土類フリー永久磁石や磁気冷凍材料などのいわゆるグリーン磁性材料のほか、次世代情報ストレージや磁気メモリ用の新規材料・素子の研究を推進し、実用化への道を切り拓いていきます。さらに、センター内には文科省委託事業を推進する「データ創出・活用型磁性材料研究拠点(DXMag)」を設置し、先駆的なデータ駆動型研究手法の開発を行っています。
④ 構造材料研究センター
構造材料は、社会インフラを支える極めて重要な基盤であり、その性能が10年単位の長期にわたって安定して発揮されることが求められます。本センターでは、インフラや輸送機器、エネルギー創製に関わる技術を対象に、材料の高性能化とそれを支える周辺技術を開拓しています。例えば、ビル・橋梁などを巨大地震から守る耐震材料、輸送機の軽量化に不可欠な高比強度材料、さらにはジェットエンジンの高効率化に必須な超耐熱材料の開発を推進しています。加えて、極低温環境下における材料の耐久性を高め、水素インフラの構築に貢献することを目指すほか、材料の特性評価・寿命予測技術の高度化により社会の安心・安全を守ります。
⑤ ナノアーキテクトニクス材料研究センター
ナノスケールのパーツを精密に合成・集積して新物質をつくり出し、先鋭的な新機能を持つ材料の実現を目指す「ナノアーキテクトニクス(ナノの建築学)」。WPI拠点*設立当初からかかげてきたこの理念の具現化に向け、引き続きボトムアップ型の基礎研究を推進しています。例えば、ナノ界面や欠陥の制御による新材料探索のほか、ナノ材料の次元制御による新物性の開拓、新原理の構築を進めています。さらに、量子技術のニーズが高まる中、新しい量子応用を可能にする物質の創製を目指し、重点プロジェクト「量子マテリアル」(右ページで紹介)にも注力。既成概念を打ち破る材料の創出に挑んでいます。*WPI拠点…文科省事業「世界トップレベル研究拠点プログラム」の推進拠点。2007年に設立されたMANAは10年のプログラムを満了し、現在はWPIアカデミーとなり国際研究拠点としての活動を継続中。
⑥ 高分子・バイオ材料研究センター
本センターでは、高分子材料の研究者とバイオ応用を見据えた研究者が一丸となり、素材革命をもたらすソフト・ポリマー材料と、ウェルビーイング*な社会を実現するバイオ材料の研究・開発を行っています。具体的には、有機材料の高度合成技術と、反応・構造の制御技術、物性評価技術を駆使し、高分子材料を生み出す上で基盤となる技術の確立を目指しています。また、NIMSが独自に培ってきた有機・無機・バイオ・ハイブリッド材料設計技術を強化していくことにより、生命・生体現象に呼応して機能を発現し次世代医療の足がかりとなる材料の創製に尽力していきます。*ウェルビーイング…人が肉体的、精神的、社会的、すべてにおいて満たされた状態(世界保健機構による定義)
⑦ マテリアル基盤研究センター
本センターは先端的な解析技術の専門家と、データ駆動による材料設計の専門家を結集した組織です。様々な物質・材料に共通する基礎基盤研究を担当し、研究開発スピードを大幅に加速させていきます。先端解析分野では、マルチスケール計測技術や、デバイス動作中の物質の挙動を捉えるオペランド計測技術など、物質・材料の本質にあらゆる角度から迫る解析技術を開発します。材料設計分野では、先端解析技術を取り入れたデータ駆動型手法の開発や、ハイスループットデータ収集技術の開発、種々のデータベースを連携させるための材料知識基盤の構築を行っていきます。
 中核的機関としての活動
中核的機関としての活動-
NIMSは、我が国全体のマテリアル研究開発力の強化を先導する中核的な役割を果たすための取り組みを進めています。
①マテリアル研究開発を先導する研究基盤の構築
・マテリアルDXプラットフォーム構築のためのデータ中核拠点の形成
・最先端のマテリアル研究を支える施設及び設備の共用
・マテリアル人材が集う国際的な拠点の形成
②アカデミアと産業界との架け橋となる多様な連携体制の構築及び研究成果の社会還元
③研究成果等の発信力強化とプレゼンスの向上、広報・アウトリーチ活動の推進