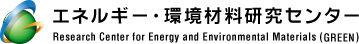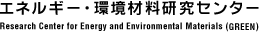電池材料分野
Koichi Hashimoto, Kei Kubota, Ryoichi Tatara, Tomooki Hosaka, Shinichi Komaba*, INORGANIC CHEMISTRY 63, 23317-23327 (2024). "Na5/6[Ni1/3Mn1/6Fe1/6Ti1/3]O2 as an Optimized O3-Type Layered Oxide Positive Electrode Material for Sodium-Ion Batteries"
DOI:10.1021/acs.inorgchem.4c04001
AI要約(翻訳):本研究では、ナトリウムイオン電池の正極材としてO3型層状酸化物Na5/6[Ni1/3Mn1/6Fe1/6Ti1/3]O2の構造および性能が詳しく研究された。この材料は特定の遷移金属層移動を抑制し、高い容量保持特性と電気化学的安定性を実現している。さらに、そのユニークな構造は電池の充放電サイクルにおいて優れた耐久性を示し、ナトリウムイオン電池の次世代技術として有望であることが示唆されている。この材料は効率と寿命のバランスがとれた設計を提供し、より広範囲な電池応用に展開可能である。
Randy Jalem*, Kazunori Takada, Hitoshi Onodera, Shuhei Yoshida, Journal of Materials Chemistry A 12, 33099-33113 (2024). "Crystal structure, stability and Li superionic conductivity of pyrochlore-type solid electrolyte Li2−xLa(1+x)/3Nb2O6F: a first-principles calculation study"
DOI:10.1039/d4ta04827j
AI要約(翻訳):ピロクロア型固体電解質Li2−xLa(1+x)/3Nb2O6Fに関する研究は、その結晶構造と高い安定性を詳しく解析することで、次世代エネルギーデバイスの可能性を示した。特に、Li+の超イオン導電性により高効率なエネルギー伝達が期待され、この電解質が高い室温導電率を持つことが計算で確認された。さらに、この材料は化学的および熱的安定性を有し、リチウム電池を含む多様な応用に適している。この成果は、固体電解質分野における画期的な進展を示している。
Palivela Siva Gangadhar, Silve Dasgupta, Prakriti R. Bangal*, Towhid H. Chowdhury, Ashraful Islam*, Lingamallu Giribabu*, ACS Applied Energy Materials 7, 3309-3320 (2024). "Influence of the Selenophene Auxiliary Acceptor in Porphyrin Sensitizers for High-Performance Dye-Sensitized Solar Cells"
DOI:10.1021/acsaem.4c00062
AI要約(翻訳):本研究は、ポルフィリン増感色素にセレノフェン補助受容体を導入することによって、エネルギー変換効率とデバイスの安定性を大幅に向上させた。この材料の設計は、分子内のエネルギー遷移を最適化し、太陽電池の光吸収特性と電子移動効率を強化している。試験結果では高い変換効率が確認され、このアプローチが次世代の効率的かつ持続可能な太陽光発電デバイスの設計に新たな展望を開く可能性があると示唆されている。
Md. Emrul Kayesh, Md. Abdul Karim, Yulu He, Yasuhiro Shirai, Masatoshi Yanagida, Ashraful Islam*, Small 20, 2402896-1-2402896-8 (2024). "Minimization of Energy Level Mismatch of PCBM and Surface Passivation for Highly Stable Sn-Based Perovskite Solar Cells by Doping n-Type Polymer"
DOI:10.1002/smll.202402896
AI要約(翻訳):本研究では、n型ポリマーのドーピングを通じて、スズ系ペロブスカイト太陽電池の性能が最適化された。このアプローチにより、電子輸送層とペロブスカイト界面間のエネルギーアライメントが強化され、効率的な電子移動と高い安定性を実現している。特に、変換効率が12.98%に達し、試験結果で優れた熱安定性と環境耐性も確認された。この成果は、次世代太陽電池技術の進歩に寄与する重要なステップとして注目されている。
Shoichi Matsuda*, Shin Kimura, Misato Takahashi, Batteries & Supercaps 7, e202400509-1-e202400509-8 (2024). "Automated Robotic Cell Fabrication Technology for Stacked-Type Lithium-Oxygen Batteries"
DOI:10.1002/batt.202400509
AI要約(翻訳):本研究では、積層型リチウム酸素電池の製造プロセスにおいて、完全自動化されたロボット製造技術が提案された。この技術はセル製造の精度と効率を同時に向上させるものであり、従来の生産手法と比較して10倍の効率性を達成している。この進展により、大規模かつ商業的な電池製造における課題が解消される可能性が高く、持続可能なエネルギーソリューションへの道を開く新たなアプローチとして注目される。
Hiroaki Kaneko, Yohei Cho, Tomotaka Sugimura, Ayako Hashimoto, Akira Yamaguchi, Masahiro Miyauchi*, CHEMICAL COMMUNICATIONS 60, 10406-10409 (2024). "Sustaining syngas production at a near-unity H2/CO ratio in the photo-induced dry reforming of methane independent of the reactant gas composition"
DOI:10.1039/d4cc03088e
AI要約(翻訳):この研究は、反応ガス組成に左右されずにH2/CO比がほぼ1:1の合成ガスを生成可能な、光誘起メタンのドライリフォーミングを扱っている。Rh触媒を担持したストロンチウムチタネートが用いられ、この反応が熱力学平衡に基づかず進行できることが示された。さらに光照射により副反応の抑制が達成され、合成ガスの生成効率が向上した。この成果は持続可能なガス変換技術の進展に寄与するものである。
Yasuhiro Domi*, Hiroyuki Usui, Takumi Okasaka, Kei Nishikawa, Hiroki Sakaguchi*, JOURNAL OF THE ELECTROCHEMICAL SOCIETY 171, 080506-1-080506-12 (2024). "Silicon-Based Nanocomposite Anodes with Excellent Cycle Life for Lithium-Ion Batteries Achieved by the Synergistic Effect of Two Silicides"
DOI:10.1149/1945-7111/ad69c6
AI要約(翻訳):シリコンベースのナノコンポジット負極材料に関するこの研究は、二種類のシリサイドの相乗効果によるサイクル寿命向上を示している。この材料はリチウムイオン電池に適応し、構造安定性と容量保持率の向上を可能にしている。結果として、エネルギー密度の向上と耐久性の両立が図られ、次世代エネルギーデバイスへの応用可能性が広がる重要な進展である。
Vishnuvardhan Reddy Chappidi, Sudhanshu Kumar Nayak, Md. Emrul Kayesh, Md. Abdul Karim, Yulu He, Ashraful Islam*, Sai Santosh Kumar Raavi*, Solar Energy 281, 112888-1-112888-9 (2024). "Elucidating the improved properties of defect engineered lanthanum-doped nickel oxide as hole-transport layer in triple-cation perovskite solar cells"
DOI:10.1016/j.solener.2024.112888
AI要約(翻訳):本研究では、三陽イオンペロブスカイト太陽電池の正孔輸送層として、欠陥工学を用いたランタンドープニッケル酸化物の特性向上が報告されている。ランタン添加による結晶構造の最適化により、電子移動効率と界面安定性の向上が確認された。この改良技術は、太陽電池の効率を強化し、持続可能な発電技術として有望であることを示唆している。
Dhruba B. Khadka*, Yasuhiro Shirai, Masatoshi Yanagida, Kenjiro Miyano, Conference Record of the IEEE Photovoltaic Specialists Conference 1, 0002-0004 (2024). "Effect of Charge-Modulated Molecular Passivator on Methylammonium/Bromine-Free Inverted Perovskite Solar Cells"
DOI:10.1109/PVSC57443.2024.10749333
AI要約(翻訳):本研究は、臭素を含まないメチルアンモニウム系逆型ペロブスカイト太陽電池において、電荷変調型分子パッシベータの導入がデバイス性能に与える影響を検討したものである。分子パッシベータは界面の欠陥を緩和し、電荷輸送の効率を向上させるとともに、構造的安定性を高める役割を果たすことが示された。その結果、太陽電池の変換効率と長期安定性が大幅に改善された。これにより、臭素フリー材料を用いた高性能ペロブスカイト太陽電池の実現に向けた新たな設計指針が提示された。
Md. Abdul Karim, Vishnuvardhan Reddy Chappidi, Md. Emrul Kayesh, Sai Santosh Kumar Raavi, Ashraful Islam*, Solar Energy 278, 112761-1-112761-7 (2024). "Crosslinker additive integration: A strategy to boost performance and stability in FASnI3 perovskite solar cells"
DOI:10.1016/j.solener.2024.112761
AI要約(翻訳):本研究では、FASnI3ペロブスカイト太陽電池の性能と安定性を向上させるために、クロスリンカー添加剤の統合手法が提案された。添加剤はエネルギーレベルのミスマッチを緩和し、界面の電荷輸送特性を改善することで、デバイスの長期安定性と変換効率を同時に高める効果を示した。さらに、構造的安定性の向上により、環境耐性の強化も確認された。この成果は、鉛フリー太陽電池の実用化に向けた重要な技術的進展であり、持続可能なエネルギー材料の設計に新たな指針を提供するものである。
Shamim Ahmmed, Yulu He, Md. Emrul Kayesh, Md. Abdul Karim, Kiyoto Matsuishi*, Ashraful Islam*, ACS Applied Materials & Interfaces 16, 32282-32290 (2024). "Ce-Doped SnO2 Electron Transport Layer for Minimizing Open Circuit Voltage Loss in Lead Perovskite Solar Cells"
DOI:10.1021/acsami.4c05180
AI要約(翻訳):本研究では、鉛系ペロブスカイト太陽電池における開回路電圧損失を低減するために、CeドープSnO2電子輸送層の導入が検討された。Ceのドーピングにより、電子輸送層のエネルギー準位が調整され、電荷抽出効率が向上した。これにより、デバイスの出力電圧と変換効率が改善され、同時に動作安定性も向上した。この手法は、高性能かつ安定なペロブスカイト太陽電池の実現に向けた有望な材料設計戦略であり、今後の太陽電池開発において重要な役割を果たすと考えられる。
Jun Nakanishi*, Takeshi Ueki, Sae Dieb, Hidenori Noguchi, Shota Yamamoto, Keitaro Sodeyama*, SCIENCE AND TECHNOLOGY OF ADVANCED MATERIALS 25, 2418287-1-2418287-11 (2024). "Data-driven optimization of the in silico design of ionic liquids as interfacial cell culture fluids"
DOI:10.1080/14686996.2024.2418287
AI要約(翻訳):本研究では、細胞培養用界面流体としてのイオン液体の設計に対し、データ駆動型の最適化手法が提案された。計算科学を用いた分子設計により、非毒性かつ高機能なイオン液体の候補が効率的に抽出され、幹細胞の培養および再利用に適した特性が得られた。さらに、従来の石油由来材料に代わる持続可能な代替手段としての可能性も示された。このアプローチは、バイオマテリアル分野における材料設計の革新を促進するものであり、環境負荷の低減と高性能化の両立を目指す研究に貢献する。
Mikio Ito, Hidenori Noguchi*, Kohei Uosaki*, JOURNAL OF CHEMICAL PHYSICS 161, 204703-1-204703-8 (2024). "Effect of Para Substituents on NC Bonding of Aryl Isocyanide Molecules Adsorbed on Metal Surfaces Studied by Sum Frequency Generation (SFG) Spectroscopy"
DOI:10.1063/5.0236548
AI要約(翻訳):本研究では、金属表面に吸着したアリールイソシアニド分子のNC結合に対するパラ置換基の影響を、和周波発生分光法(SFG)を用いて解析した。置換基の種類によって分子の電子分布や吸着構造が変化し、金属との相互作用に顕著な違いが生じることが明らかとなった。これにより、分子の化学的性質と表面反応性の関係が詳細に理解され、新たな触媒設計や表面機能化技術への応用可能性が示された。本成果は、分子表面科学の深化と材料開発の加速に寄与するものである。
Gen Hasegawa*, Youngseok Kim, Yoshinori Tanaka, Naoaki Kuwata*, Kunimitsu Kataoka, Takahisa Ohno, Junji Akimoto*, Kazunori Takada, ACS Applied Energy Materials 7, 10897-10905 (2024). "Improvement of lithium-ion conductivity by Hf substitution in lithium tantalum phosphate (LiTa2PO8) solid electrolyte"
DOI:10.1021/acsaem.4c01773
AI要約(翻訳):本研究では、リチウムタンタルリン酸塩(LiTa2PO8)におけるHf(ハフニウム)置換がリチウムイオン伝導性に与える影響を詳細に検討した。Hfを部分的に導入することで、結晶構造が変化し、イオンの拡散経路が広がることで伝導性が向上することが明らかとなった。特に室温付近でのイオン伝導性の改善が顕著であり、これは次世代の全固体電池における性能向上に寄与する可能性がある。また、材料の安定性や加工性にも優れており、実用化に向けた展望が広がる結果となった。
Emily C. Hayward*, Glen J. Smales, Brian R. Pauw, Masaki Takeguchi, Alexander Kulak, Robert D. Huntere, Zoe Schnepp, RSC Sustainability 2, 3490-3499 (2024). "The effect of catalyst precursors on the mechanism of iron-catalysed graphitization of cellulose"
DOI:10.1039/D4SU00365A
AI要約(翻訳):本研究では、鉄触媒を用いたセルロースのグラファイト化において、触媒前駆体の種類が反応機構および生成される炭素材料の構造に与える影響を系統的に調査した。鉄(III)硝酸塩や塩化鉄など異なる前駆体を用いることで、生成物の結晶性や多孔性が大きく変化することが示された。これにより、触媒の選択が炭素材料の機能性を制御する鍵となることが明らかとなり、持続可能な炭素材料の設計において重要な知見が得られた。環境負荷の少ないプロセス開発にも貢献する成果である。
Rui Sun, Man Wang, Tianjiao Zeng, Huajian Chen, Toru Yoshitomi, Masaki Takeguchi, Naoki Kawazoe, Yingnan Yang, Guoping Chen*, Bioactive Materials 44, 205-219 (2024). "Scaffolds functionalized with matrix metalloproteinase-responsive release of miRNA for synergistic magnetic hyperthermia and sensitizing chemotherapy of drug-tolerant breast cancer"
DOI:10.1016/j.bioactmat.2024.10.011
AI要約(翻訳):本研究では、薬剤耐性乳がんに対する治療効果を高めるため、マトリックスメタロプロテアーゼ(MMP)応答性miRNA放出機能を持つ足場材料が開発された。足場には磁性ナノ粒子が組み込まれており、外部磁場によって局所的な温熱効果を誘導し、がん細胞の感受性を高める。さらに、MMPの活性に応じてmiRNAが放出され、薬剤耐性や細胞増殖に関与する遺伝子の発現を抑制する。in vitroおよびin vivoの実験により、足場の治療効果と安全性が確認され、薬剤耐性乳がんに対する新たな治療戦略として期待される。
Tetsuro Morooka, Tamao Shishido, Ruttala Devivaraprasad, Ganesan Elumalai, Makoto Aoki, Tetsuroh Shirasawa, Takuya Nakanishi, Atsushi Ishikawa, Toshihiro Kondo, Takuya Masuda*, Journal of Physical Chemistry C 128, 16426-16436 (2024). "Potential-Dependent and Face Orientation-Dependent Electrochemical Oxidative Desorption Behavior of Sulfur Species Adsorbed on Platinum Single-Crystal Surfaces"
DOI:10.1021/acs.jpcc.4c03227
AI要約(翻訳):本研究は、白金単結晶表面に吸着された硫黄種の酸化脱離挙動が、電位と結晶面の向きに依存することを示した。Pt(111)、Pt(110)、Pt(100)面では、硫黄吸着により水素や水酸化物の反応が抑制され、S2pピークがX線光電子分光法で確認された。電位を上げることでピークが減少し、電気化学的活性表面積(ECSA)が回復した。Pt(111)面では最も低い電位で脱離が始まり、SO2の吸着エネルギーの違いが影響していることが理論計算で示された。これらの知見は、燃料電池触媒の性能維持に役立つ可能性がある。
Go Kamesui, Kei Nishikawa, Mikito Ueda, Hisayoshi Matsushima*, JOURNAL OF THE ELECTROCHEMICAL SOCIETY 171, 100507-1-100507-7 (2024). "Correlation between Electrolyte Concentration and Lithium Morphology during Lithium Bis(fluorosulfonyl)amide–Tetraglyme Electrolyte Deposition–Dissolution Reactions"
DOI:10.1149/1945-7111/ad803d
AI要約(翻訳):本研究では、LiFSI–テトラグライム系電解液におけるリチウムの析出・溶解反応において、電解液濃度がリチウム形態に与える影響を詳細に検討した。繊維状リチウムの成長挙動は、溶質・溶媒モル比に強く依存し、低モル比ではサイクル数の増加に伴い厚さが増加し、高モル比では逆に減少する傾向が観察された。デジタル顕微鏡による観察に加え、レーザー干渉顕微鏡を用いて電極近傍の濃度分布と拡散層の挙動を可視化した結果、異なるモル比に応じて3種類の繊維状成長モデルが存在することが示唆された。これらのモデルは、電解液設計における指針となり、リチウム金属電池の性能向上に貢献する可能性がある。さらに、電解液の濃度制御がリチウムの形態安定性や反応効率に与える影響を理解する上で重要な知見を提供している。
Ryo Tamura*, Ryuichi Inaba, Mami Watanabe, Yutaro Mori, Makoto Urushihara, Kenji Yamaguchi*, Shoichi Matsuda*, Science and Technology of Advanced Materials: Methods 4, 2416889-1-2416889-8 (2024). "Predicting the surface roughness of an electrodeposited copper film using a machine learning technique"
DOI:10.1080/27660400.2024.2416889
AI要約(翻訳):本研究では、電解めっきによって形成される銅膜の表面粗さを機械学習技術により高精度に予測する手法を提案した。実験から得られた複数のプロセスパラメータを特徴量として用い、学習モデルを構築することで、表面形状の定量的予測が可能となった。電流密度、膜厚、電解時間などの条件が予測精度に与える影響を分析し、モデルの汎化性能を評価した。予測結果は実測値と良好に一致し、製造工程の最適化や品質管理に有用であることが示された。さらに、本手法は材料設計におけるデータ駆動型アプローチの有効性を示すものであり、従来の経験則に依存しない精密な制御が可能となる。今後は他の金属や複合材料への応用も期待され、表面特性の予測と制御に関する新たな展開が見込まれる。
Yushen Wang, Hidenori Noguchi*, PHYSICAL CHEMISTRY CHEMICAL PHYSICS 26, 25352-25362 (2024). "Revealing the Enhancement of Li Plating/Stripping Efficiency in the TEGDME-based Low-concentration Electrolytes for Anode-free Lithium Metal Batteries"
DOI:10.1039/D4CP02755H
AI要約(翻訳):本研究では、アノードフリー型リチウム金属電池(AFLMB)におけるLiの析出・剥離効率を向上させるため、TEGDMEベースの低濃度電解液の効果を詳細に検討した。LiNO3添加により、Li2Oを主成分とするSEI層の安定性が向上し、酸化反応の抑制によって効率的なLiの挙動が得られた。特に2.0 M濃度の電解液では、SEIの主成分がLiFへと変化し、クーロン効率がさらに改善された。電位領域の制御によりOSS(酸化SEI形成)を抑制し、長寿命かつ高効率な電池動作が可能となった。これらの成果は、電解液設計による性能向上の可能性を示すものであり、高エネルギー密度を持つAFLMBの実用化に向けた重要な知見である。今後の研究では、さらなる電解液の最適化とSEI構造の理解が求められる。
K. Mitsuishi*, T. Ohnishi, K. Niitsu, T. Masuda, S. Miyoshi, K. Takada, SOLID STATE IONICS 417, 116717-1-116717-6 (2024). "Lowering the sintering temperature of LiCoO2 using LiOH aqueous solution"
DOI:10.1016/j.ssi.2024.116717
AI要約(翻訳):本研究では、LiCoO2の焼結温度を低下させるためにLiOH水溶液を用いる新たな手法を提案している。従来の高温焼結では構造や性能に影響があったが、本手法では低温でも結晶構造を保持し、優れた導電性と安定性を実現した。焼結温度を800℃から600℃に下げることが可能で、製造時のエネルギー消費を削減できる。また、LiOH水溶液の濃度や処理時間が粒子成長や密度に与える影響も検討され、最適条件下で得られた材料は正極として高性能を示した。この成果は、電池製造の低コスト化と環境負荷の軽減に貢献し、持続可能なエネルギー技術の発展に寄与する可能性がある。
Seong-Hoon Jang*, Randy Jalem, Yoshitaka Tateyama, Journal of Materials Chemistry A 12, 20879-20886 (2024). "Computational discovery of stable Na-ion sulfide solid electrolytes with high conductivity at room temperature"
DOI:10.1039/D4TA02522A
AI要約(翻訳):本研究では、室温で高いイオン伝導性を持つ安定なNaイオン硫化物系固体電解質を探索するため、密度汎関数理論(DFT)と分子動力学(MD)を組み合わせた計算手法を用いた。DFT-MDサンプリングにより、Ga–P–Na4SiS4やSi–Ta–Na4SiS4系で、σNa,300K ≧ 10−3 S/cmの伝導性を持つ熱的に安定な化合物を特定した。これらは実験的合成が可能と予測され、全固体電池の性能向上に貢献する可能性がある。提案手法は他の電解質材料にも応用でき、材料探索の効率化に寄与すると期待される。Na資源の豊富さと機械的特性の利点を活かし、持続可能なエネルギー技術の発展に向けた有望な成果である。
Kiho Nishioka, Mizuki Tanaka, Terumi Goto, Ronja Haas, Anja Henss, Shota Azuma, Morihiro Saito, Shoichi Matsuda, Wei Yu, Hirotomo Nishihara, Hayato Fujimoto, Mamoru Tobisu, Yoshiharu Mukouyama, Shuji Nakanishi*, ACS Applied Materials & Interfaces 16, 46259-46269 (2024). "Fluorinated Amide-Based Electrolytes Induce a Sustained Low-Charging Voltage Plateau under Conditions Verifying the Feasibility of Achieving 500 Wh kg–1 Class Li–O2 Batteries"
DOI:10.1021/acsami.4c08067
AI要約(翻訳):本研究では、Li–O2二次電池において500 Wh/kg級の高エネルギー密度を実現するため、フッ化アミドベースの新規電解液を開発した。この電解液は約3.5 Vの低充電電圧プラトーを維持し、充電時のエネルギー損失を低減する。放電生成物のリチウム過酸化物は、フッ素含有溶媒により分解しやすく、充電効率を高める。放射光X線回折により、生成物がアモルファスかつリチウム欠損型であることが確認された。これらの成果は、分子設計による電池性能の改善可能性を示し、高性能Li–O2電池の実用化に向けた有力な知見を提供する。
Qianli Si, Shoichi Matsuda, Youhei Yamaji, Toshiyuki Momma, Yoshitaka Tateyama*, Advanced Science 11, 2402608-2402608 (2024). "Data-Driven Cycle Life Prediction of Lithium Metal-Based Rechargeable Battery Based on Discharge/Charge Capacity and Relaxation Features"
DOI:10.1002/advs.202402608
AI要約(翻訳):本研究では、リチウム金属二次電池の寿命予測を目的に、充放電容量と緩和特性に基づく機械学習モデルを構築した。劣化機構に依存せず、放電・充電・緩和プロセスから抽出した特徴量を用いて高精度な予測を実現した。最適化されたモデルはR2値0.89を達成し、未知データに対しても6.6%の誤差で予測可能だった。特徴量分析では、100サイクルと10サイクル間の放電容量差の最小値の対数が最も有効な指標と判明した。この手法は電池管理の効率化や寿命延長に貢献し、高エネルギー密度電池の実用化に向けた有力な技術といえる。
Yimeng Wu, Jie Tang*, Shuai Tang, You-Hu Chen, Ta-Wei Chiu, Masaki Takeguchi, Lu-Chang Qin*, Nanomaterials 14, 1567-1-1567-11 (2024). "Stable Field Emission from Single Crystalline Zirconium Carbide Nanowires"
DOI:10.3390/nano14191567
AI要約(翻訳):本研究では、化学気相成長法により合成された単結晶ジルコニウムカーバイド(ZrC)ナノワイヤの電界放出特性を評価した。ZrCl4とCH4を用いて<100>配向のZrCナノワイヤをグラファイト基板上に形成し、直径100 nm未満、長さ10 µm以上の構造が得られた。単一ナノワイヤをタングステンチップに固定し、表面処理後に電界放出測定を行った結果、440 Vの低ターンオン電圧で1.1×1010 A/m2の高電流密度を達成し、150分間にわたり1.77%の変動で安定した放出が確認された。本成果は、ZrCナノワイヤを電子ビーム源として安定化させる有効な手法を示しており、電子顕微鏡やマイクロ電子デバイスへの応用に向けた基盤技術として期待される。
Yuki Nakagawa*, Yasuhiro Shiratsuchi, Tamaki Shibayama, Masaki Takeguchi*,, Nanomaterials 14, 1486-1-1486-9 (2024). "Ultraviolet Light-Induced Surface Changes of Tungsten Oxide in Air: Combined Scanning Transmission Electron Microscopy and X-ray Photoelectron Spectroscopy Analysis"
DOI:10.3390/nano14181486
AI要約(翻訳):本研究では、酸化タングステン(WO3)に紫外線を照射した際の表面変化を、走査透過型電子顕微鏡(STEM)とX線光電子分光法(XPS)を組み合わせて解析した。IL-STEMにより、照射後の粒子表面にアモルファスな薄膜が形成されることが確認され、XPSでは炭化水素の分解とカルボキシル・ヒドロキシル基の生成が観察された。これらの結果から、形成された薄膜は光触媒的酸化種である可能性が示唆される。本手法は、光誘起現象の微細構造解析に有効であり、光触媒や親水性変換材料の評価に役立つ。酸化物材料の表面反応理解を深めるうえで、本研究は新たな視点を提供するものである。
Naoto Ogiwara, Takenobu Nakano, Koki Baba, Hidenori Noguchi, Tsukuru Masuda, Madoka Takai*, ACS Applied Materials & Interfaces 16, 44575-44589 (2024). "High-Quality Three-Dimensionally Cultured Cells Using Interfaces of Diblock Copolymers Containing Different Ratios of Zwitterionic N‑Oxides"
DOI:10.1021/acsami.4c10118
AI要約(翻訳):本研究では、双性イオン性N-オキシドを異なる比率で含む二重ブロック共重合体の界面を用いて、三次元培養細胞の形成と機能を制御した。共重合体は親水性と疎水性のバランスを持ち、表面のタンパク質吸着量や帯電特性が比率に応じて変化する。ヒト臍帯由来間葉系幹細胞を用いた実験では、N-オキシド比率が40%以上で球状構造が形成され、20%未満では平面増殖が優勢となった。50〜70%の比率では、未分化マーカーの発現が高く、均一なスフェロイドが得られた。これらの結果は、細胞培養表面の設計によって高品質な三次元細胞モデルを構築できる可能性を示しており、再生医療や創薬スクリーニングへの応用が期待される。
Kunie Ishioka*, Oleg V. Misochko, PHYSICAL REVIEW B 110, 094313-1-094313-10 (2024). "Suppression of shear ionic motions in bismuth by coupling with large-amplitude internal displacement"
DOI:10.1103/PhysRevB.110.094313
AI要約(翻訳):本研究では、ビスマス単結晶における剪断イオン運動(Egモード)が、内部変位(A1gモード)との強い結合によって抑制される現象を、異方性反射率測定を用いて解析した。11 Kでの光励起下において、Egモードの振幅はポンプ光強度に応じて増加した後、急激に減少する挙動を示し、A1gモードとは対照的な振る舞いを見せた。この差異は、励起状態での振動ポテンシャルの動的変動によるEgモードのコヒーレンス喪失に起因すると考えられる。従来の薄膜研究とは異なり、高対称相への転移は観測されず、表面の損傷が確認された。本研究は、非平衡状態におけるフォノン間および電子-フォノン結合の理解を深めるものであり、光による構造制御の可能性を示唆している。
Omar Falyouna*, Mohd Faizul Idham, Osama Eljamal, Toshihiko Mandai*, Batteries & Supercaps 7, e202400231-1-e202400231-13 (2024). "Compatibility of Molybdenum Disulfide and Magnesium Fluorinated Alkoxyaluminate Electrolytes in Rechargeable Mg Batteries"
DOI:10.1002/batt.202400231
AI要約(翻訳):本研究では、充電式マグネシウム電池における二硫化モリブデン(MoS2)とフルオロアルコキシアルミネート系電解液(Mg-FAl)の相互適合性を評価した。MoS2は高い電気化学的安定性と層状構造を持ち、Mg-FAl電解液との組み合わせにより、優れた充放電特性が得られる可能性がある。実験では、MoS2電極の表面状態や界面反応を詳細に解析し、Mgイオンの可逆的挿入・脱離が確認された。さらに、電解液の分解生成物がMoS2表面に与える影響や、界面抵抗の変化についても検討された。これらの結果は、Mg電池の高性能化に向けた材料設計に重要な知見を提供し、次世代二次電池の開発に貢献するものである。
Ryuto Eguchi*, Yu Wen, Hideki Abe, Ayako Hashimoto*, Nanomaterials 14, 1413-1-1413-12 (2024). "Interpretable Structural Evaluation of Metal-Oxide Nanostructures in Scanning Transmission Electron Microscopy (STEM) Images via Persistent Homology"
DOI:10.3390/nano14171413
AI要約(翻訳):本研究では、パーシステントホモロジーを用いて、STEM画像から金属酸化物ナノ構造の解釈可能な幾何学的特徴を抽出した。Pt-CeO2ナノ構造を対象に、ゼロ次および一次ホモロジー群から5つの特徴量を導出し、構造の乱れや屈曲密度を定量化した。主成分分析と階層的クラスタリングを組み合わせることで、CeO2相の幅やアーク状構造の数が構造分類に有効であることが示された。この手法により、従来の幾何学的指標では捉えにくい構造の違いを明確にし、材料設計における構造-機能相関の理解を深めることが可能となった。トポロジー解析を応用した新しい構造評価法として、広範な材料科学分野への展開が期待される。
Kiyoshi Kobayashi*, Shogo Miyoshi, Tohru S. Suzuki, MATERIALS TRANSACTIONS 65, 1397-1401 (2024). "Production of Solidified Body from a Melt and Its Electrical Conductivity of CsSnBr3 Using Precursor Prepared by Mechanochemical Reaction Process"
DOI:10.2320/matertrans.MT-Y2024005
AI要約(翻訳):本研究では、メカノケミカル反応で合成した前駆体を用いてCsSnBr₃の溶融凝固体を作製し、その電気伝導特性を評価した。X線回折により主相はCsSnBr₃であることが確認され、少量の不純物も検出された。初回加熱時には金属的な伝導挙動が見られたが、冷却時には半導体的性質へと変化し、再加熱後にはこの挙動が可逆的であることが示された。これらの結果は、製造工程やアニール処理がCsSnBr₃の電気特性制御に重要であることを示唆しており、太陽電池や熱電変換材料への応用に向けた基盤技術として期待される。
Eun Jeong Kim, Ryoichi Tatara, Tomooki Hosaka, Kei Kubota, Shinichi Kumakura, Shinichi Komaba*, ACS Applied Energy Materials 7, 1015-1026 (2024). "Effects of Particle Size and Polytype on the Redox Reversibility of the Layered Na0.76Ni0.38Mn0.62O2 Electrode"
DOI:10.1021/acsaem.3c02462
AI要約(翻訳):本研究では、Na₀.₇₆Ni₀.₃₈Mn₀.₆₂O₂電極の酸化還元可逆性に対する粒径と多型の影響を調査した。P3型とP2型の試料を異なる粒径で合成し、電気化学的性能を比較した結果、小粒径かつ不純物の少ないP3型は優れたサイクル性能とレート性能を示した。二次粒子が大きいほど両型において性能が向上し、微細亀裂の形成や抵抗増加、CO₂放出などの劣化要因も粒径に依存することが明らかとなった。さらに、粒子構造の均一性や界面安定性が電極反応に与える影響も示唆され、ナトリウムイオン電池の長寿命化と高出力化に向けた材料設計の重要性が強調された。
Rui Sun, Huajian Chen, Man Wang, Toru Yoshitomi, Masaki Takeguchi, Naoki Kawazoe, Yingnan Yang, Guoping Chen*, BIOMATERIALS 307, 122511-1-122511-14 (2024). "Smart composite scaffold to synchronize magnetic hyperthermia and chemotherapy for efficient breast cancer therapy"
DOI:10.1016/j.biomaterials.2024.122511
AI要約(翻訳):本研究では、磁性Fe₃O₄ナノ粒子と抗がん剤ドキソルビシンを含む熱応答性リポソームを組み合わせたスマート複合足場を開発し、磁気温熱療法と化学療法の同期的実施を可能にした。交流磁場の照射により局所温度が上昇し、薬剤が効率的に放出されることで、がん細胞の除去効果が高まった。さらに、足場は脂肪幹細胞の増殖と分化を促進し、治療後の組織再建にも寄与することが確認された。この足場は、治療と再生を同時に実現する多機能性を備えており、乳がん治療の新たなプラットフォームとして高い応用可能性を示している。
Shota Azuma, Itsuki Moro, Mitsuki Sano, Fumisato Ozawa, Morihiro Saito*, Akihiro Nomura*, JOURNAL OF THE ELECTROCHEMICAL SOCIETY 171, 100511-1-100511-8 (2024). "Mechanistic Analysis of Lithium-Air Battery with Organic Redox Mediator-Coated Air-Electrode"
DOI:10.1149/1945-7111/ad7f92
AI要約(翻訳):本研究では、有機レドックスメディエーター(ORM)を被覆した空気電極を用いたリチウム空気電池の反応機構を解析した。放電時にはLi2O2が生成され、充電時にはORMが酸化されてLi2O2の分解を促進することが明らかとなった。電極表面の構造変化や反応生成物の分布をX線回折と分光分析で評価し、ORMの存在が電極反応の均一性と可逆性を向上させることが確認された。また、充放電サイクルにおける電位変化と過電圧の低減効果も示され、エネルギー効率の改善に寄与することが示唆された。これらの知見は、リチウム空気電池の高性能化と長寿命化に向けた電極設計の指針となるものである。
Yiyi Zheng, Tian Zhang, Pui-Kit Lee, Qiaohui Duan, Xin Li, Shuyu Dong, Tian Tan, Yao Wang, Denis Y.W. Yu*, ELECTROCHIMICA ACTA 500, 144718-1-144718-9 (2024). "Boosting Li-ion transport for graphite electrodes with lithium bis(fluorosulfonyl)imide salt and methyl acetate additive for fast-charging Li-ion batteries"
DOI:10.1016/j.electacta.2024.144718
AI要約(翻訳):本研究では、グラファイト電極におけるリチウムイオン輸送を促進するため、LiFSI塩とメチルアセテート(MA)添加剤を組み合わせた電解液の効果を検討した。LiFSIは高いイオン伝導性を持ち、MAは溶媒和構造を調整することでSEI形成を最適化し、界面抵抗を低減する。実験では、充電速度の向上と容量保持率の改善が確認され、特に高電流密度下での性能向上が顕著であった。XPSやSEM分析により、安定なSEI層の形成と電極表面の保護効果が示された。これらの結果は、高速充電対応型リチウムイオン電池の電解液設計において有効な戦略を提供するものであり、実用化に向けた重要な知見となる。
Qiaohui Duan, Yiyi Zheng, Yu Zhou, Shuyu Dong, Calvin Ku, Patrick H.-L. Sit, Denis Y. W. Yu*, Small 20, 2404368-1-2404368-13 (2024). "Suppressing Formation of Zn-Mn-O Phases by In-situ Ti Decoration of MnO2 for Long Lifespan MnO2-Zn Battery"
DOI:10.1002/smll.202404368
AI要約(翻訳):本研究では、MnO2-Zn電池の長寿命化を目的として、MnO2電極にTiをその場装飾することでZn-Mn-O相の形成を抑制する手法を提案した。TiOSO4を電解液添加剤として導入することで、充放電サイクル中のMnO2の構造変化が抑制され、ZnMn2O4やZnMn3O7などの副生成物の形成が減少した。電極のXRD解析や電気化学測定により、Ti添加により高い容量保持率と優れたサイクル安定性が得られることが示された。特に、10,000サイクル後でも75%の容量を維持する性能が確認され、大規模エネルギー貯蔵用途への応用可能性が示唆された。
Masaki Takeguchi*, Kazutaka Mitsuishi, Ayako Hashimoto, Applied Physics Express 17, 085001-1-085001-4 (2024). "Facile preparation of graphene-graphene oxide liquid cells and their application in liquid-phase STEM imaging of Pt atoms"
DOI:10.35848/1882-0786/ad63f2
AI要約(翻訳):本研究では、グラフェンと酸化グラフェンを用いた液体セルの簡便な作製法を開発し、液相走査透過型電子顕微鏡(STEM)による白金原子の観察に応用した。セル構造は高い安定性と透過性を持ち、液中での原子レベルの観察を可能にする。特に、Pt原子の動的挙動をリアルタイムで捉えることができ、触媒反応やナノ材料の界面解析に有用であることが示された。この手法は、液相環境下での高分解能観察技術の発展に貢献し、材料科学や電池研究など幅広い分野への応用が期待される。
Robert D. Hunter, Masaki Takeguchi, Ayako Hashimoto, Kannan M. Ridings, Shaun C. Hendy, Dmitri Zakharov, Nils Warnken, Jack Isaacs, Sol Fernandez-Muñoz, Joaquín Ramirez-Rico*, Zoe Schnepp*, ADVANCED MATERIALS 36, 2404170-1-2404170-10 (2024). "Elucidating the mechanism of iron-catalyzed graphitization: the first observation of homogeneous solid-state catalysis"
DOI:10.1002/adma.202404170
AI要約(翻訳):本研究では、鉄触媒によるグラファイト化の反応機構を解明し、均質な固体状態での触媒作用が初めて観察された。暗視野の原位透過型電子顕微鏡により、結晶性鉄ナノ粒子が非晶質炭素を貫通し、多層グラファイトナノチューブを形成する様子が確認された。さらに、原位シンクロトロンX線回折により、グラファイト化が数分以内に完了することが示された。この均質固体触媒機構は、従来の表面反応とは異なり、触媒粒子全体が反応に関与する新しい概念を提示しており、持続可能な炭素材料の設計に新たな視点を提供する。
Keisuke Yoshikawa, Takeshi Kato, Yasuhiro Suzuki, Akihiro Shiota, Tsuyoshi Ohnishi, Koji Amezawa, Aiko Nakao, Takeshi Yajima, Yasutoshi Iriyama*, Advanced Science 11, 2402528-1-2402528-7 (2024). "Origin of O2 Generation in Sulfide-Based All-Solid-State Batteries and its Impact on High Energy Density"
DOI:10.1002/advs.202402528
AI要約(翻訳):本研究では、硫化物系全固体電池(SB)における酸素(O2)発生の起源とその高エネルギー密度への影響を調査した。高電圧充電時にLiNbO3被膜からのLi抽出によりO2が発生し、周囲の固体電解質が酸化されて性能劣化を引き起こすことが明らかとなった。一方で、NbをPで部分置換した被膜(LiNbxP1-xO3)ではO2発生が抑制され、安定な充放電反応が維持された。これらの知見は、SBの高電圧動作と高エネルギー密度化に向けた被膜材料設計の重要性を示している。
Tsuyoshi Ohnishi, Isao Sakaguchi, Kazunori Takada*, ACS Applied Energy Materials 7, 5321-5325 (2024). "Surface Treatment of Garnet-Type Solid Electrolyte for Suppressing Dendritic Growth"
DOI:10.1021/acsaem.4c00805
AI要約(翻訳):本研究では、ガーネット型固体電解質Li6.6La3Zr1.6Ta0.4O12に対し、研磨・高温アニール・LiOH処理を施すことで、表面汚染層を除去し、電極界面の均一性と導電性を向上させた。これにより臨界電流密度が上昇し、デンドライトによる短絡が抑制された。電気化学インピーダンスとクロノポテンショメトリーで処理の効果を確認し、未処理試料との比較で明確な改善が示された。この簡便な表面処理は、酸化物系全固体電池の安全性向上に貢献する技術として期待される。
Ravindra Kumar Gupta, Hidehiko Asanuma, Juan J Giner-Casares, Ayako Hashimoto, Tetsuya Ogawa, Takashi Nakanishi*, NANOTECHNOLOGY 35, 335603-1-335603-11 (2024). "A compound eye-like morphology formed through hexagonal array of hemispherical microparticles where an alkyl-fullerene derivative self-assembled at atmosphere-sealed air/water interface"
DOI:10.1088/1361-6528/ad4bef
AI要約(翻訳):本研究では、アルキルフラーレン誘導体が空気/水界面で自己組織化し、六方配列の半球状微粒子による複眼状構造を形成した。密閉された界面環境により、粒子の均一性と配列精度が向上し、光学的に安定な構造が得られた。この構造は、光の散乱・吸収特性に優れ、光センサーやディスプレイ材料への応用が期待される。また、粒子サイズや配列密度の制御が可能で、機能性材料の設計に柔軟性をもたらす。自己組織化のメカニズム解明も進み、界面化学とナノ構造形成の融合による新たな材料開発の可能性が示された。
Kaiming Xue, Huimin Wang, Denis Y. W. Yu*, ChemElectroChem 11, e202300661-1-e202300661-15 (2024). "Emerging battery systems with metal as active cathode material"
DOI:10.1002/celc.202300661
AI要約(翻訳):この総説では、金属を活物質とする新型電池システムについて、Cu、Fe、Snなどの金属が持つ電気化学的特性と応用可能性を詳しく解説している。これらの金属は、可逆的な酸化還元反応を通じてエネルギーを蓄積・放出でき、資源の豊富さや低コスト性が利点となる。電解液の種類(有機、無機、混合、溶融塩)によって性能が変化し、用途に応じた最適設計が可能。さらに、反応機構や電位差に基づく出力電圧の理論的検討も行われ、実用化に向けた課題と展望が整理されている。持続可能なエネルギー技術としての可能性が高く、今後の研究開発に向けた重要な指針を提供している。
Yu Zhao, Hekang Zhu, Lidan Xing, Denis Y.W. Yu*, Chemical Engineering Journal 493, 152602-1-152602-11 (2024). "Electrolyte design for high power dual-ion battery with graphite cathode for low temperature applications"
DOI:10.1016/j.cej.2024.152602
AI要約(翻訳):本研究では、低温環境下でも高出力を維持できるグラファイト正極を用いたデュアルイオン電池向けの電解液設計を行った。LiFSI塩とメチルアセテート(MA)添加剤を組み合わせることで、電解液の粘度低下とイオン移動度の向上を実現し、−20℃でも高い容量と安定性を達成した。電解液の溶媒和構造やSEI形成挙動を分光分析と電気化学測定で評価し、MAの添加が界面抵抗を低減し、充放電効率を向上させることが確認された。これらの成果は、寒冷地や航空宇宙用途における高性能電池の開発に貢献するものであり、低温対応型電解液設計の新たな指針を示している。
Takahisa Ohno*, Nobuo Tajima, Jun Nara, JAPANESE JOURNAL OF APPLIED PHYSICS 63, 051004-1-051004-6 (2024). "First-principles investigation on potential profile induced in graphene by surface and edge metal contacts"
DOI:10.35848/1347-4065/ad3ed2
AI要約(翻訳):本研究では、グラフェンに金属接触が与える電位分布の変化を第一原理計算により解析した。表面接触と端部接触の違いによって、グラフェン内部に誘導される電位勾配が異なることが示され、特に端部接触では局所的な電位変化が顕著であることが明らかとなった。これらの電位分布は、キャリア輸送特性やデバイス性能に直接影響を与える可能性があり、ナノスケール電子デバイス設計において重要な要素となる。本研究は、グラフェンの電気的特性を精密に制御するための理論的基盤を提供し、金属接触構造の最適化に向けた新たな知見を示している。
Katsunori Tagami*, Takahisa Ohno, Jun Nara, Mamoru Usami, JAPANESE JOURNAL OF APPLIED PHYSICS 63, 023001-1-023001-6 (2024). "Magnetic structures and magnetic anisotropy of Mn3−xFexSn studied by first-principles calculations"
DOI:10.35848/1347-4065/ad2303
AI要約(翻訳):本研究では、Mn3−xFexSn合金の磁気構造と磁気異方性について第一原理計算を用いて解析した。Fe濃度の変化により、反強磁性からフェリ磁性への転移が起こり、磁気モーメントの方向性や大きさが系統的に変化することが示された。特に、x=1.0付近で異方性エネルギーが最大となり、スピン構造の安定性に大きな影響を与えることが明らかとなった。これらの知見は、スピントロニクス材料としてのMn3−xFexSnの設計に有用であり、磁気特性の精密制御に向けた理論的指針を提供するものである。
Fumihiko Uesugi*, Yu Wen, Ayako Hashimoto, Masashi Ishii, MICRON 183, 103664-1-103664-7 (2024). "Prediction of nanocomposite properties and process optimization using persistent homology and machine learning"
DOI:10.1016/j.micron.2024.103664
AI要約(翻訳):本研究では、ナノコンポジット材料の特性予測とプロセス最適化に、持続的ホモロジー(persistent homology)と機械学習を組み合わせた新手法を提案している。微細構造のトポロジー情報を抽出し、機械学習モデルに組み込むことで、材料の力学特性や加工条件との関係を高精度に予測可能とした。特に、電子顕微鏡画像から得られる構造情報を数理的に処理することで、従来の統計手法では捉えきれなかった微細構造の影響を定量化できる点が特徴である。さらに、得られたモデルを用いて加工条件の最適化を行い、実験的にも高性能なナノコンポジットの製造に成功した。このアプローチは、材料設計の効率化と高性能化に貢献するものであり、今後のマテリアルズ・インフォマティクス分野における応用が期待される。
Arghya Dutta*, Emiko Mizuki, YukaTomori, Shoichi Matsuda*, ACS Applied Energy Materials 7, 3824-3830 (2024). "Optimizing Discharge Rate for Li Metal Stability in Rechargeable Li|NMC Batteries under Lean Electrolyte Condition"
DOI:10.1021/acsaem.4c00180
AI要約(翻訳):本研究では、リチウム金属電池(LMB)の安定性向上を目的に、放電レートの最適化が電極劣化に与える影響を検討した。Lean電解液条件下でLi|NMC811セルを用い、0.4〜1.6 mA/cm²の放電電流密度がサイクル寿命に与える効果を評価。結果として、1.6 mA/cm²までの放電レート増加は、Li金属の体積膨張を抑制し、サイクル寿命を延ばすことが判明した。一方、1.6 mA/cm²を超えると、NMC電極の反応速度制限により性能が低下する。この知見は、高出力かつ長寿命なLMB設計において、放電条件の制御が重要であることを示しており、次世代電池の実用化に向けた指針となる。
Yanan Gao, Hitoshi Asahina, Shoichi Matsuda, Hidenori Noguchi, Kohei Uosaki*, PHYSICAL CHEMISTRY CHEMICAL PHYSICS 26, 13655-13666 (2024). "Nature of Li2O2 and its relationship to the mechanisms of discharge/charge reactions of lithium–oxygen batteries"
DOI:10.1039/D4CP00428K
AI要約(翻訳):本研究では、リチウム酸素電池(LOB)の充放電反応におけるLi2O2の性質とその分解挙動を解明するため、オンライン質量分析を用いてリアルタイムで生成ガスを観測した。充電時に生成されるLi2O2には、低電圧で分解するl-Li2O2と、高電圧で分解するh-Li2O2の2種類が存在することが判明。O2生成のピーク後にH2Oが発生し、h-Li2O2の分解に伴ってCO2も生成された。これらの結果から、放電時間や同位体酸素の使用が充電時の生成物分布に与える影響を考察し、LOBの劣化メカニズムとサイクル性能向上への手がかりを提示している。
Arunkumar Dorai*, Sangryun Kim*, Naoaki Kuwata, Junichi Kawamura, Kazuaki Kisu, Shin-ichi Orimo*, Journal of Physical Chemistry Letters 15, 4864-4871 (2024). "Understanding Ion Dynamics in Closoborate-Type Lithium-Ion Conductors on Different Time-Scales"
DOI:10.1021/acs.jpclett.4c00754
AI要約(翻訳):本研究では、クロソボレート型リチウムイオン導電体におけるイオン動態を異なる時間スケールで解析した。固体NMRとインピーダンス分光法を組み合わせることで、短時間スケールではLiイオンの局所的な振動、長時間スケールでは拡散的な移動が支配的であることが明らかとなった。特に、[B12H12]2−アニオンの回転がイオン伝導性に与える影響が顕著であり、温度依存性の解析から、アニオンの動的挙動がLiイオンの移動経路を促進することが示された。これらの知見は、クロソボレート系材料の設計において、アニオンの自由度を活かした高伝導性材料の開発に貢献するものである。
Go Kamesui, Kei Nishikawa, Mikito Ueda, Hisayoshi Matsushima*, JOURNAL OF THE ELECTROCHEMICAL SOCIETY 171, 040519-1-040519-8 (2024). "Elucidation of Mass Transport Phenomena in Highly Concentrated Electrolytes during Current Cycling Using In-Situ Interferometry and Finite Difference Method"
DOI:10.1149/1945-7111/ad3ad1
AI要約(翻訳):本研究では、高濃度電解液中の電流サイクル時における物質輸送現象を、インシチュ干渉法と有限差分法を用いて解析した。LiFSI–G4系電解液を対象に、電極近傍の濃度勾配と拡散挙動をリアルタイムで可視化し、電流密度の変化に伴う濃度分布の非対称性が明らかとなった。数値解析により、電解液の粘性やイオン移動度が濃度変化に与える影響を定量化し、拡散係数の時間依存性も評価された。これらの結果は、高濃度系電解液における電極反応の均一性や安定性の理解に貢献し、高性能リチウム電池の設計における電解液制御の重要性を示している。
Naoya Masuda*, Kiyoshi Kobayashi, Futoshi Utsuno, Naoaki Kuwata, JOURNAL OF SOLID STATE ELECTROCHEMISTRY 28, 4409-4417 (2024). "Enhanced capacity of all-solid-state battery comprising LiNbO3-coated Li(Ni0.8Co0.1Mn0.1)O2 Cathode, Li5.4(PS4)(S0.4Cl1.0Br0.6) solid electrolyte and lithium metal anode"
DOI:10.1007/s10008-024-05886-7
AI要約(翻訳):本研究では、LiNbO3被覆Li(Ni0.8Co0.1Mn0.1)O2正極、Li5.4(PS4)(S0.4Cl1.0Br0.6)固体電解質、Li金属負極からなる全固体電池の容量向上を報告した。炭素添加による正極の電子伝導性向上により、初期容量は3.1 mAh/gから167 mAh/gへと大幅に増加し、50サイクル後も95.4%の容量保持率と99.9%のクーロン効率を維持した。電池抵抗の変化も安定しており、高イオン伝導性を持つハロゲンリッチアルギロダイト電解質との組み合わせが高性能化に寄与した。本成果は、次世代全固体電池の設計における材料選定と構造最適化の有効性を示している。
Kento Ishii, Yuri Taniguchi, Akira Miura, Shogo Miyoshi, Kazunori Takada, Go Kawamura, Hiroyuki Muto, Atsunori Matsuda, Masayoshi Fuji, Tetsuo Uchikoshi, JOURNAL OF THE CERAMIC SOCIETY OF JAPAN 132, 257-266 (2024). "Surface modification of Li3PO4 to Li1.30.3Ti1.7(PO4)3 by wet chemical process and its sintering behavior"
DOI:10.2109/jcersj2.23208
AI要約(翻訳):本研究では、湿式化学法によりLi3PO4を修飾し、Li1.3Al0.3Ti1.7(PO4)3(LATP)への変換と焼結挙動を評価した。修飾により、800℃で90%以上の高密度焼結が達成され、従来のLATPより約300℃低い温度で焼結が可能となった。熱分析では700〜800℃での吸熱ピークが観察され、液相焼結による緻密化が示唆された。さらに、得られた焼結体は25℃で3.5×10−4 S/cmの高いイオン伝導性を示し、固体電解質材料として優れた性能を有することが確認された。これらの成果は、低温焼結による高性能固体電解質の製造技術として有望である。
Atsuki TABO, Hisayoshi MATSUSHIMA, Takahiro OHKUBO, Kei NISHIKAWA, Mikito UEDA*, ELECTROCHEMISTRY 92, 043011-1-043011-6 (2024). "Arrangement of Al Ions between Ionic Liquid and Graphite Electrode Interface by AFM Force Curve Measurement"
DOI:10.5796/electrochemistry.23-69151
AI要約(翻訳):本研究では、AlCl3–EmImClイオン液体とグラファイト電極界面におけるAlイオンの配置を、AFMフォースカーブ測定により解析した。測定では、電極に近づくにつれて0.3、0.4、0.5 nmの3段階のステップが観察され、それぞれがEmIm+、Al2Cl7−、混合層に対応すると推定された。電位変化に伴い、最も近接した層の厚みが減少する傾向があり、電極表面でのイオン配列が電位に依存して変化することが示された。これらの知見は、イオン液体の電極界面構造の理解を深め、電気二重層モデルの拡張や電極反応の制御に貢献するものである。
Tsuyoshi Ohnishi*, JOURNAL OF SOLID STATE ELECTROCHEMISTRY 28, 4355-4366 (2024). "Fabrication of thin film batteries composed of LiCoO2, Li3PO4, and Li layers"
DOI:10.1007/s10008-024-05873-y
AI要約(翻訳):本研究では、LiCoO2、Li3PO4、Liの3層からなる薄膜電池の作製と特性評価を行った。LiCoO2層はパルスレーザー蒸着法で形成され、結晶性はLi/Co比により制御された。次に、Li3PO4層を高周波スパッタリングで堆積し、バイアス制御により界面抵抗の低減を図った。最後に、Li金属層を真空中で加熱蒸着し、低抵抗な界面を形成した。得られた電池は、(104)配向のLiCoO2層を用いた場合に高いレート性能を示し、薄膜構造による高反応面積と安定な界面が性能向上に寄与した。本成果は、高品質な薄膜電池の設計と製造に向けた有効な手法を示している。
Shoichi Matsuda*, ChemElectroChem 11, e202300605-1-e202300605-8 (2024). "New Insights into Fundamental Processes and Physical Degradation Mechanisms in Rechargeable Lithium-Oxygen Batteries Providing Suitably High Energy Densities"
DOI:10.1002/celc.202300605
AI要約(翻訳):本論文では、リチウム–酸素電池(LOB)の高エネルギー密度化に向けた基礎技術と物理的劣化機構について概説している。ガス拡散層や軽量保護膜などの新技術が、500 Wh/kgを超える実用的なエネルギー密度の実現に貢献する可能性があると示された。また、充放電の繰り返しに伴う正極の体積変化や電解液の移動など、LOB特有の物理的劣化現象にも焦点を当てている。これらの現象は、固体生成物(Li2O2など)の形成・分解に起因し、電池性能に大きな影響を与える。本研究は、LOBの長寿命化と高性能化に向けた新たな研究の方向性を示すものである。
Esmail Doustkhah*, Nao Tsunoji, Shinya Mine, Takashi Toyao, Ken-ichi Shimizu, Tetsuro Morooka, Takuya Masuda, M. Hussein N. Assadi, Yusuke Ide*, ACS Applied Materials & Interfaces 16, 10251-10259 (2024). "Feeble Single-Atom Pd Catalysts for H2 Production from Formic Acid"
DOI:10.1021/acsami.3c18709
AI要約(翻訳):本研究では、ギ酸からの水素生成に用いる単原子Pd触媒の設計と性能評価を行った。Pd原子を担持した触媒は、従来のナノ粒子触媒と比較して金属使用量を大幅に削減しつつ、高い活性を維持できることが示された。特に、単原子Pdが担体との強い相互作用を持ち、反応中の中間体の吸着と脱離を効率的に制御することで、選択的かつ安定な水素生成が可能となった。また、反応条件下での触媒の構造安定性や反応経路の解析も行われ、単原子触媒の実用性と将来性が明らかになった。本成果は、低コストかつ高効率な水素製造技術の開発に貢献するものである。
Xin Zhao, Wan-Peng Li, Yanhui Cao, Arsenii Portniagin, Bing Tang, Shixun Wang, Qi Liu, Denis Y. W. Yu, Xiaoyan Zhong, Xuerong Zheng*, Andrey L. Rogach*, ACS Nano 18, 4256-4268 (2024). "Dual-Atom Co/Ni Electrocatalyst Anchored at the Surface-Modified Ti3C2Tx MXene Enables Efficient Hydrogen and Oxygen Evolution Reactions"
DOI:10.1021/acsnano.3c09639
AI要約(翻訳):本研究では、Ti3C2Tx MXene基板に固定されたCo/Ni二原子電極触媒の設計と水素・酸素発生反応(HER/OER)における性能評価を行った。L-トリプトファン分子による表面修飾により、Co/Ni原子が安定に固定され、電子状態の最適化と中間体の吸着強化が達成された。この触媒は、10 mA/cm2でのHERとOERにおいて、それぞれ31 mVと241 mVの低い過電位を示し、500 mA/cm2の高電流密度でも100時間以上の安定動作を維持した。本成果は、MXene基材を用いた高効率・高耐久な電極触媒の設計指針を提供するものである。
Takeshi Ueki*, Koichiro Uto, Shota Yamamoto, Ryota Tamate, Yuji Kamiyama, Xiaofang Jia, Hidenori Noguchi, Kosuke Minami, Katsuhiko Ariga, Hongxin Wang, Jun Nakanishi*, ADVANCED MATERIALS 36, 2310105-1-2310105-10 (2024). "Ionic Liquid Interface as a Cell Scaffold"
DOI:10.1002/adma.202310105
AI要約(翻訳):本研究では、イオン液体(IL)を細胞培養の足場として利用する新技術を提案した。テトラアルキルホスホニウム系ILは非毒性で、表面に形成されるタンパク質ナノ層が幹細胞の接着と分化を促進する。AFM観察により、ILのカチオン構造がタンパク質吸着に影響を与え、細胞のメカノセンシングにも関与することが示された。さらに、ILの溶解性を活かしてイオンゲル足場を構築し、液体基材の力学特性が細胞応答に与える影響も評価された。従来の固体足場とは異なる柔軟性と環境適応性を持ち、培養効率の向上と環境負荷の低減を両立する革新的な細胞培養技術として期待される。
Toshihiko Mandai*, Umi Tanaka, Shin Kimura, Advanced Energy and Sustainability Research 5, 2400059-1-2400059-10 (2024). "Electrode Engineering Study Toward High-Energy-Density Sodium-Ion Battery Fabrication"
DOI:10.1002/aesr.202400059
AI要約(翻訳):本研究では、高エネルギー密度ナトリウムイオン電池(SIB)の実現に向けた電極設計の最適化を行った。Na3V2(PO4)3(NVP)とハードカーボン(HC)を用いたフルセル構成において、正負極容量のバランス(N/P比)や電極組成が性能に与える影響を系統的に解析した。面積容量や容量保持率を考慮した最適な電極構成が提案され、特にプリソジエーション技術の導入が高エネルギー密度化に有効であることが示された。従来のハーフセル評価では見落とされがちな要素を含め、実用的なSIB設計に必要な工学的視点を提供する内容となっている。環境負荷の少ない次世代蓄電技術としてのSIBの可能性を広げる成果である。
Shoichi Matsuda*, Eiki Yasukawa, Shin Kimura, Shoji Yamaguchi, Kohei Uosaki, FARADAY DISCUSSIONS 248, 341-354 (2024). "Evaluation of performance metrics for high energy density rechargeable lithium–oxygen batteries"
DOI:10.1039/D3FD00082F
AI要約(翻訳):本研究では、リチウム–酸素電池(LOB)の高エネルギー密度化に向けた性能指標の評価を行った。スタック型セル構成を用いて、電解液量と面積容量の比(E/C比)が電圧挙動に与える影響を解析し、高容量条件下での複雑な電圧プロファイルを明らかにした。また、ガス拡散層の材質が充電時の“突然死”現象に与える影響も検討され、サイクル寿命や往復効率に関わる要因の理解が深まった。これらの結果は、LOBの実用化に向けた実験設計と技術パラメータの選定が極めて重要であることを示しており、高エネルギー密度電池の性能評価に新たな視点を提供するものである。
Dhruba B. Khadka*, Yasuhiro Shirai*, Masatoshi Yanagida, Hitoshi Ota, Andrey Lyalin*, Tetsuya Taketsugu, Kenjiro Miyano , Nature Communications 15, 882-1-882-16 (2024). "Defect passivation in methylammonium/bromine free inverted perovskite solar cells using charge-modulated molecular bonding"
DOI:10.1038/s41467-024-45228-9
AI要約(翻訳):本研究では、メチルアンモニウムおよび臭素を含まない反転型ペロブスカイト太陽電池における欠陥緩和手法として、電荷調整型分子結合を用いたパッシベーション技術を提案した。アルキル基を持つジアミン分子(PZDI)が表面およびバルク欠陥を効果的に緩和し、界面のエネルギー準位を調整することで、キャリア抽出効率と安定性が向上した。結果として、23.17%の高効率と21.47%の認証効率を達成し、長期動作安定性も確認された。分子の電荷分布と強い吸着性が欠陥密度の低減とイオン移動の抑制に寄与しており、本手法は高性能ペロブスカイト太陽電池の設計における新たな指針となる。
Itsuki Konuma, Naohiro Ikeda, Benoît D.L. Campéon, Hinata Fujimura, Jun Kikkawa, Huu Duc Luong, Yoshitaka Tateyama, Yosuke Ugata, Masao Yonemura, Toru Ishigaki, Taira Aida, Naoaki Yabuuchi, Energy Storage Materials 66, 103200-1-103200-11 (2024). "Unified Understanding and Mitigation of Detrimental Phase Transition in Cobalt-free LiNiO2"
DOI:10.1016/j.ensm.2024.103200
AI要約(翻訳):本研究では、コバルトフリーのLiNiO2正極材料における有害な相転移の統一的理解と緩和手法を提案した。充電時に起こるNiイオンの移動が構造劣化の主因であることを明らかにし、アンチサイト欠陥を導入することでその移動を抑制できることを示した。Li0.975Ni1.025O2という過剰Ni組成の材料を合成し、構造解析により欠陥の存在とその効果を確認。この材料は高いエネルギー密度と優れたサイクル特性、急速充電性能を示し、コバルト含有材料を凌駕する性能を達成した。簡便な合成法で実用性も高く、次世代電気自動車用電池材料としての応用が期待される。
Jittraporn Saengkaew, Emiko Mizuki, Shoichi Matsuda*, Energy Advances 3, 248-254 (2024). "Performance evaluation of lithium metal rechargeable batteries with a lithium excess cation-disordered rocksalt based positive electrode under high mass loading and lean electrolyte conditions"
DOI:10.1039/d3ya00281k
AI要約(翻訳):本研究では、リチウム過剰型カチオン無秩序ロックソルト(DRX)構造を持つ正極材料を用いたリチウム金属電池の性能評価を行った。Li2RuO3/Li2SO4をモデル材料とし、30 mg/cm²の高質量負荷と少量電解液条件下での動作を検証。粒子径制御によりスラリーのゲル化を抑制し、活物質比96%以上の電極を作製。保護Li金属電極との組み合わせで、80サイクル後も180 mAh/g超の容量を維持した。従来の評価条件では見えにくかったDRX材料の高性能が実用的条件下で示され、高エネルギー密度電池の実現に向けた有望な設計指針を提供する。
Ridwan P. Putra, Kyosuke Matsushita, Tsuyoshi Ohnishi, Takuya Masuda*, Journal of Physical Chemistry Letters 15, 490-498 (2024). "Operando Nanomechanical Mapping of Amorphous Silicon Thin Film Electrodes in All-Solid-State Lithium-Ion Battery Configuration during Electrochemical Lithiation and Delithiation"
DOI:10.1021/acs.jpclett.3c03012
AI要約(翻訳):本研究では、全固体型リチウムイオン電池構成におけるアモルファスSi薄膜電極のリチウム挿入・脱離過程を、原位ナノメカニカルマッピングにより解析した。二重モードAFMを用いて、LixSiの形成に伴うヤング率の変化をリアルタイムで追跡し、3300 mAh/g(x=3.46)までのリチウム挿入で弾性率が低下、脱離では1467 mAh/g(x=1.54)まで回復する様子が観察された。相転移による体積変化が脱離停止の要因となり、Si電極の構造安定性と性能劣化の関係が明らかとなった。この手法は、高容量電極材料の力学的挙動を理解する上で有用であり、次世代電池設計に貢献する。
Fumisato OZAWA*, Kazuki KOYAMA, Daiki IWASAKI, Shota AZUMA, Akihiro NOMURA, Morihiro SAITO*, ELECTROCHEMISTRY 92, 047003-1-047003-7 (2024). "The Effect of Supply Rate of Li Ion and Anion on Li Dissolution/Deposition Behavior in LiNO3 Electrolyte Solutions for Li-Air Batteries"
DOI:10.5796/electrochemistry.23-00142
AI要約(翻訳):本研究では、LiNO3/G4電解液中におけるLi金属の溶解・析出挙動に対するLiイオンおよびアニオン供給速度の影響を検討した。O2雰囲気下での対称セル試験により、1.0 M LiNO3溶液ではLi2O保護層が形成され、デンドライト抑制と反応の可逆性向上が確認された。さらに、電流密度や温度を変化させた条件下での挙動を評価し、SEMおよびXPS解析により電極表面の変化を可視化した。結果として、LiおよびNO3−の供給速度が電極反応の安定性に大きく影響することが示され、Li–空気電池の性能向上に向けた電解液設計の重要性が明らかとなった。
Toshihiko Mandai*, Umi Tanaka, Mariko Watanabe, Energy Storage Materials 67, 103302-1-103302-10 (2024). "Mg–Zn–Cl-integrated functional interface for enhancing the cycle life of Mg electrodes"
DOI:10.1016/j.ensm.2024.103302
AI要約(翻訳):本研究では、マグネシウム電池のサイクル寿命を向上させるために、Mg–Zn–Cl系の機能性界面を設計・評価した。MgCl2とZnCl2を含む電解液を用いることで、Mg電極表面に安定な保護層が形成され、腐食や不均一な析出が抑制された。電気化学インピーダンス測定により、界面抵抗の低減と充放電の安定性向上が確認され、SEMおよびXPS解析によって保護層の組成と構造が明らかとなった。特にZn添加は、Mgの電析挙動を均一化し、電極の長寿命化に寄与することが示された。さらに、界面の安定性が電池性能に与える影響を詳細に解析し、Mg電池の実用化に向けた界面設計の重要性を強調している。本成果は、高性能かつ長寿命なMg電池の開発に向けた新たな材料戦略を提示するものであり、次世代エネルギー貯蔵技術への応用が期待される。
Shota Azuma, Mitsuki Sano, Itsuki Moro, Fumisato Ozawa, Morihiro Saito*, Akihiro Nomura*, ELECTROCHIMICA ACTA 489, 144261-1-144261-9 (2024). "Improving the cycling performance of lithium-air batteries using a nitrite salt electrolyte"
DOI:10.1016/j.electacta.2024.144261
AI要約(翻訳):本研究では、リチウム空気電池のサイクル性能向上を目的として、亜硝酸塩(NO2−)を含む電解液の効果を詳細に検討した。従来の硝酸塩系電解液と比較して、NO2−はLi金属の溶解・析出反応を安定化させ、電極表面に形成される保護層の構造を改善することが示された。対称セル試験では、電圧安定性と可逆性の向上が確認され、XPS解析により副反応の抑制と界面の化学的安定性が明らかとなった。さらに、電流密度や温度の変化に対する電池挙動も評価され、亜硝酸塩の導入が長寿命化に寄与することが実証された。本成果は、Li–空気電池の実用化に向けた電解液設計に新たな選択肢を提供し、高エネルギー密度と安定動作を両立する次世代電池技術の確立に貢献するものである。
Reona Iimura, Hiroto Watanabe, Toshihiko Mandai, Itaru Honma, Hiroaki Imai, Hiroaki Kobayashi*, ACS Applied Energy Materials 7, 5308-5314 (2024). "An Electrically Conductive CuMn2O4 Ultrananospinel Cathode for Room-Temperature Magnesium Rechargeable Batteries"
DOI:10.1021/acsaem.4c01211
AI要約(翻訳):本研究では、室温で動作可能なマグネシウム二次電池用に、導電性CuMn2O4超ナノ尖晶石正極材料を開発し、その電気化学的特性を評価した。アルコール還元法により粒径5 nm以下の均一なナノ粒子を合成し、CuおよびMnの二重酸化還元反応を活用することで、Mgの挿入・脱離に伴う半可逆的な相転移を実現。高電圧(>1.5 V)での安定動作と225 mAh/gの理論容量を持ち、従来の酸化物系正極材料と比較して優れたレート性能とサイクル安定性を示した。さらに、導電性の向上により内部抵抗が低減され、室温動作における実用性が高まった。この成果は、Mg電池の高性能化と低温動作の両立を可能にする新規材料設計の一例であり、次世代エネルギー貯蔵技術への応用が期待される。
水素材料分野
Taku T. Suzuki*, Soshi Iimura, PHYSICAL REVIEW B 110, 085426-1-085426-10 (2024). "Quench-condensed hydrogen films studied by cryogenic time-of-flight secondary ion mass spectrometry"
DOI:10.1103/PhysRevB.110.085426
AI要約(翻訳):本研究では、急冷凝縮された水素薄膜の表面構造と昇温過程における変化を、極低温飛行時間型二次イオン質量分析(TOF-SIMS)を用いて詳細に解析した。多結晶タングステン基板上に形成された固体水素膜に対し、温度を段階的に上昇させながら、H−およびH2−イオンの強度変化を追跡。イオン強度の増加は昇華、減少は吸着分子の脱離に起因することが示され、表面融解の兆候は観察されなかった。また、表面構造の変化は膜厚や基板の性質にも依存することが示唆され、固体水素の表面物性に関する理解を深める結果となった。この知見は、極低温環境下での水素の挙動を解明する上で重要であり、将来的には超流動性や量子物理の分野への応用も期待される。
Prerna Chettri, Anup Singhania, Sudeshna Kalita, Hidenobu Nakao, Bharati Bora, Ponkaj Saikia, Sanghamitra Dutta, Anirban Bandyopadhyay*, Subrata Ghosh*, Advanced Optical Materials 12, 2400650-1-2500650-8 (2024). "Fluorescent Nanowires from Dual-State Emitting Fluorophores Directed by Molecular Motors and Aggregation-Induced Emission: Produce Quantized Light Spectrum"
DOI:10.1002/adom.202400650
AI要約(翻訳):本研究では、二状態発光性フルオロフォアを用いた蛍光ナノワイヤの構築と、それによる量子化された光スペクトルの生成に成功した。分子モーターによる方向性制御と凝集誘起発光(AIE)効果を組み合わせることで、自己組織化されたナノワイヤが形成され、発光特性が精密に制御された。このナノ構造は、分子の運動と発光状態の切り替えを可能にし、光の波長を離散的に制御する新たな手法として注目される。さらに、ナノワイヤは高い蛍光強度と安定性を示し、光情報処理、量子通信、バイオセンシングなど多様な応用が期待される。本成果は、分子設計とナノ構造制御を融合させた革新的な光機能材料の創出に貢献し、次世代の光技術に新たな可能性をもたらす。
Koji Kamiya*, Kyohei Natsume, Takenori Numazawa, Kohei Ouchi, Tsuyoshi Shirai, Akira Uchida, IEEE TRANSACTIONS ON APPLIED SUPERCONDUCTIVITY 34, 3800805-1-3800805-5 (2024). "Development of a Superconducting Magnet System for Magnetic Refrigeration Using a Switching Power Supply"
DOI:10.1109/TASC.2024.3367966
AI要約(翻訳):本研究では、磁気冷凍技術に向けた超電導磁石システムをスイッチング電源を用いて開発し、その性能と動作特性を評価した。NbTi超電導線材を用いた磁石は、電源の切り替えによって磁場の制御が容易になり、冷却効率の向上とエネルギー消費の低減を両立。設計では、磁場強度の安定性と電源応答性を重視し、実験により高い再現性と信頼性が確認された。さらに、システムの小型化と軽量化にも成功し、実用的な磁気冷凍機への応用可能性が高まった。この成果は、超電導技術と電源制御の融合による新しい冷却システムの構築に貢献し、環境負荷の少ない冷却技術の実現に向けた重要な一歩となる。
Daiki Umeyama*, Soshi Iimura, JOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY 146, 33964-33972 (2024). "Ligand-Directed Valence Band Engineering in Pb2+ Hybrid Crystals: Achieving Dispersive Bands and Shallow Valence Band Maximum"
DOI:10.1021/jacs.4c12804
AI要約(翻訳):本研究では、Pb2+を含むハイブリッド結晶において、配位子設計による価電子帯の分散性と浅い価電子帯最大値(VBM)の制御に成功した。有機配位子の構造を変化させることで、結晶中の電子軌道の重なりを調整し、価電子帯の分散性を高めるとともに、VBMのエネルギー準位を浅くすることが可能となった。第一原理計算と光電子分光測定により、配位子の電子供与性がバンド構造に与える影響を定量的に評価し、電子移動度の向上と光吸収特性の改善が確認された。これにより、Pb系ハイブリッド材料の光電変換効率や電荷輸送特性の最適化が期待される。本成果は、バンド構造を分子レベルで制御する新たな材料設計指針を示しており、次世代の光電子デバイスやエネルギー材料への応用に大きく貢献する可能性がある。
Minoru Maeda, Jun Hyuk Choi, Dong Gun Lee, Akiyoshi Matsumoto, Gen Nishijima, Zhenan Jiang, Nicholas M. Strickland, Jung Ho Kim*, Seyong Choi*, Ceramics International 50, 36042-36049 (2024). "Evaluation of in-plane and out-of-plane crystallinities with residual amorphous phases for MgB2 superconductor"
DOI:10.1016/j.ceramint.2024.06.416
AI要約(翻訳):本研究では、MgB2超伝導体における面内および面外の結晶性と残留アモルファス相の関係を評価し、材料特性への影響を明らかにした。X線回折(XRD)と透過型電子顕微鏡(TEM)を用いて、結晶性の異方性とアモルファス相の分布を詳細に解析。面内方向では高い結晶性が確認された一方、面外方向にはアモルファス相が多く残存しており、これが臨界電流密度や磁束ピン止め特性に影響を与えることが示された。さらに、熱処理条件や成膜プロセスの違いが結晶成長に与える影響を比較し、最適な製造条件の指針を提示した。本成果は、MgB2の構造制御による超伝導特性の向上に貢献し、高性能な超伝導材料の開発に向けた重要な知見を提供するものである。
M. Sugano*, A. Kikuchi, H. Kitaguchi, G. Nishijima, T. Yagai, IEEE TRANSACTIONS ON APPLIED SUPERCONDUCTIVITY 34, 8400305-1-8400305-5 (2024). "Uniaxial Tensile Stress Tolerance of Ultra-Thin Nb3Sn Composite Wires and Twisted Cables"
DOI:10.1109/TASC.2024.3355355
AI要約(翻訳):本研究では、極薄Nb3Sn複合線材および撚りケーブルの一軸引張応力耐性を評価し、超電導マグネット応用における機械的信頼性を検証した。Nb3Sn層の厚さを制御した複合構造により、応力集中の緩和と断線リスクの低減が図られた。引張試験では、撚り構造が応力分散に寄与し、単線よりも高い耐性を示した。さらに、超電導特性への影響を測定し、臨界電流密度の保持率が高いことが確認された。SEM観察により、応力下での微細構造変化と破壊メカニズムが明らかとなり、設計指針の構築に貢献した。本成果は、次世代高磁場超電導マグネットの構造設計において、機械的強度と電気特性の両立を可能にする材料開発の重要な一歩となる。
S. Matsunaga*, G. Nishijima, Y. Narushima, K. Natsume, N. Yanagi, K. Kamiya, IEEE TRANSACTIONS ON APPLIED SUPERCONDUCTIVITY 34, 4605705-1-4605705-5 (2024). "No-Insulation BSCCO Coils Impregnated With Low-Melting Point Metal"
DOI:10.1109/TASC.2024.3397572
AI要約(翻訳):本研究は、低融点金属を含浸させた無絶縁型Bi-Pb-Sr-Ca-Cu-O(Bi,Pb)2Sr2Ca2Cu3O10(BSCCO)高温超伝導コイルの電気的および熱的特性を評価したものである。無絶縁型は過電流時の自己保護機能を有し、熱的安定性に優れることが示された。低融点金属の含浸により、機械的強度と熱伝導性が向上し、冷却効率も改善された。液体窒素中での充電試験により、電流分布と温度応答を詳細に解析した。結果として、無絶縁構造と金属含浸の組み合わせが、高信頼性かつ高性能な超伝導磁石の実現に寄与する可能性が示された。今後は、核融合炉や医療用MRIなどへの応用が期待される。
Sherjeel Mahmood Baig, Satoshi Ishii, Hideki Abe*, Nanoscale Advances 6, 2582-2585 (2024). "Sub-50 nm patterning of alloy thin films via nanophase separation for hydrogen gas sensing"
DOI:10.1039/d4na00071d
AI要約(翻訳):本研究では、水素ガスセンシング用途に向けた合金薄膜のサブ50 nmパターン形成技術を開発した。プラチナ-セリウム合金をシリコン基板上に成膜し、酸素と一酸化炭素雰囲気下で相分離を誘導することで、Pt-CeO2/Si構造のナノパターンを形成した。得られたパターンは平均幅50 nmで、光リソグラフィーの波長限界を克服する新たな手法として注目される。このナノ構造は水素の吸着・脱離に対して高感度な電気応答を示し、水素センサーとしての有用性が示された。本手法はスケーラブルで量産性にも優れ、次世代のガスセンシングデバイスへの応用が期待される。工程が簡易で、低コストで高性能なセンサーの実現に貢献する可能性がある。
Wen-Ning Lu, Shunqin Luo*, Yibo Zhao, Jianbing Xu, Gaoliang Yang, Emmanuel Picheau, Minmin Han, Qi Wang, Sijie Li, Lulu Jia, Ming-Xing Ling, Tetsuya Kako, Jinhua Ye*, Applied Catalysis B-Environment and Energy 343, 123520-1-123520-9 (2024). "Bifunctional Co active site on dilute CoCu plasmonic alloy for light-driven H2 production from methanol and water"
DOI:10.1016/j.apcatb.2023.123520
AI要約(翻訳):本研究は、希薄なCoCuプラズモン合金上に構築された双機能Co活性点が、メタノールと水からの光駆動型水素生成において高い触媒性能を示すことを明らかにしたものである。Co活性点は、酸化還元反応と光吸収の両方に寄与し、反応効率を向上させる役割を果たす。特に、プラズモン共鳴による光エネルギーの活用が、低エネルギー条件下での水素生成を可能にしている。実験では、光照射下での反応速度や生成量を定量的に評価し、従来の単機能触媒と比較して優れた性能を確認した。さらに、触媒の安定性と再利用性も高く、持続可能な水素製造技術としての可能性が示された。この成果は、太陽光を利用したクリーンエネルギー生成の新たな道を拓くものであり、将来的な実用化が期待される。
Akiyoshi Matsumoto*, Shigeyuki Matsunami, Hiroshi Narazaki, Shinya Kawashima, Masayoshi Inoue, IEEJ Transactions on Fundamentals and Materials 144, 366-372 (2024). "Example of Data-driven Superconducting Wire Research"
DOI:10.1541/ieejfms.144.366
AI要約(翻訳):本論文は、データ駆動型アプローチを用いた超伝導線材の研究事例を紹介している。従来の実験主導型手法に代わり、膨大な材料データを解析することで、性能予測や寿命評価を効率的に行う手法が提案された。特に、機械学習を活用して、線材の電気特性や構造的安定性に関する相関を抽出し、最適な設計指針を導出している。このアプローチにより、試行錯誤の回数を減らし、開発期間の短縮とコスト削減が可能となる。また、実際の応用例として、電力機器への導入を想定した線材設計が示されており、信頼性評価にも有効であることが確認された。データ駆動型研究は、今後の材料開発において重要な役割を果たすと考えられる。
Kyohei Natsume*, Tsuyoshi Shirai, Akira Uchida, Yusuke Kimura, Yuki Emori, Hiroshi Miyazaki, Gen Nishijima, Koji Kamiya, Koichi Matsumoto, Takenori Numazawa, IEEE TRANSACTIONS ON APPLIED SUPERCONDUCTIVITY 34, 3801005-1-3801005-5 (2024). "Effects of Moving Magnetic Materials in and out of Superconducting Magnet for Active Magnetic Regenerative Refrigeration System"
DOI:10.1109/TASC.2024.3384342
AI要約(翻訳):本研究は、超伝導磁石を用いた能動型磁気再生冷却システムにおいて、磁性材料の出入りが冷却性能に与える影響を検討したものである。磁性材料を磁場内外に移動させることで、磁気熱量効果を活用した冷却サイクルが形成される。実験では、磁性体の移動速度やタイミングが冷却効率に与える影響を詳細に解析し、最適な運転条件を導出した。特に、磁場強度と材料の配置が温度変化に大きく関与することが示された。この手法は、液体水素や液体ヘリウムの冷却に応用可能であり、従来の冷却技術に比べて高効率かつ低エネルギーでの運用が期待される。将来的には、宇宙機器や低温医療機器への応用が見込まれる。
Ryuto Eguchi*, Yu Wen, Hideki Abe, Ayako Hashimoto*, Nanomaterials 14, 1413-1-1413-12 (2024). "Interpretable Structural Evaluation of Metal-Oxide Nanostructures in Scanning Transmission Electron Microscopy (STEM) Images via Persistent Homology"
DOI:10.3390/nano14171413
AI要約(翻訳):本研究では、金属酸化物ナノ構造のSTEM画像に対して、パーシステントホモロジーを用いた構造評価手法を提案した。従来の画像解析では困難だった微細構造の定量的特徴抽出を、トポロジー的手法により実現している。この手法は、画像中の形状や空間分布を数理的に捉えることで、構造の違いや変化を明確に識別できる利点がある。実験では、複数の酸化物ナノ構造を対象に解析を行い、構造的特徴と物性との相関を明らかにした。さらに、解釈性の高い可視化結果を得ることで、材料設計や評価における新たな指針を提供している。このアプローチは、ナノ材料の構造解析において汎用性が高く、今後の材料科学分野での応用が期待される。
Hiroshi Amekura*, Norito Ishikawa, Nariaki Okubo, Feng Chen, Kazumasa Narumi, Atsuya Chiba, Yoshimi Hirano, Keisuke Yamada, Shunya Yamamoto, Yuichi Saitoh, Quantum Beam Science 8, 29-1-29-13 (2024). "Metallic Ca Aggregates Formed Along Ion Tracks and Optical Anisotropy in CaF2 Crystals Irradiated with Swift Heavy Ions"
DOI:10.3390/qubs8040029
AI要約(翻訳):本研究は、CaF2結晶に高速重イオンを照射することで形成される金属Ca凝集体と、それに伴う光学異方性の発現を解析したものである。照射によって生成されるイオントラックに沿ってCa原子が集積し、局所的な金属相が形成されることが観察された。これにより、結晶内部に方向依存性のある光学特性が生じ、屈折率や透過率に変化が現れる。実験では、分光測定と電子顕微鏡観察を組み合わせて、構造変化と光学応答の関係を詳細に評価した。この現象は、放射線による材料改質の新たな手法として注目されており、光学素子や情報記録材料への応用が期待される。照射条件の制御により、特性を自在に設計できる可能性が示された。
Min Sung Kim, Jun Ho Yoon, Hyun Kyu Lee, Tamaki Hirose, Yoshihiko Takeda*, Jae Pil Kim*, COLLOIDS AND SURFACES A-PHYSICOCHEMICAL AND ENGINEERING ASPECTS 703, 135118-1-135118-9 (2024). "Binder-enhanced reversible photochromic films by tungsten oxide hybrid composites for advanced applications"
DOI:10.1016/j.colsurfa.2024.135118
AI要約(翻訳):本研究は、酸化タングステン(WO3)を基盤としたハイブリッド複合材料を用いて、可逆的な光クロミックフィルムの性能を向上させるためのバインダーの役割を検討したものである。バインダーの種類と濃度が、フィルムの着色・脱色速度、安定性、耐久性に与える影響を系統的に評価した。特に、ポリマー系バインダーが光応答性を高め、繰り返し使用における劣化を抑制する効果があることが示された。実験では、紫外線照射と可視光照射による色変化を定量的に測定し、応答性の高い設計指針を導出した。この技術は、スマートウィンドウや光センサーなどの先進的応用に適しており、環境負荷の少ない機能性材料としての可能性が示された。
Deepak Panchal, Qiuyun Lu, Ken Sakaushi, Xuehua Zhang-, Chemical Engineering Journal 498, 154920-1-154920-23 (2024). "Advanced cold plasma-assisted technology for green and sustainable ammonia synthesis"
DOI:10.1016/j.cej.2024.154920
AI要約(翻訳):本研究は、環境負荷の少ない持続可能なアンモニア合成技術として、冷プラズマ支援プロセスを活用した新手法を提案している。従来のハーバー・ボッシュ法に比べて、低温・低圧条件下での反応が可能であり、エネルギー消費を大幅に削減できる利点がある。プラズマによって活性化された窒素と水素が触媒表面で反応し、アンモニアを生成するメカニズムが明らかにされた。実験では、反応効率や収率を複数の触媒条件下で評価し、最適なプロセス設計を導出した。この技術は、再生可能エネルギーとの統合が容易であり、分散型化学製造にも適している。将来的には、農業やエネルギー分野におけるグリーンケミストリーの中核技術としての展開が期待される。
Kiyosumi TSUCHIYA*, Xudon WANG, Shinji FUJITA, Akio TERASHIMA, Yasushi ARIMOTO, Norihito OHUCHI, Zhanguo ZONG, Akihiro KIKUCHI, TEION KOGAKU (Journal of Cryogenics and Superconductivity Society of Japan) 59, 246-254 (2024). "Development of HTS Sextupole Magnet for Accelerator"
DOI:10.2221/jcsj.59.246
AI要約(翻訳):本研究は、加速器用高温超伝導(HTS)六極磁石の設計・製作・試験に関する成果を報告している。REBCOコート導体を用いた通常型およびスキュー型の六極コイルを組み合わせ、SuperKEKB相互作用領域向けのプロトタイプ磁石を構築した。磁場分布の均一性と強度を高精度に制御するため、コイル配置と巻線技術に工夫を施している。試験では、低温環境下での臨界電流や磁場特性を評価し、設計通りの性能を確認した。この成果は、高エネルギー物理実験におけるビーム制御精度の向上に貢献するものであり、HTS技術の加速器応用における重要なステップとなる。今後は、さらなる小型化や高効率化に向けた改良が進められる見込みである。
Akihiro Kikuchi*, Yasuo Iijima, Hiroaki Kumakura, Masaru Yamamoto, Masatoshi Kawano, Masato Otsubo, IEEE TRANSACTIONS ON APPLIED SUPERCONDUCTIVITY 34, 6200104-1-6200104-4 (2024). "Development of the Ultrafine MgB2 Superconducting Wires and Flexible Cables"
DOI:10.1109/TASC.2023.3335881
AI要約(翻訳):本研究は、超微細なMgB2超伝導線材および柔軟ケーブルの開発に関する成果を報告している。従来の線材に比べて直径を大幅に縮小しつつ、臨界電流密度や機械的柔軟性を維持する技術が確立された。製造には粉末内包法を用い、線材の均一性と密度を高める工夫が施されている。さらに、柔軟性を持たせるために多芯構造や被覆材の選定が行われ、曲げ試験でも高い耐久性が確認された。これにより、狭小空間や可動部への応用が可能となり、医療機器や航空宇宙分野での利用が期待される。MgB2の低コスト性と高性能を活かした新しい超伝導ケーブル技術として、今後の展開が注目される。
Min-Sung Kim, Jun-Ho Yoon, Hong-Mo Kim, Dong-Jun Lee, Tamaki Hirose, Yoshihiko Takeda*, Jae-Pil Kim*, Nanomaterials 14, 1121-1-1121-15 (2024). "Amplifying Photochromic Response in Tungsten Oxide Films with Titanium Oxide and Polyvinylpyrrolidone"
DOI:10.3390/nano14131121
AI要約(翻訳):本研究は、酸化タングステン(WO3)薄膜に酸化チタン(TiO2)とポリビニルピロリドン(PVP)を添加することで、光クロミック応答を増強する手法を提案している。TiO2は電子移動を促進し、PVPはフィルムの均一性と安定性を向上させる役割を果たす。実験では、紫外線照射による着色と可視光による脱色の速度と効率を比較し、複合化による性能向上を確認した。さらに、繰り返し使用における耐久性も高く、スマートウィンドウや光センサーへの応用が期待される。この技術は、環境に優しい機能性材料としての可能性を示しており、次世代の光応答型デバイス開発に貢献するものである。
Ken-ichi Bajo*, Noriyuki Kawasaki, Isao Sakaguchi, Taku T. Suzuki, Satoru Itose, Miyuki Matsuya, Morio Ishihara, Kiichiro Uchino, Hisayoshi Yurimoto, ANALYTICAL CHEMISTRY 96, 5143-5149 (2024). "In Situ Helium Isotope Microimaging of Meteorites"
DOI:10.1021/acs.analchem.3c05201
AI要約(翻訳):本研究では、隕石中のヘリウム同位体分布をその場で可視化するマイクロイメージング技術を開発した。高感度の質量分析装置とイオンビームを組み合わせることで、微細領域における3Heと4Heの空間分布を高精度に測定可能とした。この手法により、隕石の形成過程や宇宙線照射履歴を詳細に解析することができる。実験では複数の隕石試料を対象に測定を行い、鉱物種ごとの同位体濃度の違いを明らかにした。さらに、得られたデータは惑星科学や宇宙物質の起源解明に貢献するものであり、地球外物質の研究における新たな分析手法としての有用性が示された。
Shin Hasegawa*, Satoshi Ito, Gen Nishijima, Satoshi Awaji, Kohki Takahashi, Hidetoshi Hashizume, IEEE TRANSACTIONS ON APPLIED SUPERCONDUCTIVITY 34, 3801110-1-3801110-10 (2024). "Quench Detection in Insulated, NI, and MI (RE)Ba2Cu3O7−x Coils With Superconducting Quench Detectors"
DOI:10.1109/TASC.2024.3404812
AI要約(翻訳):本研究は、絶縁型、無絶縁型(NI)、金属絶縁型(MI)の(RE)Ba2Cu3O7−x超伝導コイルにおけるクエンチ検出性能を、超伝導クエンチ検出器(SQD)を用いて比較したものである。各構造に対してSQDの応答時間や検出精度を評価し、クエンチ初期段階での信号取得の有効性を確認した。特に、MI構造では熱伝導性が高く、検出器との相互作用が安定していた。実験では、液体窒素環境下での通電試験を実施し、電圧変化と温度応答を詳細に解析した。結果として、SQDは多様なコイル構造に対応可能であり、早期検出と安全停止に貢献することが示された。この技術は、次世代の高信頼性超伝導磁石の運用において重要な役割を果たすと考えられる。
Won Seok Lee, Hiroaki Maeda, Yen-Ting Kuo, Koki Muraoka, Naoya Fukui, Kenji Takada, Sono Sasaki, Hiroyasu Masunaga, Akira Nakayama, Hong-Kang Tian*, Hiroshi Nishihara*, Ken Sakaushi*, Small 20, 2401987-1-2401987-10 (2024). "Spontaneous-Spin-Polarized Two-Dimensional π-d Conjugated Frameworks towards Enhanced Oxygen Evolution Kinetics"
DOI:10.1002/smll.202401987
AI要約(翻訳):本研究では、酸素発生反応(OER)の触媒性能を向上させるために、自然発現するスピン分極を有する二次元π-d共役フレームワークを設計・合成した。分子設計により、遷移金属中心と有機配位子の電子相互作用を強化し、スピン状態の制御を実現している。これにより、電子移動が促進され、OER反応の活性が向上した。実験では、電気化学測定と分光解析を通じて、構造と反応性の相関を明らかにした。さらに、安定性試験により、長時間動作における性能維持が確認された。この成果は、エネルギー変換材料の新たな設計指針を提供し、水分解や燃料電池への応用が期待される。
S. Hoshino, N. Ishida, T. Yagai, T. Hamajima, N. Banno*, H. Utoh, Y. Sakamoto, IEEE TRANSACTIONS ON APPLIED SUPERCONDUCTIVITY 34, 1-4 (2024). "Novel Strand Position Detection System Using Thermistor Array for Next Generation Large Fusion Magnet Cable-in-Conduit Conductors"
DOI:10.1109/TASC.2024.3358267
AI要約(翻訳):本研究は、次世代大型核融合磁石用ケーブル・イン・コンジット導体(CICC)において、内部ストランドの位置を高精度で検出する新しい熱センサーアレイシステムを開発したものである。熱抵抗素子(サーミスタ)を多数配置することで、通電時の局所加熱を検出し、ストランドの空間分布を可視化する技術が提案された。実験では、模擬導体を用いて温度分布を測定し、ストランド位置との相関を解析した。この手法は、従来の非破壊検査では困難だった内部構造の把握を可能にし、製造品質の向上と信頼性評価に寄与する。将来的には、CICCの設計最適化や運用中のモニタリング技術としての応用が期待される。
Nobuya Bann*, Taku Moronaga, Toru Hara, Koki Asai, Tsuyoshi Yagai, SUPERCONDUCTOR SCIENCE & TECHNOLOGY 37, 1-10 (2024). "In-depth S/TEM observation of Ti–Hf and Ta–Hf-doped Nb3Sn layers"
DOI:10.1088/1361-6668/ad2982
AI要約(翻訳):本研究は、Ti–HfおよびTa–Hfを添加したNb3Sn層の微細構造を透過型電子顕微鏡(S/TEM)で詳細に観察したものである。添加元素が結晶粒成長や界面構造に与える影響を解析し、粒径の均一化や結晶欠陥の抑制効果を確認した。特に、Hf添加は粒界の安定化に寄与し、臨界電流密度向上に有効であることが示された。観察結果から、添加元素の分布や拡散挙動がNb3Sn層の性能に直結することが明らかとなった。この知見は、高磁場応用に向けた超伝導線材の設計指針を提供し、次世代加速器や核融合装置での利用に貢献する可能性がある。
Hiroki Fujimoto*, Akiyoshi Matsumoto, Shuuichi Ooi, Minoru Tachiki, Masayoshi Inoue, Ryo Teranishi, IEEE TRANSACTIONS ON APPLIED SUPERCONDUCTIVITY 34, 7500604-1-7500604-4 (2024). "Consideration of Magnetic Flux Distribution in Multi−Filamented YBa2Cu3O7−δ Films by Controlling Crystal Array Using Surface−Modified Substrate"
DOI:10.1109/TASC.2024.3362729
AI要約(翻訳):本研究は、多フィラメント化したYBa2Cu3O7−δ薄膜における磁束分布を、基板表面修飾による結晶配列制御を通じて検討したものである。結晶配列の均一化により、磁束ピン止め特性が改善され、臨界電流密度の向上が確認された。特に、基板表面の微細加工がフィラメント間の磁束分布を安定化させ、磁場下での性能を高める効果を示した。実験では、磁場印加下での電流分布を測定し、結晶配列と磁束挙動の相関を解析した。結果として、結晶配列制御は高性能超伝導薄膜の設計に有効であり、次世代電力機器や磁気応用への展開が期待される。
Koki Asai, Tsuyoshi Yagai, Nobuya Banno*, IEEE TRANSACTIONS ON APPLIED SUPERCONDUCTIVITY 34, 8600105-1-8600105-5 (2024). "Effect of Hf addition to Nb on Nb3Sn grain morphology under high Sn diffusion driving force"
DOI:10.1109/TASC.2024.3368990
AI要約(翻訳):本研究は、高いSn拡散駆動力下におけるNb3Sn層の結晶粒形態に対するHf添加の効果を解析したものである。Hfの導入により、粒成長が抑制され、微細かつ均一な結晶粒構造が形成されることが確認された。これにより、粒界密度が増加し、磁束ピン止め特性が向上することが示された。実験では、拡散反応条件を制御し、Nb3Sn層の形成過程を詳細に観察した。結果として、Hf添加は高磁場環境下での臨界電流密度向上に有効であり、次世代高性能超伝導線材の設計に重要な知見を提供するものである。
Nobuya Banno, Toshihisa Asano, Tsuyoshi Yagai, Shinya Kawashima, Masahiro Sugimoto, Satoshi Awaji, Hiroyasu Utoh, Yoshiteru Sakamoto, IEEE TRANSACTIONS ON APPLIED SUPERCONDUCTIVITY 34, 8400505-1-8400505-5 (2024). "Characterization of Japan's DEMO candidate reinforced Nb3Sn wires under crossover contact stress"
DOI:10.1109/TASC.2024.3362754
AI要約(翻訳):本研究は、日本のDEMO炉候補として開発された補強型Nb3Sn線材のクロスオーバー接触応力下での特性評価を行ったものである。線材がケーブル構造内で交差する際に発生する応力が臨界電流や機械的安定性に与える影響を詳細に解析した。実験では、異なる応力条件下での臨界電流密度の変化を測定し、補強設計の有効性を検証した。結果として、補強型線材は従来型に比べて応力耐性が高く、性能劣化を抑制できることが示された。この知見は、次世代核融合炉用超伝導導体の設計指針を提供し、長期信頼性の確保に寄与するものである。
Akiyoshi Matsumoto*, Minoru Tachiki, Shuuichi Ooi, Ryo Teranishi, Masayoshi Inoue, IEEE TRANSACTIONS ON APPLIED SUPERCONDUCTIVITY 34, 7500404-1-7500404-4 (2024). "Microstructural Study of YBCO Thin Films With Stripe-Patterned Substrates for Ultra-Fine Multi-Filaments"
DOI:10.1109/TASC.2024.3366159
AI要約(翻訳):本研究は、ストライプ状に加工された基板を用いて作製したYBa2Cu3O7−δ薄膜の微細構造を解析し、超微細多フィラメント化の可能性を検討したものである。基板表面のパターンが結晶成長に与える影響を観察し、フィラメント間の分離性や結晶配列の均一性を評価した。結果として、ストライプ基板は磁束ピン止め特性を改善し、臨界電流密度の向上に寄与することが確認された。この手法は、次世代高性能超伝導線材の設計に有効であり、電力応用や磁気機器への展開が期待される。
H. Amekura*, A. Chettah, K. Narumi, A. Chiba, Y. Hirano, K. Yamada, S. Yamamoto, A. A. Leino, F. Djurabekova, K. Nordlund, N. Ishikawa, N. Okubo, Y. Saitoh, Nature Communications 15, 1786-1-1786-10 (2024). "Latent ion tracks were finally observed in diamond"
DOI:10.1038/s41467-024-45934-4
AI要約(翻訳):本研究は、ダイヤモンド中に潜在的に形成されるイオントラックを初めて直接観察することに成功したものである。高速重イオン照射によって結晶内部に形成される欠陥構造を、先進的な分光法と電子顕微鏡を用いて検出した。観察結果から、イオントラックが結晶の光学特性や機械的特性に影響を与えることが明らかとなった。特に、局所的な屈折率変化や異方性の発現が確認され、材料改質の新たな可能性が示された。この成果は、放射線応用や量子材料研究において重要な知見を提供し、ダイヤモンドを基盤とする先端デバイス開発に寄与するものである。
F. Kametani, Y. Su, C. Tarantini, E. Hellstrom, A. Matsumoto, H. Kumakura, K. Togano, H. Huang, Y. Ma, Applied Physics Express 17, 013004-1-013004-5 (2024). "On the mechanisms of Jc increment and degradation in high-Jc Ba122 tapes made by different processing methods"
DOI:10.35848/1882-0786/ad1891
AI要約(翻訳):本研究は、高臨界電流密度(Jc)を有するBaFe2As2(Ba122)テープにおけるJc増加と劣化のメカニズムを、異なる加工法を比較して解析したものである。熱処理条件や機械的圧延の違いが結晶粒構造や欠陥分布に影響を与え、Jc特性に直結することが示された。適切な加工により粒界ピン止め効果が強化され、Jcが向上する一方、過度な加工は欠陥の増加を招き性能低下を引き起こすことが確認された。磁場下での臨界電流測定を通じて、加工条件と性能の相関を詳細に評価した。結果として、最適なプロセス設計が高性能Ba122テープの実現に不可欠であり、次世代超伝導応用への展開が期待される。さらに、この知見は線材開発の効率化や信頼性向上にも寄与するものである。
Hideki Abe*, Hiroshi Mizoguchi, Ryuto Eguchi, Hideo Hosono*, Exploration 4, 20230040-1-20230040-7 (2024). "Exploration of heterogeneous catalyst for molecular hydrogen ortho-para conversion"
DOI:10.1002/EXP.20230040
AI要約(翻訳):本研究は、分子状水素のオルト−パラ変換を促進するための不均一触媒の探索を行ったものである。水素分子のスピン異性体変換は低温環境で重要な役割を果たし、効率的な触媒の開発が求められている。複数の金属酸化物や複合材料を候補として評価し、変換速度や安定性を比較した。結果として、特定の酸化物触媒が高い活性を示し、長時間の反応でも性能を維持できることが確認された。さらに、触媒表面の電子状態解析により、変換機構の理解が進展した。この成果は、液体水素の貯蔵や輸送における効率向上に寄与し、エネルギー分野での応用が期待される。加えて、触媒設計の新たな指針を提供し、持続可能な水素社会の実現に貢献する可能性がある。
Dipak Patel*, Akiyoshi Matsumoto*, Hiroaki Kumakura, Yuka Hara, Toru Hara, Minoru Maeda, Hao Liang, Yusuke Yamauchi, Seyong Choi, Jung Ho Kim, Md Shahriar A. Hossain, Journal of Magnesium and Alloys 12, 159-170 (2024). "Superconducting joints using reacted multifilament MgB2 wires: A technology toward cryogen-free MRI magnets"
DOI:10.1016/j.jma.2023.11.014
AI要約(翻訳):本研究は、反応済み多フィラメントMgB2線材を用いた超伝導接続技術を開発し、冷媒不要型MRI磁石への応用可能性を検討したものである。接続部の形成過程を最適化することで、臨界電流密度を維持しつつ低抵抗のジョイントを実現した。接続部の微細構造を解析し、フィラメント間の結合状態と電気特性の相関を明らかにした。さらに、液体ヘリウムを用いない冷却環境下でも安定した動作が確認され、MRI装置の低コスト化と持続可能性に寄与する技術として期待される。この成果は、医療分野における次世代超伝導磁石の開発に重要な役割を果たす。加えて、長期信頼性や量産性の観点からも有望であり、臨床応用に向けた基盤技術として位置付けられる。
Emanuela Barzi*, Daniele Turrioni, Ibrahim Kesgin, Masaki Takeuchi, Wang Xudong, Tatsushi Nakamoto, Akihiro Kikuchi, SUPERCONDUCTOR SCIENCE & TECHNOLOGY 37, 045008-1-045008-10 (2024). "A new ductile, tougher resin for impregnation of superconducting magnets"
DOI:10.1088/1361-6668/ad2c25
AI要約(翻訳):本研究は、超伝導磁石の含浸に用いる新しい延性かつ高靭性の樹脂を開発し、その性能を評価したものである。従来の樹脂は硬化後に脆性が高く、機械的応力や熱サイクルにより亀裂が発生しやすい問題があった。新樹脂は分子設計の工夫により柔軟性と強度を両立し、含浸後のコイルにおいて高い耐久性を示した。実験では、機械的試験と熱サイクル試験を行い、従来樹脂と比較して破壊靭性が大幅に向上していることを確認した。さらに、電気的絶縁性や加工適性も良好であり、製造工程における扱いやすさが改善された。この成果は、次世代超伝導磁石の信頼性向上に寄与し、核融合炉や高エネルギー加速器などの応用において重要な役割を果たすと期待される。
Hiroshi Ueda*, Ryota Komae, Aoi Yamashita, Ryota Inoue, SeokBeom Kim, So Noguchi, IEEE TRANSACTIONS ON APPLIED SUPERCONDUCTIVITY 34, 4400805-1-4400805-5 (2024). "Experiment and simulation on mechanical behavior in 1/2-scale demonstration REBCO coil system of Skeleton Cyclotron for cancer therapy"
DOI:10.1109/TASC.2023.3338151
AI要約(翻訳):本研究は、がん治療用スケルトンサイクロトロンに向けた1/2スケールREBCOコイルシステムの機械的挙動を、実験とシミュレーションの両面から解析したものである。コイルに作用する電磁力や熱応力を模擬し、変形や応力分布を評価した。実験では、試作コイルを用いて荷重試験を行い、シミュレーション結果と比較することでモデルの妥当性を検証した。結果として、REBCOコイルは高い機械的安定性を示し、臨床応用に必要な耐久性を備えていることが確認された。さらに、設計条件の最適化により、応力集中を緩和し長期信頼性を確保できることが示された。この成果は、医療用超伝導加速器の開発において重要な基盤技術となり、次世代がん治療装置の実現に寄与するものである。
Rui Kumagai, Atsushi Ishiyama*, Hiroshi Ueda, So Noguchi, Tomonori Watanabe, Mitsuhiro Fukuda, Gen Nishijima, Jun Yoshida, IEEE TRANSACTIONS ON APPLIED SUPERCONDUCTIVITY 34, 4400705-1-4400705-5 (2024). "Fabrication and Experiments on a 1/2-Scale Demonstration NI-REBCO Coil System of a Skeleton Cyclotron for Cancer Therapy"
DOI:10.1109/TASC.2023.3338594
AI要約(翻訳):本研究は、がん治療用スケルトンサイクロトロンに向けた1/2スケール無絶縁(NI)REBCOコイルシステムの製作と実験評価を行ったものである。NI構造は自己保護機能を持ち、過電流時の安全性を高める利点がある。試作コイルを製造し、通電試験や磁場特性測定を実施した結果、安定した動作と高い臨界電流密度が確認された。さらに、冷却効率や電流分布の均一性も良好であり、医療用加速器に必要な性能を満たしていることが示された。実験結果は、システム設計の最適化に有用な知見を提供し、臨床応用に向けた信頼性評価に寄与するものである。NI-REBCO技術は、次世代がん治療装置の開発において重要な役割を果たすと期待される。
Mukesh Dhakarwal*, Masami Iio, Kento Suzuki, Makoto Yoshida, Tatsushi Nakamoto, Toru Ogitsu, Michinaka Sugano, Kiyosumi Tsuchiya, Xudong Wang, Ramesh Gupta, Tengming Shen, Ye Yang, Gen Nishijima, IEEE TRANSACTIONS ON APPLIED SUPERCONDUCTIVITY 34, 1-5 (2024). "Development and Testing of HTS Coil With Ceramic Coated REBCO Conductor for High Radiation Tolerance"
DOI:10.1109/TASC.2024.3365090
AI要約(翻訳):本研究は、高放射線環境下での耐久性を高めるために、セラミックコーティングを施したREBCO導体を用いた高温超伝導(HTS)コイルの開発と試験を行ったものである。従来のREBCO導体は放射線照射による劣化が課題であったが、セラミック層の導入により機械的強度と耐放射線性が向上した。試作コイルを製造し、臨界電流密度や磁場特性を評価した結果、照射後も安定した性能を維持できることが確認された。さらに、熱サイクル試験や長時間運転試験を通じて、信頼性の高さが実証された。この成果は、核融合炉や高エネルギー加速器など強放射線環境で使用される次世代超伝導磁石の設計に重要な知見を提供し、長期運用における安全性と効率性の向上に寄与するものである。
Gen Nishijima*, Koji Kamiya, IEEE TRANSACTIONS ON APPLIED SUPERCONDUCTIVITY 34, 1-5 (2024). "Test Results of Conduction-Cooled Bi-2223 Magnet With Shield Coils at Both Ends"
DOI:10.1109/TASC.2024.3358254
AI要約(翻訳):本研究は、両端にシールドコイルを配置したBi2Sr2Ca2Cu3O10(Bi-2223)超伝導磁石を伝導冷却方式で試験した結果を報告している。シールドコイルは主磁場の端部効果を抑制し、磁場分布の均一性を改善する役割を果たす。試験では、液体ヘリウムを用いず冷凍機による伝導冷却を採用し、臨界電流や磁場安定性を評価した。結果として、シールドコイルの導入により磁場の均一性が向上し、安定した動作が確認された。さらに、長時間運転試験においても性能劣化は見られず、伝導冷却方式の有効性が示された。この成果は、低温冷却コストを削減しつつ高性能を維持できる超伝導磁石の設計に有用であり、医療用MRIや加速器応用における展開が期待される。