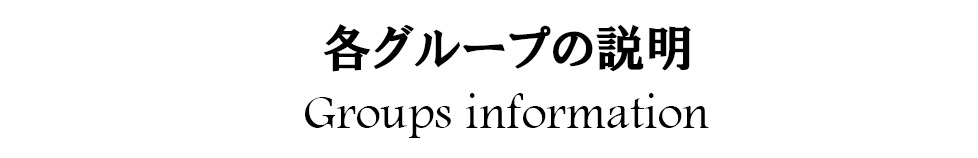先端解析分野
電子顕微鏡グループ (GL: 木本 浩司)

最先端の材料開発や実用材料の性能評価のためには、物質の極微細構造を知る必要があります。本研究グループでは、球面収差補正装置やモノクロメーター、電子エネルギー損失分光法などの最先端電子顕微鏡手法自体を研究開発するとともに、先端材料の評価へ応用しています。独自の計測・解析用ソフトウエアやハードウエアの改造などを行い、従来技術では計測困難な分析もできるように研究開発を行っています。大学・企業とも積極的に連携して研究を進めています。
(グループのページへ)
先端解析分野
実働環境電子顕微鏡開発グループ (GL: 三石 和貴)

試料に外部から与えられた刺激に対し、試料がどのように反応するかを動的に観察する「その場観察技術」は、材料の研究に大変有効です。特に最近では機能を持った材料やデバイスが、実際にその機能を発現し動作している状況を観察する、“実働環境計測”が世界的に盛んにおこなわれています。しかしながら、電子顕微鏡での実働環境計測では電子顕微鏡観察を行う事からくる様々な制約があり、観察目的ごとに様々な工夫を行う必要があります。
本研究グループでは材料の実働環境計測をターゲットとし、これまで培ってきた電圧印加、ガス環境、液中観察などの実働環境計測法の更なる高度化ともに、大量データ取得と得られたデータの情報理論を用いた処理により、材料の観察によるダメージを抑えた観察手法の開発など電顕手法自体の高度化を行い、より高度で適用範囲の広い実働環境計測を実現することで、NIMSの材料研究者を始めとした材料研究全般に貢献していく事を目的としています。
(詳細ページへ)
先端解析分野
ナノプローブグループ (GL: 川井 茂樹)

表面の構造や状態を実空間かつ超高分解能で計測できる走査型プローブ顕微鏡は、今日のナノサイエンスを支える重要な計測装置である。ナノプローブグループでは、超高真空・極低温・磁場中といった極限環境から雰囲気を制御した室温まで、様々な環境で動作する最先端の原子間力顕微鏡や走査型トンネル顕微鏡を開発しています。また、それらを用いた表面化学や表面物理の基礎学理を探究するとともに、電池材料などのオペランド電位計測技術を開発し、ナノ・量子・環境・エネルギー材料の開発に寄与することを目指しています。
(詳細ページへ)
先端解析分野
固体NMRグループ (GL: 後藤 敦 )

固体NMRグループでは、電池、半導体、触媒、ポリマーなどの重要材料の性能向上や、固体表面での酸素・水素分子の反応機構の解明などの重要課題の解決に資するため、材料研究者との連携のもと、NIMSの持つ強磁場NMRや量子計測等の技術・装置を活用して材料分析を進めています。また、その基盤技術として、高温・実働環境・光照射下などの様々な環境下で稼働する固体NMR技術や、表面化学反応を計測する量子計測技術の開発、さらには、量子化学計算やデータ科学との融合によるデータ解析の高度化にも取り組んでいます。
(詳細ページへ)
先端解析分野
光電子分光グループ (GL: 矢治 光一郎)

材料の電気的性質や磁気的性質はその中を運動する電子によって決まります。したがって、材料の機能発現の鍵となる電子の振る舞いを明らかにすることは新規材料開拓やデバイス設計において極めて重要です。私たちはスピンも含めた電子状態を精密計測できるスピン角度分解光電子分光や電場印加化における顕微光電子分光を利用して材料の定常状態や動作環境における電子状態を計測しています。最近では、量子マテリアルや磁性材料の電子状態の評価が重要な研究テーマとなっております。
(詳細ページへ)
先端解析分野
強磁場物性計測グループ (GL: 今中 康貴)

新規物質・新材料の研究においては、電気的、光学的、磁気的性質といった物質の基本的な性質を明らかにすることは非常に重要です。そのためには試料の高品質化が基本的には求められますが、同時に強い磁場や低い温度のような極端な環境下での計測も物質の特性を顕わにする上で非常に強力な手段となります。
強磁場計測グループでは、磁気冷凍材料はじめとする機能性新材料の特性を詳細に調べるために、様々な「強磁場下物性計測技術」の開発を行っています。また20テスラを超える磁場が発生可能な「強磁場磁石」の開発も行っており、様々な物質・材料の特徴ある性質 (物性) を多面的に明らかにしています。
(詳細ページへ)
先端解析分野
量子ビーム回折グループ (GL: 小原 真司)

材料がなぜ機能を発現するかを知るために最初に行うことはその原子配列を調べることです。私たちは、高輝度放射光X線を用いた回折実験を軸に、様々な量子ビームを駆使した実験および解析技術の開発を行います。また、計測インフォマティクスや人工知能を導入することによりハイスループット計測・解析を実現し、得られた結果をデータベース化することを試みます。さらに、それらに基づいた自律的な計測・予測・材料合成の循環システムの構築を目指し、物質・材料研究を加速させることを試みます。対象となる材料は原子の配列が規則的である結晶材料から原子配列の規則性に乏しいアモルファス材料や液体まで幅広く扱います。
(詳細ページへ)
先端解析分野
放射光イメージンググループ (GL: 山崎 裕一)

本グループでは、スピントロニクスデバイスや磁性量子デバイス材料の磁気構造や電子状態の解明を通じて特性や創発物性の起源解明を目指しています。特に、放射光のパルス特性と高い空間分解能を組み合わせた装置開発を推進し、ナノスケールの磁気構造ダイナミクスの観測手法を開拓しています。反強磁性体材料の可視化手法や共鳴X線散乱による電子状態観測など、放射光計測技術を多角的活用して物質・材料研究を行っています。また、計測限界を突破するための革新的な計測インフォマティクス解析技術の開発も行っています。
(詳細ページへ)
材料設計分野
データ駆動型無機材料グループ (GL: 徐 一斌)

自然科学は、実験データから見いだされた物理と化学の法則を出発点として発展してきた。マテリアルズ・インフォマティクス (MI) は、従来の紙などの記録メディアをはるかに超えたデータ蓄積能力と、人間より優れたデータ処理能力を有するコンピュータシステムを用いて、これまで、および、これからの材料データを最大限に蓄積し、人工知能によりパターンや法則を見つけることによって、新材料の設計と開発の時間短縮とコストダウンを目指す研究手法である。
本グループは、文献、実験、計算から無機材料の化学組成や、結晶構造、組織、特性などのデータを収集し、MIの手法を用いて、材料の特性と機能を支配する物理と化学要因を特定し、革新的な無機材料の設計と創出を目指している。
(詳細ページへ)
材料設計分野
データ駆動型材料設計グループ (GL: 袖山 慶太郎)

データ駆動型手法を用いた、本当に使える新しい材料の探索が求められています。本研究グループでは、データ科学、計算科学、理論科学、さらにNIMS内外からの実験データを融合することで、新しい材料設計の仕組みを構築するとともに、実験研究者と協働で新規材料を合成、評価していきます。そのために必要なマテリアルズ・インフォマティクスの手法開発や計算データの蓄積、材料系ごとの利用ノウハウの蓄積をしていきます。
(詳細ページへ)
材料設計分野
材料モデリンググループ (GL: 出村 雅彦)

材料は、プロセス、構造、特性、性能の4つの要素の連関を明らかにしながら開発していきます。私たち材料モデリンググループでは、材料工学の4要素をつなぐモデリング技術を研究します。
モデリング技術によって、実験を計算に置き換え、プロセスから構造、特性を経て、性能を予測する順問題の解析を高速化していきます。そして、順方向の解析手法を確立できれば、AIによる最適化アルゴリズムと組み合わせて、ほしい性能から最適な材料・プロセスをデザインする逆問題を解くことができるようになります。
このような計算機上での材料設計は、「マテリアルズインテグレーション」というコンセプトで提案され、内閣府SIP「革新的構造材料」・「マテリアル革命」においてMIntというシステムに具現化しています。
我々は、マテリアルズインテグレーションのコンセプトを基盤として、さまざまな材料課題において、モデリングによる順問題の解析、逆問題による新しい材料・プロセスの提案を行っていきます。
(詳細ページへ)
材料設計分野
材料科学計算基盤グループ (GL: 東後 篤史)

コード開発で科学する
第一原理量子モンテカルロ計算、フォノン計算、フォノン間相互作用計算、電子・フォノン相互作用計算に関する研究および科学ソフトウエア開発を行っています。
科学計算ソフトウエア開発と計算自動化
私たちは科学計算ソフトウエアを開発し、計算機シミュレーションを行うことで、材料の研究をしています。また、計算機シミュレーションの自動実行環境を構築し、計算材料データの蓄積を行っています。
(詳細ページへ)
材料設計分野
データ駆動型アルゴリズムチーム (GL: 田村 亮)

データサイエンスで材料研究に革新を
データ駆動型アルゴリズムチームでは、データ駆動型材料研究開発を加速するための「材料データに特化したデータ駆動型アルゴリズム・ツール」を開発しています。そして、それを用いた応用研究をNIMS内外の実験グループと共同で実施しています。材料研究のニーズは多岐にわたっているため、研究ごとに扱うデータが変わります。そのため、各論的に適したアルゴリズムを開発・最適化し、それを利用することで初めて真のデータ駆動型材料研究開発が可能となると考えています。
(詳細ページへ)