- ホーム
- > アウトリーチ
- > 刊行物
- > CONVERGENCE
- > LEADER'S VOICE
 LEADER'S VOICE
LEADER'S VOICE
西義雄 教授に聞く
真摯な姿勢で人類の未来に貢献を

英語公用化は国際化に必須
——WPI-MANAの発展を先生はどのようにご覧になりますか?
色々な紆余曲折がありましたが、全体として言えば非常な進展がありました。材料開発、またそれに基づく新しい分野での先端的な探索研究といったMANAの活動そのものが、ナノサイエンスという学問の進歩に対して大変寄与しました。また、MANAの中で育ってきた、例えば「原子スイッチ」といった研究成果を「脳型コンピュータ」のようなシステムに実際に応用できるのか、その可能性を検証しようというレベルまで成長を遂げました。我々スタンフォードの側から見ても、よい仕事をしておられるな、と感じています。西欧やアメリカから優秀な研究者を呼ぶという意味では、英語公用化も絶大な効果がありました。
——海外の優秀な研究者の招聘は、日本では今でも大きな課題のようです。
やはり言語の問題が大きいですね。私の学生達を見ましても、素晴らしい研究能力を持っている組織同士の比較となると、そこに自分を置いた時に研究生活上で必要な手続きを何語でやれるのか、ということを問題にします。例えば、部品の取り寄せだとか、学会へ行くための新幹線の予約だとか、それを英語で進められるなら、合格です。
ただ私は正直なところ、だいたいの人が英語をしゃべって研究者同士のやりとりには問題がないというレベルではまだ不便に感じます。例えばパソコンの調子が悪くて誰かに助けてもらいたい時、修理する人は英語をしゃべれたとしても、現地語を介さないとその人に辿りつけないといったことがままあります。そういう些細なことで時間をロスすると、たとえ数日であったとしても、それが積もり積もると大きなロスになり、研究生活全体に支障が出ます。言語の障害というのは、日本に住んでおられる日本人が考える以上に遥かに高い、ということを認識するのが大事だと思います。
色々な紆余曲折がありましたが、全体として言えば非常な進展がありました。材料開発、またそれに基づく新しい分野での先端的な探索研究といったMANAの活動そのものが、ナノサイエンスという学問の進歩に対して大変寄与しました。また、MANAの中で育ってきた、例えば「原子スイッチ」といった研究成果を「脳型コンピュータ」のようなシステムに実際に応用できるのか、その可能性を検証しようというレベルまで成長を遂げました。我々スタンフォードの側から見ても、よい仕事をしておられるな、と感じています。西欧やアメリカから優秀な研究者を呼ぶという意味では、英語公用化も絶大な効果がありました。
——海外の優秀な研究者の招聘は、日本では今でも大きな課題のようです。
やはり言語の問題が大きいですね。私の学生達を見ましても、素晴らしい研究能力を持っている組織同士の比較となると、そこに自分を置いた時に研究生活上で必要な手続きを何語でやれるのか、ということを問題にします。例えば、部品の取り寄せだとか、学会へ行くための新幹線の予約だとか、それを英語で進められるなら、合格です。
ただ私は正直なところ、だいたいの人が英語をしゃべって研究者同士のやりとりには問題がないというレベルではまだ不便に感じます。例えばパソコンの調子が悪くて誰かに助けてもらいたい時、修理する人は英語をしゃべれたとしても、現地語を介さないとその人に辿りつけないといったことがままあります。そういう些細なことで時間をロスすると、たとえ数日であったとしても、それが積もり積もると大きなロスになり、研究生活全体に支障が出ます。言語の障害というのは、日本に住んでおられる日本人が考える以上に遥かに高い、ということを認識するのが大事だと思います。
材料研究を通じた社会への貢献
——先生は渡米されて28年目になるとのことですが、ご自身のお仕事について教えていただけますでしょうか?
アメリカには定年制度がありませんので、ずっと100%現役です。今私の研究室に博士課程の学生が11人おりま
すが、その連中と年中議論して、同時に講義をやってと。常に研究と教育のバランスを取ってやっていくのが私の信条です。
この数年は、不揮発性抵抗変化メモリの開発に取り組んでいます。例えば遷移金属酸化物の中に、組成比が特定の比に保たれず、酸素の空孔ができてしまう場合があります。
そうしますと、その周りの金属原子で軌道電子の雲が互いに重なり合って、本来は絶縁体だったその酸化物が、電気を通すようになるのです。そのふるまいを理論計算で調べたり、実験的にも予測通りになっているかを確かめたり、といった研究をしています。
この系統の仕事、つまり2つの違った物質が適当に混ざり合った時にどうなるかという問題には、東芝時代から
取り組んでいます。シリコンのトランジスタで、シリコンとその表面のシリコン酸化物との界面に酸素の空孔が生じるとその空孔に電子がトラップされるという現象を、私は世界で最初に電子スピン共鳴吸収測定により見つけました。原子の未結合手のふるまいの探求は、言ってみれば私のライフワークみたいなものです。
——先生ご自身の研究の行き先と、社会とのつながりについてはどうお考えですか。
一番大きなつながりと言いますと、人が必要とする色々なデータの蓄積ですね。よく話題になるビッグデータやデータセントラルなどにも、基本的には従来の電荷蓄積型メモリが山のように入っていますが、その方式にはもう限界が来ています。しかし、電気伝導度を変化させられる物質を用いて、電気が流れるか流れないかを情報として記憶できるような仕組みを確立できれば、桁違いに消費電力が小さく、読み出し速度が高速という抵抗変化メモリを実現できるのです。
世の中のあらゆるところのさまざまな状態量をセンサーで感知し、センサーが取ってくるデータを蓄積する。そんなシステムができれば、それを基にして、例えば長期天気予報だとか環境モニタリングだとか医療データモニターと集積など、集めたデータを人類我らのために広く役立てる、という段階に進むことができます。
アメリカには定年制度がありませんので、ずっと100%現役です。今私の研究室に博士課程の学生が11人おりま
すが、その連中と年中議論して、同時に講義をやってと。常に研究と教育のバランスを取ってやっていくのが私の信条です。
この数年は、不揮発性抵抗変化メモリの開発に取り組んでいます。例えば遷移金属酸化物の中に、組成比が特定の比に保たれず、酸素の空孔ができてしまう場合があります。
そうしますと、その周りの金属原子で軌道電子の雲が互いに重なり合って、本来は絶縁体だったその酸化物が、電気を通すようになるのです。そのふるまいを理論計算で調べたり、実験的にも予測通りになっているかを確かめたり、といった研究をしています。
この系統の仕事、つまり2つの違った物質が適当に混ざり合った時にどうなるかという問題には、東芝時代から
取り組んでいます。シリコンのトランジスタで、シリコンとその表面のシリコン酸化物との界面に酸素の空孔が生じるとその空孔に電子がトラップされるという現象を、私は世界で最初に電子スピン共鳴吸収測定により見つけました。原子の未結合手のふるまいの探求は、言ってみれば私のライフワークみたいなものです。
——先生ご自身の研究の行き先と、社会とのつながりについてはどうお考えですか。
一番大きなつながりと言いますと、人が必要とする色々なデータの蓄積ですね。よく話題になるビッグデータやデータセントラルなどにも、基本的には従来の電荷蓄積型メモリが山のように入っていますが、その方式にはもう限界が来ています。しかし、電気伝導度を変化させられる物質を用いて、電気が流れるか流れないかを情報として記憶できるような仕組みを確立できれば、桁違いに消費電力が小さく、読み出し速度が高速という抵抗変化メモリを実現できるのです。
世の中のあらゆるところのさまざまな状態量をセンサーで感知し、センサーが取ってくるデータを蓄積する。そんなシステムができれば、それを基にして、例えば長期天気予報だとか環境モニタリングだとか医療データモニターと集積など、集めたデータを人類我らのために広く役立てる、という段階に進むことができます。
「人格」と「チームワーク力」
——スタンフォード大学での人材育成の強みを教えていただけますか?
個々の研究者間の、あるいは研究室間のバリアが日本ではかなり高いようですが、アメリカ、特にスタンフォードにはそういうものが殆どないのです。私の研究室の内輪の議論の中に他の教授の学生が入ってきても歓迎ですし、その逆も然り、別に私に仁義を切る必要も全くありません。
また、ドクターコースの学生1名当たりに主従の指導教官計3名が付くのですが、その人選も同じ学部どころか、同じ大学の中からである必要すらありません。学生が研究をやっている内に知識を広げたくなった時には、学生自身がその分野でよい仕事をしている人のところに行って指導を請います。ドクターはたこつぼ型の専門家ではなく、横の広がりも十分持っていると…。そういう育て方を我々は心がけていまして、実際学生はそう育ってきます。
ですから、そういう環境がMANAにもあって、例えば、MANA以外のNIMSの誰かとか、あるいは他所の大学の誰かとかと一緒に研究をしたい時に、いちいち上司に断らずにどんどんやれるというぐらいの、横の連携があると非常にいいなと思いますね。
——そうやって優秀な若い方々を育てるために、先生はどういうことを意識されていますか?
大学にいる間は基本的には個人プレーですが、そういうのと違う価値基準が世の中にはあるよ、と伝えてい
ます。君の研究能力を疑う人はいないだろうけれど、何を疑うかっていうと、第一にあなたの人格(human
integrity)がどうかということ。それから同等に大事なのが、チームの中で仕事をすることに意欲的であるかどうか。往々にして、トップクラスの大学を出てきたがため、なかなか皆と一緒に何かをやろうという姿勢を出せない者がいます。
企業人だけではなく大学教授になる場合も同じです。学生が求職をする際、先方が私に照会をして来るので
すが、その時に聞かれる極めての質問は、今言った「人格」と「チームワーク力」、やっぱりこの2つですね。
個々の研究者間の、あるいは研究室間のバリアが日本ではかなり高いようですが、アメリカ、特にスタンフォードにはそういうものが殆どないのです。私の研究室の内輪の議論の中に他の教授の学生が入ってきても歓迎ですし、その逆も然り、別に私に仁義を切る必要も全くありません。
また、ドクターコースの学生1名当たりに主従の指導教官計3名が付くのですが、その人選も同じ学部どころか、同じ大学の中からである必要すらありません。学生が研究をやっている内に知識を広げたくなった時には、学生自身がその分野でよい仕事をしている人のところに行って指導を請います。ドクターはたこつぼ型の専門家ではなく、横の広がりも十分持っていると…。そういう育て方を我々は心がけていまして、実際学生はそう育ってきます。
ですから、そういう環境がMANAにもあって、例えば、MANA以外のNIMSの誰かとか、あるいは他所の大学の誰かとかと一緒に研究をしたい時に、いちいち上司に断らずにどんどんやれるというぐらいの、横の連携があると非常にいいなと思いますね。
——そうやって優秀な若い方々を育てるために、先生はどういうことを意識されていますか?
大学にいる間は基本的には個人プレーですが、そういうのと違う価値基準が世の中にはあるよ、と伝えてい
ます。君の研究能力を疑う人はいないだろうけれど、何を疑うかっていうと、第一にあなたの人格(human
integrity)がどうかということ。それから同等に大事なのが、チームの中で仕事をすることに意欲的であるかどうか。往々にして、トップクラスの大学を出てきたがため、なかなか皆と一緒に何かをやろうという姿勢を出せない者がいます。
企業人だけではなく大学教授になる場合も同じです。学生が求職をする際、先方が私に照会をして来るので
すが、その時に聞かれる極めての質問は、今言った「人格」と「チームワーク力」、やっぱりこの2つですね。
Honor codeをもった研究者が未来を創る
——先生は、これからのナノテクノロジーの研究の方向性を、どのようにご覧になりますか。ナノテクノロジーは人類をよい方向に導くのでしょうか。
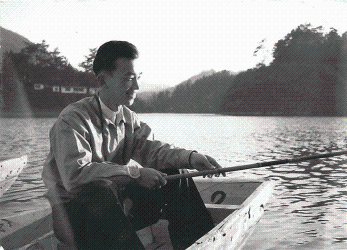
若き日の西先生
まず一番には、個々の研究が未来の社会にどう寄与していくか、だと思います。研究者が個々に考えておられるはずではありますが、そうした視点をもっと明示的に表現できることがMANAにおいても必要でしょう。自分が進めている研究がマクロな視野から見た時に、どういう位置を占めるか。それを三次元空間的であると同時に、時間軸も考慮して考えられたらと。そういう中で不幸にして先の展開が望めないという場合に、例えば潔くやめて次へという判断を下すのは、研究の管理者ではなく、研究者自身であるべきです。自分で自分の運命を決めるための色々な基準を常に自分の中で考えていくことが、やっぱり大切だと思います。
私にとっての一般論で言えば、ナノテクノロジーは必ず人類に寄与していくと思います。例えば医療分野や環境分野など。ただし、技術というものは、純粋な科学と違って、どう使う、あるいはどう使われるかが問題ですね。ただ我々の社会は、人によって違う意見もあるとは思うのですが、基本的には性善論でないといけない、と
いうのが私の信念なのです。我々は‘honor code’(規律、倫理規定)と言っているのですが、欧米には、人間
が自分の倫理、あるいはプライドに照らしてやるべきことは必ずやる、という姿勢を評価する風土があります。私はそういう意味ではまさに性善説に立ちたいですし、そうした志が科学や技術の行く先でどう社会に貢献していくかを考えて行きたいです。人類の未来、それは決して人のせいにはできないものではないでしょうか。
私にとっての一般論で言えば、ナノテクノロジーは必ず人類に寄与していくと思います。例えば医療分野や環境分野など。ただし、技術というものは、純粋な科学と違って、どう使う、あるいはどう使われるかが問題ですね。ただ我々の社会は、人によって違う意見もあるとは思うのですが、基本的には性善論でないといけない、と
いうのが私の信念なのです。我々は‘honor code’(規律、倫理規定)と言っているのですが、欧米には、人間
が自分の倫理、あるいはプライドに照らしてやるべきことは必ずやる、という姿勢を評価する風土があります。私はそういう意味ではまさに性善説に立ちたいですし、そうした志が科学や技術の行く先でどう社会に貢献していくかを考えて行きたいです。人類の未来、それは決して人のせいにはできないものではないでしょうか。

西義雄 教授
スタンフォード大学電気工学科教授
スタンフォード大学電気工学科教授
東京大学において博士課程修了後、1962年に東芝に入社しシリコンCMOSデバイス開発に従事。1986年よりのヒューレットパッカード勤務後、1995年テキサスインスツルメンツ上級副社長兼研究開発部長。2002年スタンフォード大学に招聘され学界に転身。専門は半導体デバイスの物理・工学。1987年よりIEEEフェロー、2002年 Robert Noyce Medal等、受賞歴多数。MANA評価委員会メンバー。

