
融合研究がもたらしたもの
新しい演算機構開拓を照らす「スター」な有機材料
若山裕 ナノアーキテクトニクス材料研究センター
量子材料分野 量子デバイス工学グループ グループリーダー
相見順子 高分子・バイオ材料研究センター
高分子材料分野 分子メカトロニクスグループ 主任研究員
研究分野を大きく超え、領域外の研究者とひとつの研究をおこなうMANAの「融合研究プログラム」。MANA量子デバイス工学グループの若山裕と、高分子・バイオ材料研究センターで高分子材料を扱う相見順子は、ナノ物理工学と高分子化学というかけ離れた研究を行っていた。
しかし、ひとつの有機高分子材料である「スターポリマー」をそれぞれの視点から見ることで、互いの研究が大きく前進したと感じている。
機能性ポリマーを有機デバイスに用いる
2021年の中央大学。NIMSの研究員による連続講義で若山は自分の次に行われた講義を熱心に聴いていた。それは、同じNIMSの相見順子によるもので、彼女がずっと研究している機能性ポリマーのひとつ、「スターポリマー」についての講義だった。
若山は以前から論文1)などでこのスターポリマーの存在を知っており、気にはなっていたが、相見の講義を実際に聴講して、これは使える、と確信した。そこで、講義後に「MANAの融合研究プログラムを使って共同研究をやってみないか」と提案をした。若山はこの研究が、何に使えると思ったのか。
相見は一貫して機能性ポリマー(高分子)の精密合成を研究している。有機化合物に特定の機能を持たせるブロックコポリマー(2種以上のモノマー(分子)による重合によって合成される高分子)を様々につくっており、特に新規エレクトロニクス材料開発を目指していた。そのひとつが、スターポリマーである。
一方の若山は「電子デバイスの研究をメインでやっていますが、扱う材料はずっと有機材料。そのおもしろさは、いろんな分子を自在に合成できるところにつきます」という。電子デバイスの作製という観点から有機材料に長くアプローチしてきた彼は、このスターポリマーが新規メモリ材料に使えるのでは、と思ったのだ。
スターポリマーのユニークさ

若山の提案は相見の快諾を得て、MANA独自のプログラムである融合研究として申請し、採択された。化学研究の相見と、物理を専門とする若山の融合研究は、まさにこのプログラムの目的である「異分野の融合」だ。
「プロポーザルを書いて審査を受け、予算や期限がつくというのは、単なる共同研究よりも明確なインセンティブになる」(若山)
相見は自らが合成したスターポリマーを提供し、若山はそれが電子デバイスとしてどのように有効かを検証し、二人はディスカッションを定期的におこなっていった。
スターポリマーについて少し詳しく見ていこう。モノマーを繋ぎ合わせた紐状のポリマーを利用して、様々なかたちを作ることができる。例えばリングのようなものやブラシのようなものなどがある。その流れで星のようなかたちのポリマーを相見は作った。星の手にあたる部分が同じ長さなので、星のように見える。この星の、真ん中部分に量子ドットがあり、電荷を「囲う」ことができるのだ。
「それぞれのポリマーがきれいに星形になることで、中心にある量子ドット同士が均一に分散する。似た例は世界にあることはあるけれど、これほどきれいにできるのは非常に少ない。ナノサイズの量子ドットを同じ大きさにつくることは非常に難しく、ちょっとずつかたちや大きさ、原子数がちがってくる。ところが有機材料であるスターポリマーでは、原子レベルですべて同じにすることができる。それをデバイスに使うことができたのが非常におもしろい」(若山)
「スターポリマーは、フタロシアニン分子がポリスチレンで覆われた構造で、溶液に溶かして基板に塗るだけで絶縁体中に電荷トラップ部位が浮遊(フロート)した、フローティングゲートのような構造になります。わたしは高分子のデザインを作り込むのが好きで、その機能を異なる分野で効果的に活用する方法を探求しています。そのバトンがうまく渡せたのが今回の融合研究だと思います」(相見)
若山は長年、有機エレクトロニクスの開発に注力している。その長所である機械的な柔らかさ(フレキシビリティ)を活かす電子素子を開発するためには、メモリ機能も有機系材料で賄う必要があった。メモリ機能も単なる記録媒体ではなく、ロジックインメモリ2)やニューロモルフィック素子3)など、次世代素子をやわらかくするために、相見の研究はうってつけだったのだ。
「今までも有機材料の研究者から、材料測定などを頼まれることはあったが十中八九うまくいかなかった。その中で、このスターポリマーは非常に優秀な結果を残すことができました」(若山)
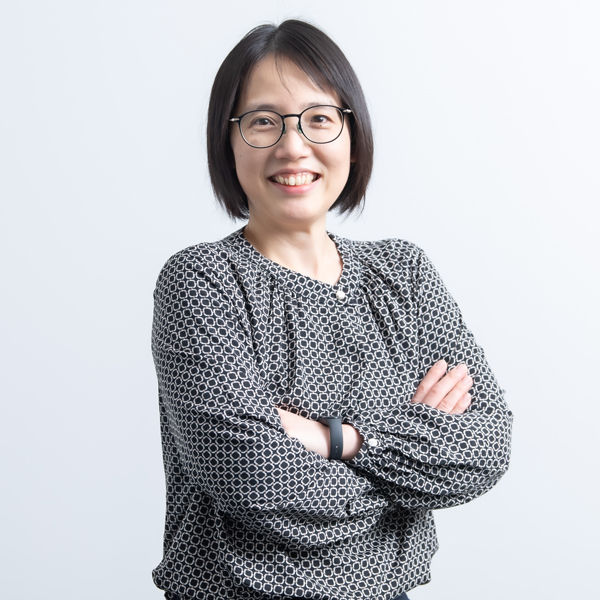
物理工学にとっては意外な発見は、高分子化学で説明がつく
実は当初、スターポリマーはメモリとして必ずしも完璧なものではなかった。主たる機能である書き込みと消し込みを、どのようにコントロールするかという課題が残っていたのだ。それを解決したのは一人のポスドクだった。通常メモリは電圧で書き消しが行われるが、そこに光と電圧、ふたつの入力値を組み合わせる実験をおこなったのだ。しかもその光の波長を変えることによって、書くときには短い波長、消すときには長い波長を用いると、うまく制御できることが検証された。
「ポスドクがおもしろいことやっているな、何でそんなこと思いついたの、って思って見ていた。実際やってみればなるほど、波長によるエネルギー量が違うのでうまくいくんだ、と合点が行った」(若山)
「スターポリマーの中心にあるフタロシアニン分子は色素材料なので、光を吸収します。それまではプラスの電子は溜められるけれど、マイナスは溜められないと思っていた。いまではプラスもマイナスも溜めることができます」(相見)
このポスドクであるDebdatta Panigrahi氏は論文の共著者にもなり、現在はドイツで研究をおこなっているという。

気づきから、新しいアプローチを探っていく未来へ
ふたりの融合研究は最終的に3本の論文[1-3]にまとめられた。相見は論文になるまでのスピード感が印象に残っているという。
「最初のスターポリマーを有機メモリに利用する論文は1年以上かかりました。それが、材料の性質やデバイス化などのプロセスがわかっていたので、すぐ実験が出来、すぐデータがでる」(相見)
「たしかに意外と早くデータがでた。データがでるとドラフトをすぐに書き、それをふたりで練り上げて行く作業でしたね。22年と23年に分けて合計3本の論文になりました」(若山)
論文を出してから、周囲の受け止めはどうだったのか。
「学会発表すると必ず質問を受けますね(笑)。どうやってこの材料をつくったんだ、と。わたしの研究分野では非常に注目が高いです」(若山)
「わたしは自分で育ててきたポリマーが人に認められた、という感じがありました。もちろん領域内で自分への評価はありましたが、他の研究領域で、しかも実デバイスへの応用に自分の機能性ポリマーが注目されているというのを聞くと、今までの評価とはまた違った認められ方をしたとうれしかったですね」(相見)
融合研究プログラムは最終的に2年間で終わった。しかし、ふたりの共同研究はまだ続いていくという。
「実は細かく克服する課題もあります。ポリマーの膜の性質とか、有機半導体との相性とか。ポリマーがよくてもこんどは実デバイスへのプロセスの段階に来ている。そこはやはりハードルが高い。もしかしたら今までとは別のアプローチをした方がいいかもしれない。ものづくりのプロセスがあって設計やデータがでて、それをポリマーのデザインにフィードバックする。そうしたやり方が理想かなと思っています」(相見)
「スターポリマー自体はたしかにやり尽くした感がある。新規の演算機構開拓というわたしの研究の基本に立ち返ると、機能性ポリマーを別のアプローチでもっと使えるのではないかと思っています」(若山)
別領域の研究者が同じ研究をおこなうプログラムを通じ、それぞれへの刺激は十分あったようだ。
「この融合研究を通じて、わたし自身すごく勉強になりました。機能性ポリマー合成は専門ですが、電子回路は別の専門領域。デバイスにも様々な種類があり、さらに深く自分の研究が使えるのではないかな、という気づきがあったのがとても大きいですね」(相見)
「わたしも、やはり有機材料はおもしろい、ということを再認識できました。わたしは物理はできるけれども化学が実は苦手意識があり、分子構造は自分の領域外だと思ってきた。でも有機材料はほんとうにおもしろいな、可能性が非常にあるな、と改めて感じています」(若山)
注)
- Advanced Electronic Materials. 2 [2] (2016) 1500300 10.1002/aelm.201500300
- ロジックインメモリ:ロジックとメモリ機能をひとつのアーキテクチャに入れ込んだもの
- ニューロモルフィック素子:脳内ニューロン網を模した半導体

