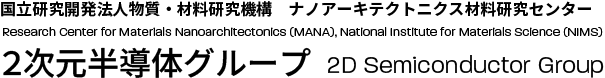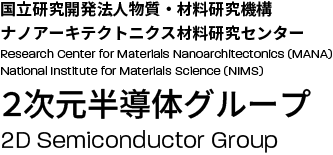研究紹介
私たちの研究グループでは、厚さが原子1〜数個分という極限的に薄い二次元物質(原子層物質)に着目し、次世代の半導体デバイス応用を見据えた研究を推進しています。
近年、生成系AIやデータセンターの利用が急速に広がり、それに伴って世界中の電力消費が増加しています。この問題を解決するためには、電子部品の一つであるトランジスタの消費電力を減らすことが重要です。この課題に対処するため、トランジスタに使われる半導体であるシリコンをさらに小さくする試みが行われています。しかし、シリコンの微細化には限界があるため、シリコン以外の新しい材料、例えば二次元物質を使う方法や、トランジスタの動作原理を変えて熱や電力消費を抑える「トンネルFET」などの新しい技術も検討されています。
このような研究が進む一方で、高品質な材料を用いて微細なデバイスを実現するためには、多くの課題があります。この課題を解決するために、本グループでは、代表的な二次元物質である「遷移金属ダイカルコゲナイド」を主な対象として、成膜・結晶成長、物性制御、デバイス作製に加え、電気伝導測定、ラマン散乱分光、光吸収・発光分光、電子顕微鏡、走査プローブ顕微鏡などによる構造・物性評価を行っています。
以下に私たちがこれまで研究してきたテーマの一部をご紹介します。
二次元半導体の成膜・結晶成長、構造制御
私たちのグループでは、種々の二次元物質やその接合構造(ヘテロ構造)を自在に合成する技術の開発に成功してきました。最近では、得られた高品質な試料を用いて、一次元界面における量子閉じ込め効果やトンネル電流の検証や、高性能な光・電子スイッチング素子やエネルギー変換素子の実現などに取り組んでいます。
詳細は以下のプレスリリースなどもご覧ください。(東京都立大学での研究)
インタビュー記事など
ナノサイエンスや電子材料に関するおすすめの本
ナノカーボンの科学(講談社ブルーバックス) 著:篠原 久典
フラーレン・ナノチューブ・グラフェンの科学;ナノカーボンの世界(共立出版) 著:齋藤 理一郎
高校数学でわかる半導体の原理―電子の動きを知って理解しよう (講談社ブルーバックス) 著:竹内 淳
青い光に魅せられて―青色LED開発物語(日本経済新聞出版) 著:赤崎 勇
新しい物性物理(講談社ブルーバックス) 著:伊達 宗行