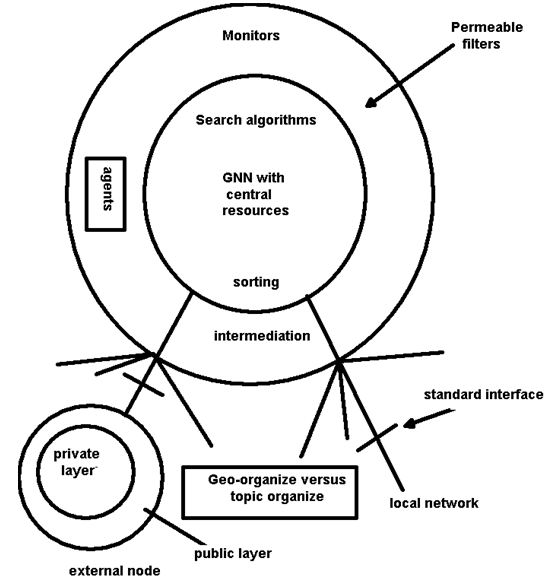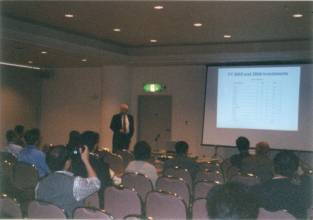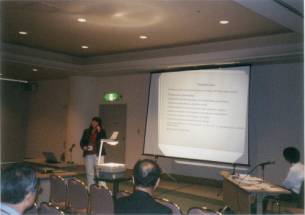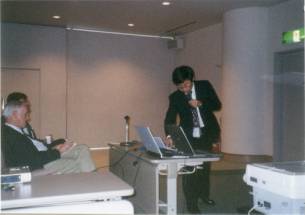�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�ڎ�
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���[�N�V���b�v����
��Q��i�m�e�N�l�b�g���[�L���O�ƍ��ۋ��͂Ɋւ��郏�[�N�V���b�v�́A��8�ۍޗ��Ȋw�w��A���|��i�ޗ��Ɋւ��鍑�ۉ�c�iIUMRS-ICAM�j�̃V���|�W�E��A-10�Ƃ���2003�N10��11�|12���Ƀp�V�t�B�R���l�ɂĊJ�Â��ꂽ�B���[�N�V���b�v�͓��{MRS�iMRS-J�j�ɂ���đg�D����A�ݖ{�����i�����E�ޗ������@�\�j�AR.P.H. Chang�iNorthwestern��w�j�A���������i�Y�ƋZ�p�����������j�A�����L��i�k��B��w�j�ɂ���ċ����c�������߂�ꂽ�B�{���[�N�V���b�v�̖ړI�́A��Ƃ��ăO���[�o���i�m�e�N�l�b�g���[�N�iGNN�j�̊J���Ɍ����Ă̌v��ł������B�����ʂł̓i�m�e�N�m���W�[�����x���v���W�F�N�g�Z���^�[�iNRNSJ,
���{�j�A�č��Ȋw���c(NSF, USA)�y�ъC�R������(U.S. Office
of Naval Research)����̎x�����B
���[�N�V���b�v�̎Q���҂͖�60�����x�ł���A�u���ƂƂ��ɏ��O���[�v�ɕ�����Ă̗L�Ӌ`�ȃO���[�v���_���s�����B�J�i�_�A�����A�t�����X�A�h�C�c�A�C���h�A�A�C�������h�A���{�A�؍��A�j���[�W�[�����h�A�V���K�|�[���A�X�y�C���A��p�A�p���A�č�����̎Q���҂��������B�i�Q���҃��X�g�͕t�^�Q���Q�ƁB�j
���[�N�V���b�v�̔w�i�ƖړI
�@�{���[�N�V���b�v�̓O���[�o���i�m�e�N�l�b�g���[�N�iGNN�j�Ɋւ��郏�[�N�V���b�v�̑�Q��ڂɂ�����B���E���̃i�m�e�N�m���W�[�̃��[�_�[�B���A�i�m�e�N����̉Ȋw�I�E�Z�p�I�E����I���������悭�����ł��邱�Ƃ�ړI�Ƃ����A�l�b�g���[�N�̍\�z�̂��߂̊�旧�ĂƋ�̓I�Ȑ헪����ɂ��ċ��͂��������B���̃_�C�i�~�b�N�Ȑi�W�ɂ��A���E���̊e�̈悩�痈���Ȋw�ҁA����ҁA���{��\�̊Ԃ̑����͂�����������A�V�����������𑣐i���邱�Ƃ������܂��B
�@�e������̍u���̌�ɁA����̃��[�L���O�O���[�v�Z�b�V�������J�Â��ꂽ�B�i�m�e�N����̍��ۓI�ȃ��[�_�[�B����̒Z���́A���[�N�V���b�v�Q���҂Ɍ�������l�b�g���[�N�ƁA�����̃l�b�g���[�N���ǂ̂悤�ɋ@�\���Ă��邩��F���������B���{��\�����͔ނ�̍��X��n��ł̃l�b�g���[�L���O�ƌ������͂������Ɏx�����邩���c�_�����B�W���u���iFocus
Talk�j�ł́A�����������f���A����A����ɂ��ďW���I�ɏЉ�Ȃ��ꂽ�B���ۃ��[�L���O�O���[�v�͗����Ƃ��J�Â���AGNN�̂��߂̋ٗv�ȃS�[���A�@�\�A�\�͂肷��ƂƂ��ɁA���X��n��̃l�b�g���[�N�������N���Ď��ۂ�GNN���\�z������@�ɂ��ċc�_���ꂽ�B�ŏI�I�Ȋ�����GNN�J���̃��[�h�}�b�v�̂��߂̊�b�Ƃ��Ď�����悤���̕��ɂ܂Ƃ߂�ꂽ�B
���[�N�V���b�v�̃e�[�}
�@���[�N�V���b�v�̂��߂Ƀi�m�e�N�m���W�[�̋ٗv�ȕ��삪�I�肳�ꂽ�B�Q���҂́A���ɓI�ɂ͂��L�����f�I�ޗ�����ɑ��Ă����̃A�C�f�A��K�p���Ȃ���Ȃ�Ȃ����A�g�D�ψ���i�m�e�N����̋ߔN�̋��ٓI���W���l�����ăi�m�e�N�m���W�[��ΏۂƂ��Đݒ肵���B�u���̓i�m�e�N�����v���O�����̃C���t���Ǝ��{�Ă̗��ʂɊւ����̂ł������B�X��������W�܂��������ҒB�͂��ꂼ��̍��ł̃i�m�e�N�v���W�F�N�g�̌���ɂ��ďЉ���B�����\�Z�x���g�D����S���@�ւ���̑�\�B�́A���{���̎����x���̓��e�ɂ��Đ��������B
�@�g�D�ψ���́A���E���̊e��v�n�悩��̃i�m�e�N�m���W�[���[�_�[���A�i�m�e�N�����ƌv������悤���ق����B�e�u���҂̓i�m�e�N�m���W�[�ւ̏W�������̏���A�����헪�̍l�����ɘj��A�e���v���O�����ɂ��Đ��������B���[�N�V���b�v�v���O�����ƍu���T�v�͎��߂ɋL�ڂ���Ă���B
�u���̌�ɎQ���҂͓�A�O�̃O���[�v�ɕ�����A���ۃl�b�g���[�L���O�̋@����L���邱�ƂɊ֘A����_�_���c�_�����B�O���[�v�͂��̂悤�ȃl�b�g���[�N���x����C���t�����ǂ̂悤�ɊJ�����邩�ɂ��Ă��l�������B
�@���ɁA�Q���҂́A�i�m�e�N�l�b�g���[�L���O�ւ̐��E�I�Q���������̌��ł���A���ւ̊ȒP�Ŗ����̃A�N�Z�X���i�m�}�e���A�������̐����⍑�ۋ��̓v���W�F�N�g�̓W�J�ɗL�Ӌ`�ȃC���p�N�g��^���邱�Ƃɍ��ӂ����B���[�N�V���b�v�ŐV�����F�����ꂽ�_�_�́AGNN�̂��߂̃��[�U�[�哱�g�D�̕K�v���Ƃ������Ƃł������B
���[�L���O�O���[�v�̌��_
�@�u����O���[�v���_�ւ̎Q�����܂߁A�{���[�N�V���b�v�ւ̑����������ȎQ�������Ƃ́A�f�m�m���J������Ƃ����l�����ɑ��āA�L�͂����ۓI�Ȏx����Ղ����݂��邱�Ƃm�ɕ����B
�|���V�[�ƍ\��
�c�_�̃Z�b�V�����ł́A�ȉ����܂ނ������̏d�v�Ȉӌ����T�O�I���ӂ������Ē�Ă��ꂽ�F
�P�D�f�m�m�͂��̍��ۓI�����N�⍑�ۓI�ɊJ�����ꂽ�v���O�����A�v���W�F�N�g�A�T�[�r�X��ʂ��āA�i�m�e�N�m���W�[�����⋳��̐����̂��߂ɋɂ߂ėL�v�ł���B
�Q�D�f�m�m�͐ӔC�\�͂̂���g�D���ꂽ���̂Ƃ��ĊJ������A���̓��e�A�v���O�����A�Ǘ��A�C���t���Ɋւ��Ă̓��[�U�[���䂳���\���ƂȂ�ׂ��ł���B
�R�D�f�m�m�͔�c���c�̂Ƃ��ċ@�\���A���{��Y�ƊE�A�t�@���h����c�A�K�v�ɂ���Ă̓��[�U�[�����ɂ���āA�����I�Ɏx�������ׂ��ł���B
�S�D�������l�������A�K�ōŐV�̓��e�̑I���ƈێ��������̂ЂƂ̊�ƂȂ�B�f�m�m�́g���C�h�ɖ����A�A�N�Z�X���e�ՂŁA�����ɊǗ������ׂ��ł���B
�T�D���͂͊ȒP�ł���ׂ��ł���B
�U�D�f�m�m��web�T�C�g�̓��[�U�[�t�����h���[�ł���A���̃����N���ꂽ�T�C�g����ւ̃A�N�Z�X�ւ֗̕��ȕ\���ւƂȂ�ׂ��ł���B���̂��߂ɂ͗D�G�Ȍ����G���W�����܂ޕK�v������B
�V�D�f�m�m�͌�����J�����̃i�m�l�b�g���[�N�Ɨe�Ղɂ������I�Ƀ����N���ׂ��ł���A�]���ȏd�������͍Œ���ɂ����ׂ��ł���B���̂��Ƃ͎v���[���J�����ꂽ���L�v���g�R�������݂��ď��߂ĉ\�ɂȂ�B
�v���ƃv���O����
�@�f�m�m�́A�i�m�e�N�m���W�[�̌����ҁA�����v���W�F�N�g�A�����{�݂̊ԂɌ����I�Ȑ��E�I�K�͂̃����N����A�o�ŕ��A�������A����p�����A�f�[�^�x�[�X�ւ̋��͂ȃA�N�Z�X����邱�Ƃ�ړI�Ƃ�����̂ł���B����ɁA���[�N�V���b�v�O���[�v�́A�f�m�m�̎����������ď��߂ĉ\�ɂȂ�ł��낤�A�������̏d�v�ȐV�����v���O�����̖�S�I�ȉ\���ɂ��ē��_�����B���̂悤�ȉ\���̂��������ȉ��ɋ�����F
�P�D�i�m�e�N�m���W�[�Y�Ƃ̋����̓��[�h�}�b�v�̊J���̑��i�B
�Q�D�i�m�e�N�m���W�[�W���̕]���f�[�^�x�[�X�̊J���B
�R�D�q���c�p�[�g�i�[�V�b�v�𒇉�A���i����B
�S�D�i�m�e�N�m���W�[�����̐l�I�����ƌ����{�݂̐��E�I�f�[�^�x�[�X�̊J���B
�T�D���ۓI�F�m���l�����邽�߂̋���I�v���O�������n��������B
�U�D���j�I�Ȍ����{�݂ւ̃A�N�Z�X���܂ފw����w���Ԃ̌����v���O�����𑣐i����B
�V�D���E�I�ȃi�m�e�N�m���W�[�����̎��g�݁A����A���H�A�����z���Ɋւ������
�@�@���W�E���s���B
�W�D�ŐV�j���[�X�̔z�z�⌤���n�C���C�g�̃M�������[���ێ��E�Ǘ�����B
�A�N�V��������
�@�f�m�m���J�����A�����̖�S�I���̗v�ȃv���O������B�����邽�߂ɂ́A�f�m�m�̑g�D�\�����A���[�U�[�哱�ł���A���ӔC�̂���Ǘ��\�͂��A�ϋɐ��Ə_���g�ݍ��킹�����@�ő��₩�Ɍ`����邱�Ƃ��̗v�ł���ƍl������B�Ȃɂ����A�f�m�m�̖ړI�Ƌ@�\�����[�U�[�ɂ悭��������A�T�|�[�g����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�b��I�ȊJ���v��͖��m�ɕ\�������K�v������A�o�����ɗ\�z����鎑���Ɍ������g�D�\���肵�Ȃ���Ȃ�Ȃ��B
�f�m�m�̌����I�ȕ`��
�@�O���[�v���_�Z�b�V�����́A�W�c�Ƃ��ď��߂āA�f�m�m�ƌĂ����Ԃ����ۂɂǂ̂悤�ȋ@�\�╨���I�\���ɂ��\������邩�ɂ��Ă̋�̓I�ȕ`�����������B�Y�t�������͂R�̓Ɨ��ȃO���[�v���ȉ��̃g�s�b�N�X�ɂ��ċc�_�������ʂł���F
�@�@�@�@�@�|�@�f�m�m�ɎQ������R�~���j�e�B�[
�@�@�@�@�@�|�@�f�m�m�̋@�\�ƖړI
�@�@�@�@�@�|�@�f�m�m�̑g�D�\��
�@�@�@�@�@�|�@�����̉\��
�@�@�@�@�@�|�@���������ׂ����
�@�R���O���[�v����̕����܂Ƃ߂����̂��t�^�PA,B,C
�Ƃ��ēY�t����B�ǎ҂ɂ͂��̑�ϕ�����₷��������ǂ��邱�Ƃ߂�B
�@�ꓯ�ɉ�čl�@���邱�Ƃɂ��A���́u���݁A�����G���W��Google��d�q���C���ł͗e�Ղɂ͍s���Ȃ������ŁA�f�m�m�ɂ��\�ɂȂ邱�Ƃ͉����H�v�Ƃ�������I�Ȗ₢�ɑ��Ė��m�ɉ��Ă���B����ɁA���p���ꂽ�����̃L�[���[�h�̔����p�x����A�D��x��r�W�����Ɋւ���{���I�ȍ��ӂ�������Ă���B
�O���[�v�`�Ƃb�̌��_�ł́A�f�m�m�ɗv������钆�����Ǘ����ׂ��͈͂����Ȃ�قȂ����B�O���[�v�`�́A�f�m�m����◘�p�҃R�~���j�e�B�[�̑�\�Ƃ��ăf�B���N�^�[�ψ���Ɨ��p�҂̃A�h�o�C�U���[�ψ���̗�����݂��悤�Ƃ��Ă���B�ψ���͓K���ȃX�^�b�t���ق��A����̊�]�����s����ӔC���A��c���g�D�Ƃ��Ă̂f�m�m�̊Ǘ��ɕK�v�ȑS�Ă̎����������I�ɍs���B�O���[�v�b�́A�n��I���ِ��ɑΉ����邽�߂ɁA���S�ɕ������ꂽ�g�D�\�����Ă����B���̂悤�ȉ��������K�v�̂��鑊��_���ˑR�Ƃ��Ďc���Ă���B����ł��Ȃ��A�����̕��͗ǂ��l�����Ă���A�����I�ȑg�D�\����Ǘ����@�̃��f������Ă���B����ɕ��́A�f�m�m�̑�\�̉^�c�ψ���ɁA�\�Z���m�ۂ��f�m�m�̏��ݒn�����肵�f�m�m�g�D�̗ǎ��ȊǗ����w�肷�邽�߂́A��̓I�Ȏb��v��ƃ^�C���e�[�u��������������C���𖾂炩�ɂ��Ă���B
���[�N�V���b�v�̃v���O�����ƍu���T�v
�ڎ�
2003�N10��11��
�J��̈��A
�@-. �J��̎���IUMRS-ICAMS2003�̃`�F�A�}���ł���P�Y�i�i�m�e�N�m���W�[�����x���v���W�F�N�g�Z���^�[�y�ѕ����E�ޗ������@�\�j�y�і{���[�N�V���b�v�̋����c���ł���ݖ{�����i�����E�ޗ������@�\�j�AR.P.H. Chang�iNorthwestern��w�j�A���������i�Y�ƋZ�p�����������j�A�����L��i�k��B��w�j�ɂ���āA�s��ꂽ�B
�@-. R.P.H. Chang�iNorthwestern��w�j�ɂ���āA�{���[�N�V���b�v�̌o�܂ƍŋ߂̃S�[�����������ꂽ�B
�X�s�[�J�[�p�l���P: �i�m�e�N�����ƃl�b�g���[�L���O�Ɋւ����
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@����: ���������i�Y�ƋZ�p�����������j
�_�J�@���@(NEDO)
�g���{�̃i�m�e�N�l�b�g���[�N�h
�_�J��NEDO�ɂ�����i�m�e�N�����J�����́A�l�b�g���[�N�A����ɂ��ďЉ�A�ߔN�̓��{�ɂ�����C�j�V�A�`�u�ɂ��ču�������B�ނ͂������̃i�m�e�N�ޗ������v���O�����̐��ʂ̃V�X�e�����A���ۉ�c��W�����ʂ����������A�Y�ƊE�Ƃ̒n��I�i�m�e�N����Ɋւ��鋦�͂Ȃǂ̎�X�̎��݂ɂ��ďЉ���B
R.W. Siegel (Rensselaer Polytechnic Inst., �č�)
�g�č��ɂ�����i�m�e�N�l�b�g���[�N�h
Siegel �́A�č��G�l���M�[�ȁiDOE�j�ɂ���Ďx������Ă���Nanoscale Science Research Centers�ANSF�ɂ��x������Ă���Nanoscale Science and Engineering Centers�ANASA�ɂ���Ďx������Ă���Nanotechnology University Research Education Technology Institutes���܂ޕč��̃i�m�X�P�[���Ȋw�E�Z�p�̌����Z���^�[�ɂ��ĊT�ς����B�ނ͂����̌����Z���^�[���ǂ̂悤�Ɍ݂��ɑ��ݍ�p���A���E���̑��̌����Z���^�[��l�b�g���[�N�Ƃǂ̂悤�Ƀ����N����邩�ɂ��Đ��������B
�X�s�[�J�[�p�l���Q: �i�m�e�N�����ƃl�b�g���[�L���O�Ɋւ����
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@����: �����L��i�k��B��w�j
Z.G. Khim (Korean Nano Researches Association, �؍�)
"�؍��ɂ�����i�m�e�N�l�b�g���[�N�Ǝ����z��"
Khim�͊؍��ɂ�����1995�N�Ɏn�܂�1999�N�Ɋg�傳�ꂽ�i�m�e�N�Ɋ֘A���邢�����̌����l�b�g���[�N�ɂ��ďЉ���B���̌�̐�i������̃i�m�e�N�����̔g�ɂ��A2002�N�ɐ헪�I����R&D�v���O���������肳�ꂽ�B���̃v���O�����ɂ��Daeduck�Ȋw�s�s�Ƀi�m�t�@�u���P�[�V�����Z���^�[���ݒu�����ƂƂ��ɁA���{�y�і��Ԃɂ��i�m�e�N�̌����J���ɑ啝�Ȍ����������n�܂����B
G.L. Rochon (Purdue ��w, �č�)
�gPurdue��w�ɂ�����i�m�e�N�����E����E�C���t���E�A�g�h
Rochon�͕č��i�m�e�N�l�b�g���[�N�ɂ�����v�Z�Ȋw�E�V�~�����[�V�����Ɋ֘A����b��ɍi���ču�������B�ނ�Purdue��w�ɐݒu���ꂽ�l�b�g���[�N�i�i�m�e�N�v�Z�Ȋw�̂��߂̃i�m�n�uNCN�l�b�g���[�N��e-�G���^�[�v���C�Y�Z���^�[�j�ɂ��ďЉ�A���E���̊O���̃l�b�g���[�N�Ƃǂ̂悤�ɑ��ݍ�p���Ă��������c�_�����B
Prof. C.N.R. Rao (Jawaharlal Nehru Centre for Advanced Scientific Research, �C���h)
"�C���h�ɂ�����i�m�����ƃl�b�g���[�N"
Rao�̓C���h�����ƃi�m�E�C�j�V�A�`�u���J�n���A��N���u�y�уC���t���̉��P�ɓ����������Ƃ�����B�������̐�剻�����Z�p�Ɋւ��Ē��S�I���Ǝ{�݂�ݗ����Ă���B�܂��i�m�T�C�G���X����̑�w�@���⋳�t���g���[�j���O���邽�߂̃��[�N�V���b�v���J�Â��Ă��邱�Ƃ��Љ���B
J.M. Yacaman (Texas��wAustin�Z, �č�)
"�č�-���e���A�����J�ɂ�����i�m�e�N�l�b�g���[�N"
Yacaman�͋ߔN�̕č��ƃ��e���A�����J�̊Ԃ̃i�m�e�N�A�g�Ɋւ��ču�������B�����̍��X�ɂ�����o�ϓI�A����I���Љ����A���̉\���ɂ��ċc�_�����B�A�g�̗��_�E���_�Ɋւ��Č��y���A�J���r��̃��e���A�����J�����ɂƂ��ăi�m�e�N�ƃl�b�g���[�N�̏d�v�����w�E�����B
�t�H�[�J�X�g�[�N�P
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@����: �ݖ{�����i�����E�ޗ������@�\�j
���{�m�u (�k�C����w)
�g�i�m�e�N�����ɂ����鍑�ۋ��͂Ɍ����āh
���{�̓i�m�e�N�����Ɗw�ۗ̈�̍��ۋ��͂̏d�v���ɂ��ču�������B�ߔN�A�����w�A���w�A�d�q�H�w�A�͊w�A�ޗ��Ȋw�A���w�A���_�V�~�����[�V�����Ȃǂ̕�������f�����V���|�W�E����[�N�V���b�v���p�ɂɊJ�Â���Ă��邪�A�ނ͂��̂悤�ȏ�ŋc�_���ꂽ�������̎����ɂ��ďЉ���B�ނ̓i�m�e�N�ɂ�����g����h�ƌv���w�̏d�v�����������A�����̐��x�ƍČ����ɂ��ď[���ɗ�������K�v����������B
�t�H�[�J�X�g�[�N�Q
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@����: �ݖ{�����i�����E�ޗ������@�\�j
�{�Z�b�V�����ł�C. Ziegler
(Kaiserslautern��w, �h�C�c)��H. Schmidt (Institute for New Materials, �h�C�c)�� �g�h�C�c�ɂ�����i�m�e�N�l�b�g���[�N���f���h�Ƃ����薼�̂��ƂɎ��Ԃ����ču�����s�����B
"�h�C�c�ɂ�����i�m�e�N�l�b�g���[�N���f��"
�@Ziegler�̓h�C�c�ɂ�����i�m�e�N�l�b�g���[�N���f���̏d�v�ȓ����ɂ��ču�������B�ޏ��̓h�C�c�̃l�b�g���[�N�\���̋��͂�����������ƂƂ��ɁA���[���b�p�ɂ����鐬���̗�Ƃ��Ă��̊������Љ���B
�@Schmidt�̓i�m�e�NBMBF�l�b�g���[�N�ɂ��Đ��������B�V�̏d�v�ȃl�b�g���[�N�̈�Ƃ���CC-�i�m���w�A�i�m���́A�i�m���w�A�����@�\�����A�i�m�����A�i�m�o�C�I�e�N�Ȃǂ��w�肳��Ă���BCC�i�m���w�l�b�g���[�N���ɂƂ�A���̍\���A�A�g�A���ʂȂǂ���������B
���[�L���O�O���[�v�f�B�X�J�b�V�����P
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@����: R.P.H. Chang (Northwestern ��w, �č�)
�e�[�}�F�O���[�o���i�m�e�N�l�b�g���[�N�iGNN�j�̐ݗ�
�O���[�v���[�_�[�FJ. Baglin (IBM, �č�), R. Nemanech (North Carolina �B����w, �č�), E. Kaufmann
(Argonne������, �č�)
�@�Q���҂͂R�̃O���[�v�ɕ�����AGNN�ɋ��߂���v���ɂ��ċc�_�����B
�@�Q���҂���GNN�̓��[�U�[�哱�ʼn^�c����AGNN�̍\�������[�U�[�哱�ɂ���Ĕ��W�������Ă������Ƃ̏d�v�����������ꂽ�B�ނ�́A����̖��A�A�g�A�i�m�e�N�̃O���[�o���ȃ��[�h�}�b�v���A�f�[�^�̕]���A�W���̊m���A�A�N�Z�X�̂��Ղ��Ȃǂ��c�_�����B
�@�ȏ�̋c�_����AGNN�̊����Ɣ\�͂Ɋւ���u��]���X�g�v���쐬���ꂽ�B���X�g�̊e���ڂɂ��Ď����\���ƃR�X�g���e���]�����ꂽ�B�����̃X�^�b�t�ɗv�������Ɩ��̊����Ɗe�n���i�m�[�h�j�ɗv��������^�̊��������ς���ꂽ�B
2003�N10��12��
�L�[�m�[�g���N�`���[�P
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@����:�F�� �P�Y (NRNSJ�G�����E�ޗ������@�\)
M. Roco (�V�j�A�A�h�o�C�U�[, NSF, �č�)
"�č��ɂ�����i�m�e�N�����ƘA�g"
Roco�͐��E�̑����̍��X�ɂ�����i�m�e�N�E�C�j�V�A�`�u�Ɠ�������ɂ��ĊT�ς����B���{�@�ւɂ���ĕ��ꂽ���E�ł̃i�m�e�N�����J���ւ̓����́A1997�N��432�S���h������2003�N�̖�3�\���h���ւƉߋ��U�N�ԂłV�{�ɂ����������B�i�m�X�P�[���Ȋw�ƋZ�p�̃S�[�������ۋ��͂ɂ���Č����܂��
�X�s�[�J�[�p�l���R: ���̒n��ł̐��{�̌����\�Z����
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@����: R.P.H. Chang (Northwestern ��w, �č�)
M.K. Wu (Academia Sinica, ��p)
"��p�ɂ�����i�m�e�N�Ɋւ��鍑�ƓI�Ȋw�Z�p�v���O����"
Wu�̓i�m�e�b�N�l�b�g���[�N�ƌ������͂Ɋւ����p�̌����\�Z�����ɂ��ču�������B�ނ̓i�m�e�N�l�b�g���[�N�ƌ������͂̐i�W���x����ŋ߂̑�p���{�̌����\�Z�����ɂ��ďЉ���B�ނ͊w�ۗ̈�ł̋���v���O�����ƍ��ۓI�𗬁A���ۓI�A�g�̏d�v�������������B
S. Xie (Chinese Academy of Science, ����)
�g�����ɂ�����i�m�e�N�̌����\�Z�����ƃl�b�g���[�N�h
Xie�́A�������{�ɂ��i�m�e�N�l�b�g���[�N�̐i�W�𑣐i���A�i�m�e�N�����Ƌ���̍��ۋ��͂��x������ߔN�̕���Ǝ����z���C�j�V�A�`�u�ɂ��Đ��������B�ނ͋ߔN�̃i�m�e�N�������͂Ɋւ��钆���ɂ�����v���O�����ƃC�j�V�A�`�u�ɂ��ďЉ�A�������钆���̃i�m�e�N�l�b�g���[�N�A���ɂ��̋@�\�ƒ����O�̑��̃i�m�e�N�l�b�g���[�N�Ƃǂ̂悤�ɊW���Ă��邩�ɂ��ĕ����B
�X�s�[�J�[�p�l���S: �l�b�g���[�N�ƎY�ƊE�̃p�[�g�i�[
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@����: ���������i�Y�ƋZ�p�����������j
���R�@�_ (�Y�ƋZ�p����������)
"�헪�I�i�m�e�N�O���[�o���l�b�g���[�N�FAIST�ɂ����錻��ƒ��"
���R�͐헪�I�i�m�e�N�O���[�o���l�b�g���[�N�Ɋւ���AIST�ɂ����錻��ƒ�Ăɂ��Č��y�����B�i�m�e�N�����J���ɂ����Ă͐��I�ȃA�C�f�A���X�s�[�f�B�[�ɒx��Ȃ����������邱�Ƃ��d�v�ł��邽�߁A�k�āA���[���b�p�A�A�W�A�̎�v�Ȍ����@�ւƑo�����I�ȊW��z���w�͂����Ă������Ƃɂ��Đ��������B�ނ͂܂��A��w�ƎY�ƊE�̗������疢���̃p�[�g�i�[���W���鎎�݂ɂ��Ă��Љ���B
K.J. Snowdon (Newcastle��w, �p��)
"�p���ɂ�����i�m�e�N�l�b�g���[�N�F�Y�ƊE"
Snowdon�͉p���ɂ�����i�m�e�N�l�b�g���[�N�̎Y�ƊE�I���ʂɂ��ču�������B�ނ͉p���ɂ�����~�N��-�y�уi�m-�e�N�ɏ]�����錤���ҁA�����@�ցA�����ݔ��ɂ��ďœ_�����킹���p���~�N��-�y�уi�m-�e�N�l�b�g���[�N�̐i�W�ɂ��Č��y�����B�ނ́A�Y�ƂƑ�w�����҂̊Ԃ̋��͂��Ǘ����邱�Ƃɂ���Ɛ��_�Ə��Ɖ��𐄐i���镽�s�����J����INEX���f���ɂ��Đ��������B
J.C. Yang (ITRI, ��p)
"�i�m�e�N�l�b�g���[�N�FITRI�̃A�v���[�`"
Yang�̓i�m�e�N�̎Y�ƂɊւ����p�̃A�v���[�`�ɂ��ċc�_����B��p�ł͂U�N�v��̍��ƃi�m�e�N�v���O�����\�Z615�S���h����60�����i�m�e�N��"�Y�Ɖ�"�Ɍ������Ă���A���̎Y�Ɖ��̂��߂̌����J���̑�����ITRI�ɂ���čs����B�ނ́A�����̌����J����������p���i�m�e�N�̎Y�Ɖ��̈�ԑ��҂ł��邱�Ƃ��m�����A�����ɂ킽���p�̃i�m�e�N�Y�Ƃ̗D�ʐ����m�ۂ���Z�p�I�����͂�z�����Ƃ��g���Ƃ��Ă��邱�Ƃ����������B
G. Crean (NMRC, �A�C�������h)
"�A�C�������h�ɂ�����i�m�e�N"
Cream�̓A�C�������h�ɂ�����i�m�e�N�l�b�g���[�N�ƌ������͂ɂ��ču�������B�ނ͂ǂ̂悤�ɃA�C�������h�̃l�b�g���[�N���\�Z�z������A���̃��[���b�p�₻�̑��̐��E�̃l�b�g���[�N�Ƒ��ݍ�p���邩�ɂ��Đ��������B�ނ͂܂��ACork��Dublin�ɂ��鍑�ۓI�����͂�L����n��N���X�^�[�ƁACork�ɂ��鍑���i�m�t�@�u���P�[�V�����{�݂ɂ��Đ��������B�Y�ƊE�Ƃ̃l�b�g���[�N�ւ̃A�v���[�`�ɂ��Ă����������B
�ΐ쐳���i�O�H�����������j
"���{�Y�ƊE�ɂ�����i�m�e�N�l�b�g���[�N"
�ΐ�͎O�H�����ɂ�����i�m�e�N�l�b�g���[�N�ƌ������͂𐄐i����헪�ƃC�j�V�A�`�u�ɂ��ĊT�ς����B�ނ̓i�m�e�N�̃g�����h�̏ڍׂȉ�͂���A�i�m�e�N���[�h�}�b�v���쐬���邱�Ƃ̏d�v�����w�E�����B�܂��A��w�ƎY�ƊE�̌����҂̊ԂɌ𗬂��������邱�Ƃ̏d�v���ɂ��Ă����y�����B�ނ́A�{�g���A�b�v�i�m�e�N���Y�ƊE�ɋZ�p�I�u���[�N�X���[�̌��ƂȂ邱�ƁA���{�Y�ƊE��"�����͕�"�i�m�e�N�ɑ�ϋ����������Ă��邱�Ƃ��q�ׂ��B
�L�[�m�[�g���N�`���[�Q
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@����: �ݖ{�����i�����E�ޗ������@�\�j
��c�N�� (�i�m�e�N�m���W�[�����x���v���W�F�N�g�Z���^�[)
"�i�m�e�N�����l�b�g���[�N�̊���"
��c�̓i�m�e�N�m���W�[�����x���v���W�F�N�g�ƃi�m�e�N�m���W�[�����l�b�g���[�N�Z���^�[�iNRNSJ�j�ɂ��ču�������BNRNSJ�̖ړI�̓i�m�e�N�����ƌ����{�݂̃l�b�g���[�N���`�����A�������ʂɊւ���ŐV���⋤�����p�̓���{�݂����L���邱�Ƃɂ���BNRNSJ�́A�i�m�e�N�m���W�[�Ɋւ��鍑�̌����v���O�����⌤���҂�������̊����A�����Ɋւ�����̃f�[�^�x�[�X���쐬������B
�t�H�[�J�X�g�[�N�R
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@����: �ݖ{�����i�����E�ޗ������@�\�j
R.P.H. Chang (Northwestern��w, �č�)
�g���ۉ��z�������F�O���[�o���i�m�e�N�l�b�g���[�N�̂��߂̃T�C�o�[�C���t���h
Chang��Northwestern��w�ŊJ�����̍��ۉ��z�������̃v���g�^�C�v�̃T�C�o�[�C���t�����ǂ̂悤��GNN�̎���Ԃł̊����Ǝ{�݂������A�����o�[�Ԃ̋��͂𑣐i���邽�߂Ɏg�p����邩����������B�J�����̋@�\�̗�Ƃ��āA���͓I�����v���O�����̉��z�I�t�B�X�A�ŐV�̌������ʂ����X�ƕ\������O���[�o�������M�������[�A����Z���^�[�A�Ȋw�E�H�w����Z���^�[�Ȃǂ��Љ�ꂽ�B
���[�L���O�O���[�v�f�B�X�J�b�V�����Q
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@����: R.P.H. Chang (Northwestern ��w, �č�)
�e�[�}�F�O���[�o���i�m�e�N�l�b�g���[�N�iGNN�j�̐ݗ�
�O���[�v���[�_�[�FJ. Baglin (IBM, �č�), R. Nemanish (North Carolina �B����w, �č�)
�Q���҂͂Q�̃O���[�v�ɕ�����AGNN�̍\���Ǝ��{���@�ɂ��ċc�_�����B�܂�GNN�̎����I�ȍ\���ɂ��Ă��c�_�����B�Q���҂́AGNN���n�������A�����Ď��������A����ɗv�]���X�g�ɏ�����Ă���@�\�����邽�߂ɕK�v�ȁA�g�D�ƐM�����̍ŏ����̊�{�\���ɂ��āA�܂Ƃߏグ���BGNN�͘I��ɔ�c���c�̂Ƃ��Ċ������ׂ��ł��邱�Ƃ����肳�ꂽ�BGNN�̊�����ŋ��ɓI�ɏd�v�ȓ����ƃ|���V�[�̃��X�g���쐬���ꂽ�B�V�����ϓ_�A���Ȃ킿���[�U�[���ǂ̂悤�ɓ��@�t����GNN�̐i�W�ɎQ�������Ă��������c�_���ꂽ�B���[�U�[�ɗD�����A���[�U�[�ɂ���Ď哱����Ă���GNN�̎��{�̌��������_���ꂽ�B
�T�[�}���[�Z�b�V����
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@����: �ݖ{�����i�����E�ޗ������@�\�j
Baglin�iIBM, �č��j��GNN�̖]�܂������A�\���A���{���@�Ɋւ��ăO���[�v�f�B�X�J�b�V�����œ���ꂽ���ʂ��܂Ƃ߂��B����GNN���[�N�V���b�v�̓��[���b�p�ŊJ�Â����\��ł���B
�t�^1�F���[�L���O�O���[�v�f�B�X�J�b�V����
�ڎ�
�t�`�D
�f�B�X�J�V�������[�_�[�FJohn Baglin, IBM Almaden Research
Center, San Jose, CA, USA
�鏑�FProf.David Officer, Massey University, New Zealand
GNN �̃~�b�V�����Ɣ\�͂Ɋւ����]���X�g
�e�O���[�v��GNN�̊����Ɣ\�͂Ɋւ���v�]���X�g�̍쐬�����߂�ꂽ�B
����:
GNN���ݗ����ꂽ�ꍇ�A�Ȃɂ���ԗL�v�Ȃ��Ƃ��H
���f�����F
(a) �t�����l�������F�����̂��Ȃ��̊���ł͂ł��Ȃ����ƁB
(b) ���ۃ����N�Ɋ֘A���邱�ƁB
(c) �����̊����̑S���{���Ԃ͐��N�B
�v��F
1. �����I�ɕs�\�Ƃ��R�X�g��������߂���Ƃ����������O���ėv�]���X�g���쐬�B
2. ���̌�A�e���ڂɂ��Ď������ƃR�X�g��e���]������B
3.
���ɁA�Z���^�[�X�^�b�t�ɗv������邱�ƂƊe�n���i�m�[�h�j�ɗv��������^�̑��ΓI�䗦�����ς���B
�v�]���X�g��\�P�Ɏ����B���X�g�͂����悻���ڂ̋K�͂ɂ��z��Ă���A�z���ƗD�搫�Ƃ͊W���Ȃ��B�������A�R�X�g�A�Z���^�[�X�^�b�t�ɗv������銈���ʂƒn��ɗv��������^�̑��ΓI�傫�������������������B
���X�g�̊e���ڂ͑����̋c�_�ƍl�@�̌��ʂł���A�����ꂽ�S�Ă̍��ڂ̓O���[�v�̎Q���Ҋe�ʂɂ���ċᖡ����A�����x�����ꂽ���̂ł���B���{���\�ł���A�S�Ă̍��ڂ͍����D�搫�����ƍl������B���̑��ɂ������̒�Ă��Ȃ��ꂽ���A�����̌��ʁA�p�����ꂽ�B
�\1.�O���[�o���i�m�e�N�l�b�g���[�N�̊����A�v���O�����A�\�͂ւ̗v�]���X�g
| GNN�̊����Ɣ\�͂Ɋւ���v�] | ������ | �R�X�g | �Z���^�[�X�^�b�tI | �n���i�m�[�h |
| �i�m�e�N�Y�ƃ��[�h�}�b�v �̍쐬�Əo�� | ** | $ | ***** | **** |
| �l�I�����Ɛݔ��̐��E�I�ȃf�[�^�x�[�X | ** | $ | *** | **** |
| ����̌����̏����F���┒�� | *** | $ | ** | ** |
| ���E�I�K�͂̃i�m�e�N��w�F�w�ۓI���j�b�g�̋�����e | *** | $$$ | ***** | **** |
| �w���y�ъw���̌����v���O������ݔ��ւ̃A�N�Z�X | *** | �@ | *** | *** |
|
�p�[�g�i�[�V�b�v�̒���B�����̊����I�}�b�`���[�L���O�B �i���-��ƁA���-��w�A�ȂǁB�w�p�c��-���Ɖ��p�[�g�i�[�j |
** | $$ | ** | **** |
| �W���̊m�� | * | $ | * | * |
| ���E�I�Ȑ���₻�̎��H�i���Ɍ����\�Z�z���j�̒� | ** | �@ | ** | *** |
| �f�[�^�x�[�X�̍쐬�Əo�Łi���{���j | * | $$$ | ** | ** |
| �i�m�e�N�̉e���E���ʂɊւ��錤������̌𗬐��i | * | $ | * | * |
| �ŐV�̃f�[�^��j���[�X�����W���A�ҏW�A�\�����邱�� | * | �@ | * | ** |
| �i�m�e�N���������G���W���̑��� | *** | $ | ** | �@ |
| �L���Ȍ��I�x���v���O���� | *** | $ | **** | **** |
| �I�����C��������A���[�N�V���b�v�A�N���X�̎��{�^�x�� | *** | $ | *** | *** | ������⍑�ۉ�c�̊��E���{�x�� | *** | �@ | * | * |
| ���E�I�K�͂̌����w��̐ݗ� | * | �@ | * | * |
GNN �̐��\�Ǝg�r�F �| �d�v�Ȕ�������́H
�����F
�V����GNN�̂��߂ɓ��ɏd�v�Ȑ��\�ƓN�w�̏����́H
�A�N�Z�X�Ɋ֘A���鎖���F
- GNN�͖��m�ɔ�c���c�̂Ƃ��ĉ^�c�����ׂ��B
- �唼�̓��e�ւ̃A�N�Z�X�͖����Ƃ��ׂ��B�X�|���T�[�ɂ�鉇���������B
- �u����v�͑S�ʓI�ȓ��e�ɃA�N�Z�X���\�ŁA���ڏ�̉������x�����B
- �傫�ȃR�X�g��������T�[�r�X�͗L���Ƃ��邪�A�R�X�g�͍Œ���ɗ}����B
���[�U�[�C���^�[�t�F�[�X�F
- GNN�ւ�"����"�̓��[�U�[�t�����h���[�Ƃ��邱�ƁB
- "����"�͑S�Ă̋@�\�ւ̖����Ȃ������I�ȗU�����s�����Ƃ��ł��邱�ƁB
- ���̒P���"����"�͎��ۏ�A�����^�A�N�Z�X�̑��l�ȃ��x���̃��[�U�[�������邱�Ƃ��ł���B
- �������"����"�ƃ��[�U�[�C���^�[�t�F�[�X�F�����ɉ\���葽���̃A�N�Z�X���邱�Ƃ�������B
- ����F�|�ꂽ�f�B���N�g���[�������A�K�v�ɉ�����Google�̂悤�Ȗ|��\�t�g�����B
- Google�l�b�g���[�N�����G���W���ƌ������邱�ƁB
�o���h�ш�^�X�s�[�h�Ɋւ������F
- �\�Ȍ���"�e�L�X�g�̂�"�Ƃ��������I�v�V������݂���B
�����F
- �V��������e�Ղɓ��͂ł��邱�ƁB
- ���͎҂̃N���W�b�g�^���p�̓I�v�V�����Ƃ��ĕێ����邱�ƁB
- ��o���ꂽ���͏���"�T�C�g�}�l�[�W���["�ɂ���āA�K���̊ϓ_����I�ʂ����B
- ���͈͂�ʓI�Ƀ����o�[�݂̂̓����Ƃ���B
GNN �̎��̓I�g�D
�����F
GNN���n�������A�����Ď��������A����ɗv�]���X�g�ɏ�����Ă���@�\�����邽�߂ɁA�K�v�ȑg�D�ƐӔC�̂��߂̍ŏ����̊�{�\�����L�q���邱�ƁB
* GNN
�͐ӔC�ƒ����̂��߂Ɏ��ۏ�y�єF����̗����̃V�X�e���̕K�v�Ƃ���B
* GNN �͔F����Ǝ��ۏ�̗��ʂɂ���"���[�U�[����"�\���łȂ���Ȃ�Ȃ��B
���̓I�Z���^�[�F
��A�̐�p�T�[�o�[���K�v�����A�S�Ă���ӏ��ɐݒu�����K�v�͂Ȃ��B
�\���F
1. �f�B���N�^�[�ψ���i�n���m�[�h�̃f�B���N�^�[���܂ޏꍇ������j
2. �A�h�o�C�U���[�{�[�h�i���[�U�[�A�֘A����o����L����l�X�Ȃǁj
3. �}�l�[�W���[
4. ������
5. �Ȋw�I�^�Z�p�I���G�]���G�Z�p�I�Ή��҂ƊW�������A�K�v�Ȏ������W�߁A���e�ҁA�_��ҁA�����W�҂Ƃ̌��Ȃǂ��s���B
6. "���Y"����F�Ⴆ�Ή��z��c�A���玑���Ȃǁi�v�]���X�g�Q�Ɓj
7. �}�[�P�e�B���O�F�s�꒲���A�s��J����܂ށB
8. �r�W�l�X�v�����F��{�I�Ƀr�W�l�X�I�ɍs����B�傫�ȐӔC�\�͂����}���[�W�����g�B
9. IT�A�b�v�f�[�g�ƃ��C���e�i���X���s���l�ށFGNN�̃\�t�g�E�F�A�ƃV�X�e������ɍŐ�[�Ȃ��̂ɕۂ��Ƃ͕K�{�̏����ł���B
�헪�F
�@���_�O���[�v�`�́A�ȉ��̍��ڂɂ��č��ۓI���ӂɂ�肳��Ȃ�v�挟�����s�����Ƃ𑣂��B�@��v��GNN�C���t�����\�z���邱�ƁB�A��������Q�������シ�邱�ƁB�B���[�U�[�̋����������������邱�ƁB�CGNN�ւ̎Q���ƃT�[�r�X�������邱�Ƃ�ۏ��邱�ƁB