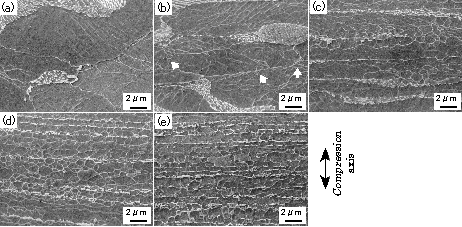|
1ミクロン超微細結晶粒を得るための指導原理 一方、本方法はより低い温度域である700℃以下のいわゆる温間温度域でフェライト自体を加工し、回復・再結晶によって微細αを生成させるものです(1,2,3)。 1) 多パス加工で懸念(予想)されるパス間での組織変化がなく、 2) 多パス加工のような途中再加熱にともなう組織変化がない、 3) 加工直後に水冷できるため、動的現象のみを抽出できる、 4) 通電加熱を用いているため、温度一定のもとで大加工ができる、 などが挙げられます。したがって、精度の高い大ひずみ加工試験が可能になっています。 図1に、加工温度650℃、ひずみ速度10/sで圧縮加工を行った場合の組織変化の様子を示します。この温度域で加工されたフェライト粒は、ひずみの増加にともなって形がつぶれて扁平になってゆきます。
(b)ひずみ1.2(減面率で70%)では筋(薄くエッチングされる)はさらに増加します。また、特徴的なことは、初期フェライト粒界付近から新しい粒の生成が生じることにあります(写真中に矢印)。初期フェライト粒界と同等に明瞭にエッチングされる粒界に囲まれ、その大きさは1ミクロン以下です。 さらに、(c)ひずみの増加にともない、もともとの粒はますます扁平になってゆきますが、新粒が占める割合も増加してゆきます。 (d)ひずみ2.7(減面率で94%)になりますと、ほぼ全面が等軸微細粒のみからなり、オリジナルフェライト粒界がどこにあったのか区別がつかなくなります。また、新粒はひずみによらず約0.7ミクロンとほぼ一定の粒径であることが注目されます。この新粒が生成し始めるひずみは1.2とかなり大きいことが特徴です。 以上は、ひずみ2をこえるような大ひずみ加工を行うことによって、単純な加工条件下でも、フェライト粒が超微細化することを示した結果であります(4)。この現象は、加工中に生じた組織変化ですので、動的回復・再結晶に分類されます。(つづく) 参考文献
|