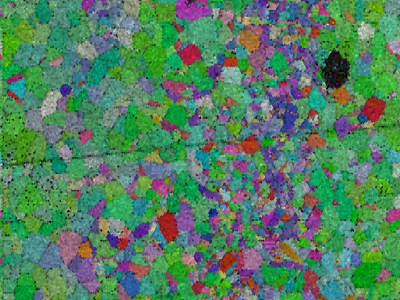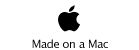My Blog

EBSD(3)
前回、EBSDではデータを取得した後が大事だとだけ、書きました。そこのところを説明するのは、なかなか大変で、筆者の手に余るような気もします。しかし、少し回り道をしながら、ゆっくりと話してみたいと思います。
EBSD法で取得したデータは、測定領域をスキャンした方位情報です。測定領域である平面をグリッドに分割して、その一点、一点に、結晶方位が与えられている訳です。と、ここで、え?結晶粒の方位をはかるんじゃなかったの?と思った方はなかなか鋭いです。この解説のはじめにも結晶粒の方位を測ると書きましたし、他の方の解説でも、良くそういう表現を見かけます。論文で実験方法を説明するときも、結晶粒の方位をEBSD法で測定したと書きます。でも、実際には、結晶粒というものをあらかじめ特定しておいて、その、例えば、真ん中あたりに電子線を当てて後方電子散乱回折=EBSDパターンから、当該結晶粒の方位を測定するという風には、測定しません。できなくはないけれど、そうはしない。実際には、この段落の冒頭で書いたように、スキャンした全ての点について方位を測定します。つまり、EBSD法で得られる一次データは、結晶粒の方位ではなく、平面の一点、一点の方位情報です。そこから、実は、結晶粒を構成するという作業が入ります。
つづく。
出村
2009年5月26日火曜日