10:10-10:50
フェムト秒非線形分光による表面ダイナミックスの観測
松本吉泰(分子科学研究所 教授)
- 固体表面は、触媒などをはじめとして重要な反応場である。特に、金属表面では電子励起と熱的励起が互いに密接な関連しながら反応が進む、極めて非断熱性の高い反応場ということができる。したがって、この反応場での光化学は、この非断熱性に真っ向から取り組む格好のテーマである。本講演では、金属表面上での光誘起過程と種々のフェムト秒非線形分光による表面ダイナミックスの観測について最近の話題も含めて紹介する。


10:50-11:20
固体における超高速電子・格子相互作用ダイナミクスの計測
北島正弘(超高速現象計測グループ グループリーダー)
- 電子・格子相互作用は電子輸送、超電導、発光及び相変態など固体の諸物性を支配する重要な過程である。我々はフェムト秒レーザー励起によるコヒーレントフォノンの観察から、半導体や半金属・金属における電子・格子相互作用の超高速ダイナミクスについて計測を行っている。最近の成果の紹介と今後の方向性について報告する。


11:20-11:50
強磁場固体NMRの開発と応用
清水 禎(強磁場NMRグループ グループリーダー)
- 強磁場を利用した固体NMRに関する技術開発とそれを応用した材料分析を研究している。最終目標は、NMRが新規材料の開発に貢献することである。強磁場の利用によってNMRは他の分析技術では達成できない独自の分野を開拓できると期待されている。また、先端的大型特殊装置の共同利用など、産学官連携の中核機関としての役割も担っている。


13:50-14:30
力学的原子識別と原子操作による複素ナノ構造体創製へ
森田清三(大阪大学大学院工学研究科 教授)
- 高性能の自家製原子間力顕微鏡(AFM)を使って、原子を力学的に識別して、操作して、多種類の元素からなる複素ナノ構造体を組み立てる技術の開発状況と、応用分野について紹介する。また、関係するAFM技術のロードマップについても紹介を行う。

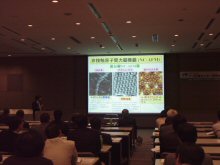
14:30-15:00
ナノ機能探索と創成のための走査プローブ顕微鏡技術の開発と応用
藤田大介(先端プローブ顕微鏡グループ グループリーダー)
- ナノ機能探索と新物質創成に資する走査型プローブ顕微鏡(SPM)技術に関する研究成果を報告する。極低温・強磁場・極高真空走査型トンネル顕微鏡(STM)、応力歪場SPM、高温場SPM、低温フォトン検出STMなどの多様な環境と多元的な機能計測に対応するナノプローブ技術の開発状況を、カーボンナノワイヤ、ナノクラスターなどの実例を用いて紹介する。
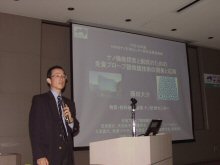
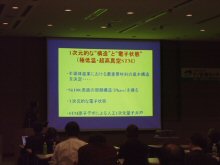
15:00-15:30
広域表層3次元ナノ解析技術の開発に関する研究の概要
田沼繁夫(先端表面化学分析グループ グループリーダー)
- AES、EPES、XPS、EPMA等により非破壊3次元分析を可能とする3次元広域シミュレーター開発の計画とその現状について報告する。特に固体中における非弾性散乱データベースの開発について言及する。
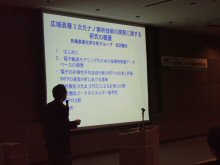
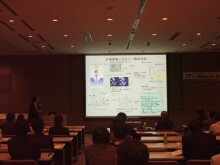
15:50-16:30
TEMその場観察による物質極微プロセスの解析
森博太郎(大阪大学超高圧電子顕微鏡センター 教授)
- 電子顕微鏡法の最大の特長は、およそ1mmにも及ぶ広い視野の中から必要に応じて次々と領域を選び出し、その領域の顕微鏡像を高い空間分解能(例えば 200kV電子顕微鏡で0.2nm程度)で迅速に記録できることである。このような全体と局所とを合わせ観る研究手法は、材料が全体として示す特性を基本となるミクロ構造ナノ構造にまで溯って調べる上で忘れてはならない手法である。さらに近年における電子顕微鏡装置の目覚しい進歩は、顕微鏡像を得たその同じ〜1nmスケールの領域からの電子回折や組成分析・結合状態分析を可能としている。このような利点を備えた電子顕微鏡法は、従って、ナノスケールの物質あるいはナノスケールで組織制御された材料を解析するためのきわめて有力な研究手法となる。こうした電子顕微鏡法の特長にさらに時系列の情報を加味したその場観察法は、ナノスケールでの微構造解析や動的過程の解析に不可欠の手法となっている。本講では、この手法によって、格子間原子集合体の一次元往復運動やナノ粒子における合金相形成の基本ルールを調べた結果について報告する。

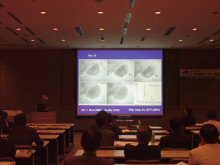
16:30-17:10
高性能電子顕微鏡の開発と先端物質材料研究への応用
松井良夫(先端電子顕微鏡グループ グループリーダー)
- ナノ計測センター先端電子顕微鏡グループでは、これまでに桜地区と並木地区の2台の超高圧電子顕微鏡をはじめとして、エネルギーフィルター型分析電顕、極低温ローレンツ電顕、ホログラフィー電顕、高分解能走査透過型電顕(STEM)等の、先端的な電子顕微鏡の開発を行い、酸化物超伝導体をはじめとする先端材料の解析や、ナノ構造のその場原子レベル解析等に応用して成果を挙げてきた。今後は、収差補正技術、電子源単色化技術や新しいスペクトロスコピー等の先進要素技術を取り入れた高分解能・高識別分析電子顕微鏡の開発を積極的に推進し、ナノレベル可視化技術のより一層の高度化と、先端材料への適用を進めて行く。講演では、電子顕微鏡による原子配列、電子状態、スピン状態(磁区)のナノレベル解析手法の最新動向について、酸化物系超伝導及び磁性材料への応用事例を交えて紹介する予定である。

